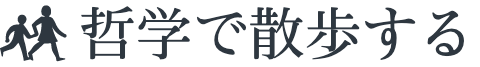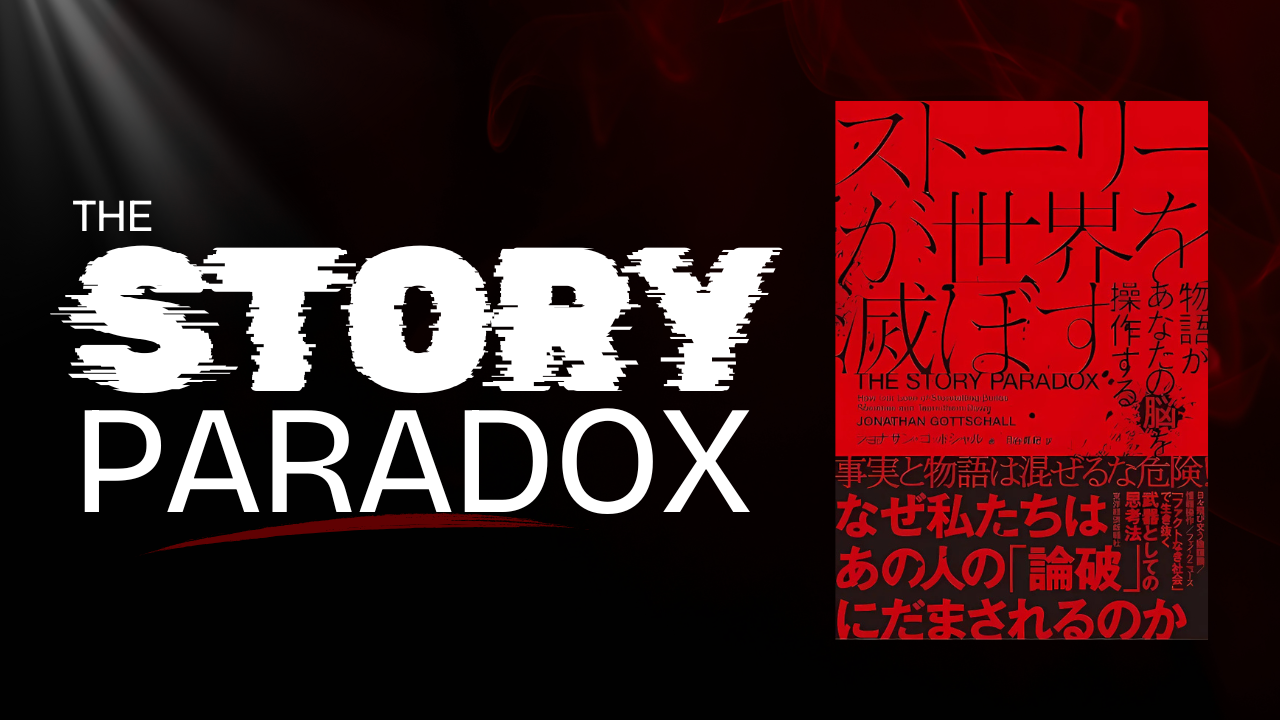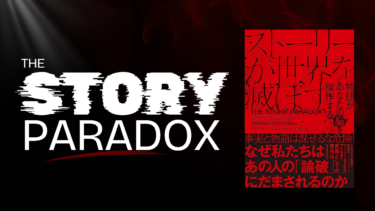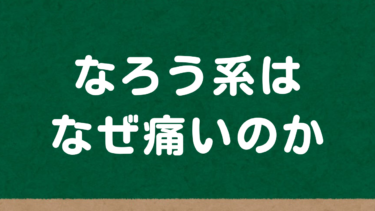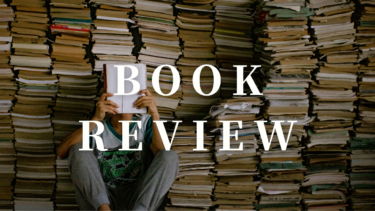内容についてはこちらから↓
SNS上ではさまざまな情報が飛び交っている。それらは、単なる情報なのではなく、発信者の感情や立場を背景に、加工された情報であることが多い。同様に、従来のメディアである新聞やテレビも、長らくそのような加工をしてきたことが、視聴者の知るところに[…]
前編はこちら↓ [sitecard subtitle=関連記事 url=https://www.sou-philosophia.com/the-story-paradox1] 前編では、物[…]
『ストーリーは世界を滅ぼす』の考察
本書では、ストーリーの負の側面に対して、4つの対応策が示されていた、と思われる。そこで、それら4つの対応策に対して、それぞれ、考察と批評をしていく。
寛容さ
物語の負の側面の解決策として、本書の結論の一つは、物語に囚われた人に対し、寛容になれというものだった。その理由は、人は物語を本能的に愛好するからであり、また、どのような物語を選ぶのかについても、生まれ、あるいは環境によって決定されており、自由であるとはいえないからである。寛容になることで、別々の物語に囚われていて、そこから逃れられない人々同士が対立し合うのを避けることができる。
しかし、寛容さには、人を見下す要素を含んでいる。寛容さとは、いわば、一段上からものを見ている態度である。たとえば、大人は子供に対して寛容だが、それは、「子供は未成熟であるから、しかたがない」と思うからであり、この思考には、大人である自分よりも子供である相手は劣った存在であるという前提が潜んでいる。
お互いに対等な立場での寛容さもありえるが、その場合は、一時的に相手より一段上に立つことで寛容になる。たとえば、「そういう事情があったならば、仕方ない」などのように、通常は非難されるべき行為であったとしても、やむを得ない事情があったとして、一時的に、一段上の立場に立ち許してあげるという意味合いが含まれるだろう。
つまり、寛容さとは、相手を許してあげるという意味を含むため、自分が相手よりも優位な立場に立つような態度なのである。では、このような態度は本当に根本的な解決になるのか。
仮にある陰謀論を信じている相手がいたとして、その人に対し、それを信じていない自分が寛容さをもって対応したとする。そうすれば、確かに、自分は相手と対立することはないかもしれない。しかし、相手の方から見ればどうだろうか。相手は自らが信じる物語に対して、その物語を受け入れるわけでもなく、「あなたはその物語を信じているのですね、理解します」とわかったような顔で言ってくる相手をどう思うだろうか。おそらく、真剣には取り合ってもらえておらず、なにか見下され、憐れまれたと思うのではないだろうか。この構図は、なんらかの被害者に対して、第三者が訳知ったような顔で、「わかります」というときに、その被害者が覚える怒りに近いだろう。
つまり、寛容さは確かに、その物語を信じていない側が、物語を信じている人々に対し、対立しようとしないことには寄与するが、物語を信じている人々は、そのような寛容さを上から目線の押し付けがましい善意であると捉え、より強固な分断を生む可能性は大いにあるのである。
物語と人の関係の研究
本書では、物語と人の関係についての研究がまだ発展途上であると述べられていた。物語同士が対立し合う現代において、物語や物語が人に及ばす影響についての研究は求められるだろう。
ただ、錯覚についての研究が、錯覚を消し去ることはないし、バイアスやステレオタイプの誤りを示す研究も、それらを世の中から消滅させてはいないという事実がある。その原因は、人々がそういった研究を知らないからという可能性もあるだろうが、おそらく、知っていてもそこから逃れるのが困難なのだろうと思われる。
もっと身近な例で考えれば、たとえば、課題を先延ばしすることは良くないことは全員が知っている。知ってはいるが、それでもやってしまう。これは、人間の悪癖全般について言えることだ。
であれば、確かに人間にはどのような性質があり、それがどのような悪影響を及ぼしうるのかを研究することは大事だが、それを社会において、実行させるのはまた別の問題であるのだろう。あるいは、それも含めた研究ができれば良いと思う。
科学の権威
本書では科学とは、真実らしさではなく、真実を強制的に見せるものであるため、物語の脅威に対して有効であるとされている。そのため、科学の権威を取り戻し、真実らしさから、真実へと向かうことが解決策になるとしている。
このことは、事実であろう。科学は、科学者たちによって共有された検証の方法によって、物語を排除する。これは、物語を排除する方法として優れているだろう。
しかし、そもそもの問題は、人は物語への愛着を離れることができないということだった。そのため、物語から科学への移行はうまくいかないだろう。
悪役のいない物語
本書では、悪役のいない物語が、物語の負の側面を解決する可能性が示唆されていた。
悪役が登場し、正義の味方がそれをやっつけるという単純な物語の構造は、シンプルでわかりやすいが、それだけでは現代の物語として稚拙であろう。多くの物語は、悪役を登場させるにしても、その悪役にも悪役の事情があり、実は単純に悪だとはいえないのではないかと問いかけるような展開をもっている。あるいは、悪役を誕生させた原因は、私たちにあったのではないかという展開も多い。
このような物語の構造が一般的であるならば、現実世界においても、単純な善悪の対比のような構造で世界を見ることはないだろう。
だが、最近では、人々はそういった単純な物語に回帰しようとしているのかもしれない。それは、ネット上のさまざまな陰謀論の跋扈や、極端な主張、特に排外主義、あるいは感情的な意見の増加が示唆している。
いずれにせよ、どういった物語を作り出すかをコントロールすることは、現代のこの社会ではできないし、するべきでない。となると、物語の発生は自然に任せるしかないのだが、そのようにして生まれる物語は、人々の現状を反映し、人々の求めるものとなっているだろう。
ということは、物語の負の側面に対する解決策として、悪役のいない物語を作るということは、難しいだろう。むしろ、現在、社会において、どのような物語が流行っているのかを分析することで、人々が社会をみるときに用いる物語(ストーリーバース)が何であるのかを知ることができるだろう。
まとめ
以上のように考えると、物語の負の側面から社会を救うことは難しいように思える。
事実、本書においても、寛容さを主な解決策としているが、その理由は、自分だけでも物語の威力について自覚し、自らが物語に囚われすぎないようにし、同時に、物語に囚われている人を非難しないようにするためだからであった。
ここでは、物語の脅威を自覚し寛容になれる自分たちと、物語の言いなりになってしまう人たちという線引きを暗黙のうちにしていると思われる。つまり、物語が生み出す分断をなくそうという解決策が、新たな分断を生んでいるというまさにパラドックス的な状況が存在する。
そもそも人が何を信じるのかは、その人の自由である。陰謀論を信じるのも自由である。それが、その人のためにならないといって、その人の思想に干渉することは、その自由を侵害している。その人の自由か、それとも幸福かどちらが優先されるべきなのかは難しい問題だが、現代の社会は、個人の自由を基本的には優先している。
このような思想の自由がある以上、その自由が発揮されれば、分断が生じるのはやむを得ないのだろう。そうであるならば、人々が物語に囚われ、分断した先に、それでもなお対話を可能にする方法が求められるのだろう。それは、おそらく、科学のような真実を求める方法ではなく、物語間を行き来し、通訳のようにお互いを対話可能にするようなそんな技術なのかもしれないと考えた。