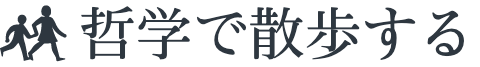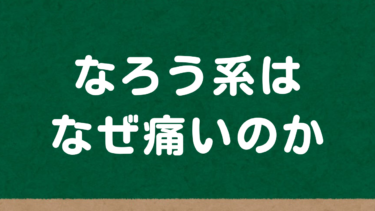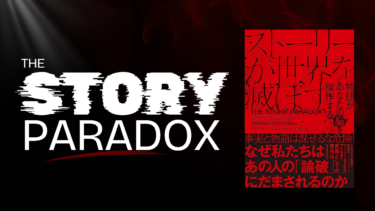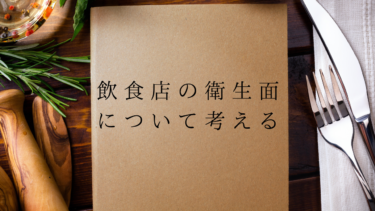先日、大阪府の商業施設にあったストリートピアノの運営が出した声明が議論を呼んだ。[1]その声明の内容は、端的に言えば、ストリートピアノは練習用ではなく、人に聞かせるものだから、ある程度弾けるようになってから弾いてくれというものだ。
この件は一見ありふれた炎上のようだが、この一連の議論は、公共の場に対して考察するのに適していると考えられる。そのため、この記事では、この議論について分析し結論を出した後に、公共の場のあり方について考察する。
議論の分析
まず、議論の内容を分析する。
声明に賛成派
賛成派の意見は明確で、下手な演奏のピアノを好んで聴く人はいないというものだ。
また、公共の場である以上、自分の演奏が他者に聞かれることを想定するべきである、とする。
撤去に反対派
一方の反対派は、演奏に失敗はつきものであり、上手くなければ演奏してはいけないという主張は、「もっと身近にピアノに触れる機会を作ろう」というストリートピアノの趣旨に反するとする。
問題の整理
この議論には、以下の二つの論点が含まれている。それは、
・ストリートピアノで練習をするのは良いのか
・ストリートピアノで下手な演奏をするのは良いのか
である。
前者は、初めから自分の練習のために弾いており、人に聴かせようとしておらず、上手く弾こうとはしていない。後者は、人に聴かせようとしているが、力不足で結果的に上手く弾けていないということだろう。
両者は、結果として上手く弾けていないことで共通しており、違いはその意図にのみある。演奏者がどういった意図で弾いているのかを見分けることは困難であるため、ここでは、練習について論じることにする。
ストリートピアノでの練習は許されるべきか
このことを考えるには、「ストリートピアノ」というものが、演奏を周りの人に聴かせる目的をもっているのかどうかを考える必要がある。仮に周りの人に聴かせる目的をもっているのならば、練習や質の低い演奏は控えるべきかもしれない。
しかし、「ストリート」ピアノという名称である以上、それは、道などの公共の場に設置されており、演奏を立ち止まって聴くことを主目的にはされていないと考えられる。つまり、その演奏を周りの人が長時間意志に沿わず、耳にすることは想定されていないといえる。
したがってストリートピアノとは、公共の場を歩いていたら耳にする程度のものであり、もし良い演奏ならば、それを聴くために立ち止まることもある、というようなものだろう。仮にその演奏が下手である、あるいは練習であっても、聞く側は通行人であるため、それをさほど不快には思わないだろう。
結論として、練習なのか演奏なのかを区別することが困難であり、かつ、仮に演奏が下手であっても、周囲の人にさほど迷惑をかけるわけではないため、ストリートピアノにおいて、練習は許されるべきだろう。
今回の論争においては、ピアノの設置場所が、「ストリート」ではなく、長時間耳にせざるを得ない場所であったため、ストリートピアノという名称がそもそも適切ではなかったと考えられる。
ストリートピアノと共有地の悲劇
とはいえ、おそらく自分の練習の目的に使用することは、本来のストリートピアノの趣旨からは外れるだろう。それでもなお、許されるべきなのか。
こういったマナーの問題が生じることは、ストリートピアノに限らない。不特定多数の人物に対して解放された施設は、当初はマナーの良い人が利用し合うのだが、知名度が上がるにつれ、「マナー違反」と呼ばれる使い方をする人が現れ出し、それに対してクレームが入り、最終的に撤去されるというパターンが多い。今回もこのパターンである。
こういったパターンは、「共有地の悲劇」と呼ばれる問題と類似しており、問題にされ続けてきたことである。共有地の悲劇とは、「多数者が利用できる共有資源が乱獲されることによって資源の枯渇を招いてしまうという経済学における法則」[2]のことである。施設の利用は資源の乱獲や枯渇ではないものの、自己中心的な利用によって、最終的に使えなくしてしまうという点で共通である。
ルールの不寛容さ
このような「悲劇」に対して、「資源を保つ=撤去しない」ためにはどうするべきか。「共有地の悲劇」が昔から存在することを考えると、共有施設を自己中心的に利用する事例は避けられないだろう。今回のストリートピアノでいえば、練習目的の使用は、自己中心的利用といえるだろう。なぜなら、共用の施設を自分の利益のためだけに利用するからである。
しかし、単に共用施設を自己中心的に使うことは問題ではない。それが、周りに対してどの程度の害を与えるかが問題である。ストリートピアノでの練習あるいは下手な演奏は、それを長時間聞くわけではないので、害の程度は低いといえる。害の程度が低いとは、許容可能であるということでもある。確かに厳密に言えば、一瞬でも下手な演奏を聞かされることは、害になるのかもしれない。また、確かにストリートピアノの本来の趣旨とは外れるかもしれない。
だが、だからといって、それらのちょっとした害も、全て厳密に排除しようとすることは、それほど問題とはならないような害をも許容しないということである。これは、害を排除し、公共の場に善をもたらそうという善良な動機であるにもかかわらず、かえって不寛容を助長しているといえる。なぜなら、厳密な害の排除を求める動機が、自らに対する一切の被害も許容しないという過剰な被害意識にもとづいていると考えられるからだ。
ではどうすればよいか。そもそもどの程度の害であれば許容可能なのかは、人によって異なるし、場合によっても異なる。であるならば、ルールによる一律の基準を設けるのではなく、その都度当事者同士で交渉して、何をしても良いのかを、その場において判断するようにすればいいだろう。
仮に交渉がトラブルに発展するリスクがあると感じるのならば、その場から立ち去ればよいのだ。ストリートピアノのような公共の施設において、その場から立ち去ることは、さほどのデメリットにはならないはずだ。もし問題になるとすれば、「なぜ私が我慢しなければならないのだ」という怒りのような感情だろうが、この感情にもとづいて規則を増やしていくことは、公共の施設を規則でがんじがらめにし、生きづらい世の中を作ることになる。
公共の場のあり方
公共の場とは、不特定多数の人間が自らの利益のために利用する場である。不特定多数の人間が自らの利益を追求し、自らの価値観に応じて行動するため、いくら共通の常識が存在しようと、完全に規則・マナーを守った「正しい」空間を作ることは不可能である。
そもそも、人間社会において、完全な公平性や善を実現しようということは不可能だし、目指すべきでない。であるならば、ある程度の害については許容し、本当に許容できないことに対してのみ処罰をするべきである。その線引きをどこにするのかが重要で、許容範囲を狭くすることは、そのまま人々の許容範囲を狭め、ちょっとしたことも許容しない生きづらい世の中を作ることになるだろう。
また、少しの害をも許容できないという精神には、過度な被害者意識があり、自らの被害に対する過剰な不寛容さがあるだろう。こういった感情は、他者に対する敵対心や暴力性と直結しているため、社会的にも問題があると思われる。要するに、社会に、より自由や、ゆとりをもたせたほうがよく、そういった自由やゆとりを生み出す実験としてストリートピアノのような施設は優れているので、多少のトラブルでなくしてしまうべきではないだろう。