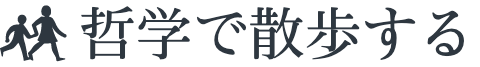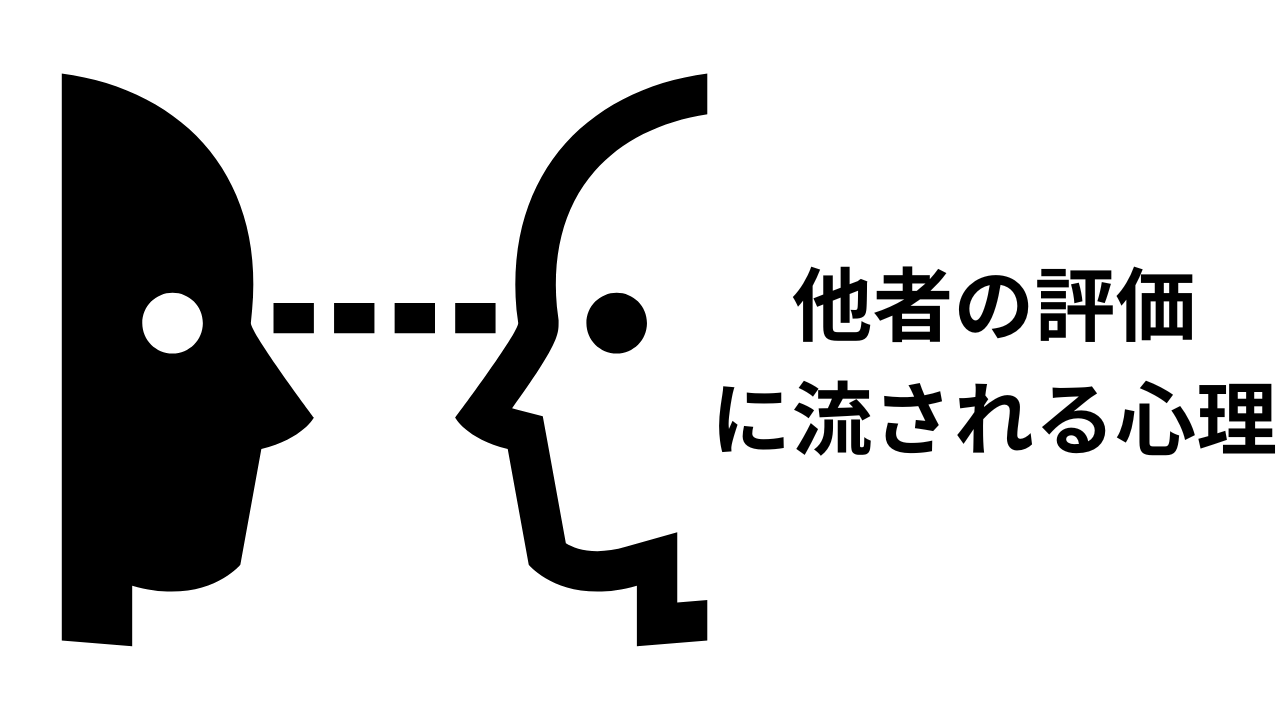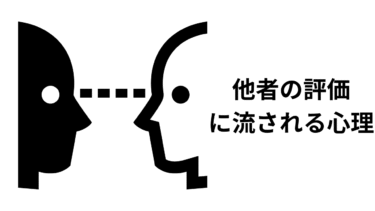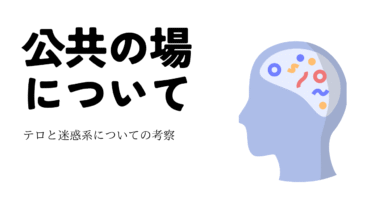最近では、レストランや映画など、あらゆるコンテンツにレビューサイトが存在する。そういったサイトは参考になるのだが、サイトのレビューに影響を受けやすくなってもいる。つまり、レビューという他者の評価に流されやすくなっている。
このような他者の評価が溢れ、それに流されやすくなっている現代では、自分の意見ではなく、他者の意見で評価するということさえ一般化しつつある。
この記事では、このような、評価されていることを評価するという心理について分析し、その原因について考えていく。
通常の評価
通常、何かを評価するとき、自分がそれをどう思ったかによって評価する。映画が面白ければ、面白いと評価するし、つまらなければつまらないと評価する。つまり、自分がそれをどう思ったかがそのまま評価になる。
このような評価の場合、評価される対象と評価する自分は、一対一の関係であり、他に関係のあるものは存在しない。つまり、評価の際に、評価対象と自分以外のものは存在しないのであり、この関係は排他的な関係である。
なぜ排他的な関係が成立するかというと、評価対象には評価される根拠が存在し、その根拠を評価者が見出すことができるからである。
たとえば、美味しい料理を食べたとき、その料理自体に美味しさが存在するし、それを食べる人間は、その美味しさを感じ取ることができる。映画の場合は、その映画に面白い要素が含まれていて、それを観た人間はその面白さに気づくことができる。
つまり、評価対象に含まれる評価の根拠を、評価者は感覚や思考を通じて理解し、直接それについて評価できるのである。そのため、このような評価を直接的評価、一次評価とみなすことができる。
他者の評価に依存した評価
他者の評価に依存した評価は、他者の評価を根拠に、評価対象を評価する。たとえば、映画が面白いという評価があるなら、その映画は面白いのだと評価するし、この料理はまずいと評価されていれば、それをまずいと評価する。
このような評価の場合、評価される対象と評価者の一対一の関係ではなく、中間に別の評価者(たち)が存在する。そして、評価対象を直接的・一次的に評価しているのは、その別の評価者(たち)であり、評価者はその別の評価者の評価をそのまま自分の評価としている。
つまり、このような評価は、間接的評価、あるいは二次的評価といえる。
なぜ他人の評価に流されるか
自分の評価が、他者の評価に流されるパターンは、いくつかある。
①自分の評価に自信がない
直接的な評価の場合、評価対象を評価するのは自分であり、その際、自分の評価基準を用いる必要がある。料理を評価するならば、自分の味覚を基準にしなければならないし、映画を評価するならば、自分のセンスや知識を基準にしなければならない。
評価対象がわかりやすいものならば、評価することは難しくない。だが、複雑さや難解さをもつ対象を評価するときには、自分がもつ評価の基準ではそれを評価することが難しいことがある。たとえば、複雑な味付けの料理を評価することは、そういった味に慣れていないと難しいかもしれない。難解なテーマをもつ映画を評価することは、前提知識がなければ難しいだろう。
こういった場合、そもそも評価することが難しいので、自分の評価に自信がなくなることは致し方ないだろう。その際に、他の人はどう評価しているのだろうかを知ることで、自分ではできない評価を補完しようとするのである。
特にそれを言語化し、他者に伝えようとする場合は、さらに難しい。そのため、すでに存在する評価に依存してしまうことがあるのだろう。
②自分を評価してもらうため
何かを評価することによって人の関心を惹くことを考える場合、すでに存在する評価に則った方が良い。
たとえば、多くの人が良いと言っている映画ついて、自分もそれを褒めれば、その評価・感想に共感してくれる人は多いだろう。リアルの場では、友人の共感を得られるし、ネットでは好意的な反応を得られるだろう。それゆえ、自分の評価を他者の評価に合わせるということがあり得る。
これを意図的にやっているならば、他者の評価に「流されている」とは言えないだろうが、他者の反応を得ることを目的にしているということは、承認欲求に流されているともいえる。そのため、他者からの評価が欲しく、他者の評価を流用している点で、二重に流されているともいえる。
③評価されていること自体に価値を見出す
これは、以前、ブランド志向を分析する記事で出した結論だが、人は、価値があるとされているものに対して、価値があると考える傾向にある。その際、価値がある原因は、物にあるのではなく、価値があるとされていることにある。
たとえば、ブランドものの服は、そのブランドであるというだけで価値があるとされる。その主要な原因は、その服の品質ではなく、そのブランドに価値があるとみなされているからである。
このように、価値があると評価されることは、それ自体が価値として扱われるのである。
その場合、その価値の根拠がどこにあるのかは問われない。つまり、評価対象に、評価すべきところがあるのかは問われないのである。そのため、評価対象とその評価が結びついていないことになる。いわば、実体のない宙に浮いた価値なのである。
このような価値の代表例は、「流行」だろう。今年はこの色が良いなどさまざまなことが言われるが、その根拠は存在しない。根拠がないため、いずれ終息するのである。
以上から、評価されていること自体が価値となるため、他者の評価に流されて評価することは、価値があるとされることを評価するためには、適切であるともいえる。
まとめ
以上、価値を評価する過程について考えた。そして、そこに第三者の評価が介在する原因についても考えた。その原因はどれも評価するという行為が自己完結的でないことにあるだろう。
自分の評価があっているのかの不安や、自分の評価が評価されるのかや、他者の評価自体に価値を見出したりである。
こういったことは、評価することの一部でもある。ただ、評価する対象と自分の一対一の関係がなくなってしまうと、自分の評価=ものの見方全てに他者の考えが介入してくることになる。
また、他人の評価を気にして、自分の素直な評価・感想が抑圧されてしまうと、自分自身が希薄化してしまうだろう。
いわば社会性によって奪われた素直な感想を、他者を介在させない対象との関係のうちで取り戻すことは、自分自身を知るためにも大事であると思う。