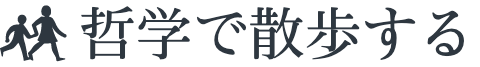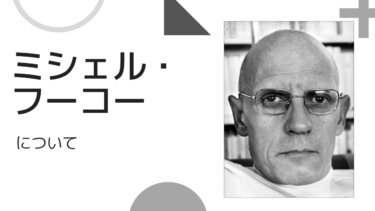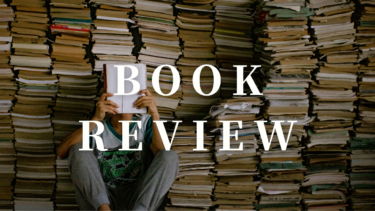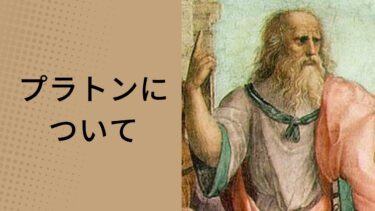現代は感情が過激になっていると思われる。その理由は、主にSNSの普及によって、不特定多数に通じやすく、より感情を掻き立て、注目を集める言説が流布しやすく、それが感情的に過激なものだからだろう。(前回の記事で詳しく論じた)
この記事ではまず、現代において感情が過激化している事例を取り上げ、分析する。その上で、そのような過激な感情から自己を保ちつつも、どのように社会と関係していくべきかを考える。
感情が過激化する現代
現代には、過激な言葉が流布している。たとえば、以前にも取り上げたが、「ビジュ」や「学歴厨」など、ある価値基準を過激に信奉する人々がいる。特に、ルッキズムは、その加熱が著しいだろう。
政治においては、トランプ大統領を筆頭に、各地で単純なストーリーに基づいた主張がなされている。
エンタメのコンテンツは、ショートコンテンツとなり、より短く、よりインパクトのある刺激の強いコンテンツが席巻している。
ニュースはスキャンダルに事欠かず、常に他人についての情報を垂れ流している。
すなわち、現代では、より感情を煽り、より人々に刺激を与え、より強力に人々の心を捉え、より行動を左右させるような言説・コンテンツ等の情報が氾濫しているといえる。こうしたことは、昔からだったのかもしれないが、記憶にある限りでは、最近になってさらに過激化している。現代にはそれを過激化させる仕組みがあるからだ。
その結果、それらの需要者である人々は、まるで常に刺激を求め続けているかのようである。常にお祭り騒ぎをしているといってもいいかもしれない。
統一的自己の喪失
このような情報に個人が晒されることは、統一的な自己の喪失を引き起こす。
なぜなら、現代において、こうした刺激の強い情報は、一時的に人々を興奮させて消滅していくのではなく、次から次へと変化し、人々を興奮させつづける。ある興奮が人々の精神を占領し、また別の興奮がやってくる。このサイクルが止むことなく繰り返される。演目が変わりながらも永遠に公演をやめない舞台、あるいは無限にスクロール可能なTikTokなどのショート動画のようである。
つまり、現代社会には平時がなく、興奮が人々を攫い続けるような非現実が永続しているといえる。
このような状態では、人は常に外的な情報に攫われており、自分自身の現実が失われる。あるいは、人が統一的な人格を保つことが困難になる。なぜならば、人は常に新たな刺激によって、非現実に連れ去られ、書き換えられていくからだ。
上述したことは大袈裟に思われるかもしれないが、現代人が常にスマホを手にしており、その画面に表示される刺激に晒され、自分の人生を生きることをおろそかにしているという言説は、もはやありきたりなものでさえあるだろう。
したがって、現代において、ゆっくり腰を据えることや、何かに時間をかけることは難しくなっている。自己を時間をかけて振り返ることが、統一的な自己を形成する方法なのだとしたら、そういった自己は失われつつあるといえる。
社会的でありながら自己を保つ方法
では、こうした社会から離脱し、山籠りでもすればよいのか。あるいは、すべての情報を遮断し、世捨て人になるか。
前回の記事の結論は、価値尺度を相対化することで、すべての価値の尺度から逃れるというものだった。これは、すべての無意味化であり、あらゆることから離脱することであり、突き詰めれば世捨て人的な生き方になる。
しかし、今回はその次の段階として、積極的な段階を考えたい。つまり、社会と接続しつつ、どのように社会の渦に巻き込まれることから逃れ、個人であり続けるか。卑近な例で言えば、みんながパニックになって買い占めているなかどう冷静さを保つか、ということである。
この問いに対して、『攻殻機動隊SAC』というアニメでは、「好奇心」を答えとしている。自己を他者と同化させる情報の波のなかで、いかにして自己を保つのかの解決策として、外部との交渉を動機づけ先導する内発的な因子としての好奇心が挙げられている。
自己の内部に存在し、自己を動機づけ、自己の外部と交渉させようとする因子。その一つとして、好奇心はある。しかし、それは欲望と何が違うのか。社会の熱狂に身を任せ、興奮したいという欲望もまた、内在的な外交因子だろう。
プラトンは、欲望に囚われた人間を不自由であるとした。それは、プラトンにとっての人間のモデルが、理性によって欲望を統御するものであったからだ。つまり、人間の本性を理性的なものとしたからだといえる。だが、理性が人間の本性である根拠については、神話に頼らざるを得ない。ニーチェは、プラトンの図式である理性と欲望を逆転させようとした。
好奇心にせよ、欲望にせよ、自己の内側にあって自己を突き動かす因子は、自己のコントロールを外れたものである限り、非自己であるともいえる。あるいは、こういえるかもしれない。全ては非自己であり、問題はどの非自己を選ぶかであると。そして、その選ぶ者もまた非自己であると。
となると、自己と非自己は何か。そうありたい自分は何によって決定されるか、という新たな課題が生まれる。
直感を信じる
自己と非自己の複雑な問題は一度置いておいて、現代社会においていかに自己を保つのかという問題の解決策を提示する。
その一つとして、「直感を信じる」というものがありうる。使い古された言い回しではあるものの、暫定的には大事な回答だろう。
まず、自己と非自己を厳密に区別する前に、現に、自分が自分でないものによって悪影響を受けていると「感じている」という事実を第一に考える必要がある。その感覚は、何かしら自分と自分じゃないものを区別する感覚であり、それは、自分にとって良いこと・やるべきことと、悪いこと・やるべきでないことを区別する感覚でもあるはずだ。
それは、自分の中に埋め込まれた良心のようなものだ。自分が本当は何をするべきなのか、自分はどうありたいのかといった自分自身に関することを、良心は直感的に教えてくれる。もちろん良心についてもそれが何なのか、それは本当に正しいのかや社会的な常識に囚われているのではないか、といったことを考える必要はある。
だがおそらく、良心は、自分についてのこれまでの経験と、社会の他のサンプルを通して、妥当なことを導くだろう。少なくとも、それがその時の自分にとって可能な最善であり、やれるだけのことをやった実感は残るだろう。大抵後悔するのは、やっておけばよかったとわかっていたのにしなかったときであるからだ。