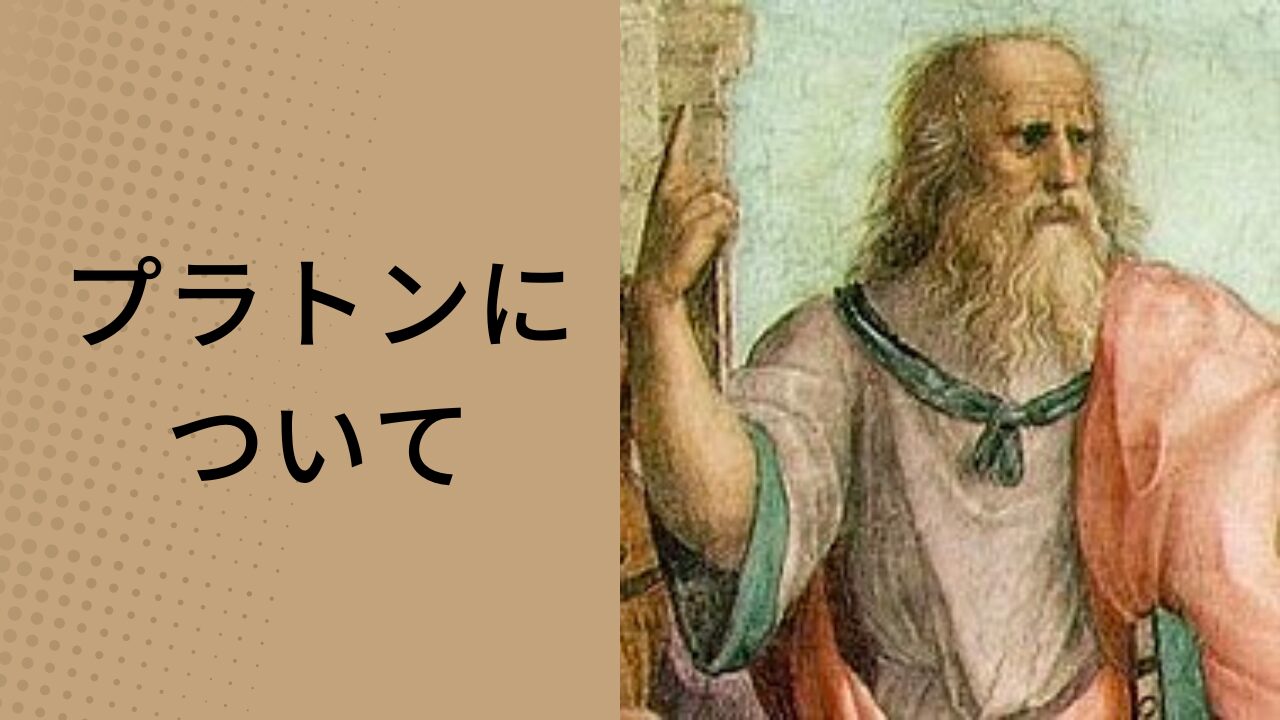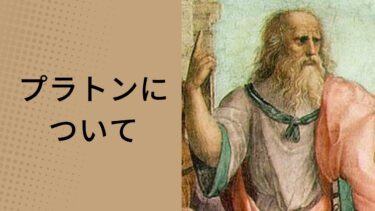今回は、中期プラトンの思想を扱っていく。
この記事では、まず、魂が不滅であることの証明とそれに密接に関係するイデア論を論じ、その後に、魂が善くなるとはどういうことかについて、プラトンが用いた洞窟の比喩を説明することにする。
前回の記事はこちら↓
今回から、プラトンの思想を初期、中期、後期の順に流れで扱っていく。流れでみていくことによって、プラトンの関心の一貫性と、その関心をもとに思想がどのように展開されていくかがわかるからである。 ということで、今回の記事では、プラトンの初期[…]
中期プラトンの著作一覧
・『饗宴』:エロース(恋)について
・『パイドン』:魂の不死について
・『国家』:正義について
・『パイドロス』:エロースについてなど多岐にわたる
魂不滅の証明とイデア論
前回扱ったように、プラトンの倫理を正当化するには、現世を超えて存在する魂が存在しなければならない。そのため、プラトンはまず、魂が永遠不滅であることの証明を行う。その証明には、イデアという概念が登場する。
イデア論とは何か
イデアとは、形相や「そのもの」と訳される言葉で、元々は「形」や「姿」を意味する(2-1-1)。プラトンにおいてイデアは、「その名前で呼ばれている当のもの」を意味する。たとえば、美しいという名前で呼ばれている当のもの、すなわち、美しさそのものを美のイデアと呼ぶ。
そして、このイデアによって、すべてのものがそのイデアのようになるとされる。この理論が、イデア論である。たとえば、美しい花が美しいのは、美のイデアによる。この美のイデアは、個別の美しいもの(たとえば花や景色など)と関係し、それらを美しくする存在である。
なぜ美しさの原因がイデアにあると考えるのか。それは、個々の美しいもののなかに、どんな場合でも美しいといえるような、美しさの原因が存在しないからである。美しい花の場合、その色や形が美しさの原因のように思われるが、色や形を単独で抜き出しても、それ自体は美しくない。また、ある人には美しく感じるとか、別の花の前だとその美しさが霞むといったことがありうる。
また、人間は、全く異なる個々の美しいものを見て、それらを皆、美しいと感じることができる。花であれ、人であれ、景色であれ、それらをすべて「美しい」と感じる。このように、全く違うものを見ながら、それらを同じ「美しい」と感じるということは、それらの個々の事物に美しさの原因があるのではなく、それらとは別に何かを美しくするものが存在する、とも考えられるだろう。
イデアの存在する場所
このように、イデアは、個々の事物のなかには存在せずに、個々の事物をそのようにする原因である。個々の事物の中に存在しないならば、イデアはどこに存在するのか。
それは、この世界、すなわち、今目の前にある世界ではない。なぜなら、この世界は、個々の事物によってできているからである。よって、この世界にイデアは存在しないということになる。
イデアの存在する場所を、プラトンは、この世を超越した天上の世界であるとした。天上の世界は、現世やこの世界と対になる世界で、永遠不滅の世界であるとされる。
想起説による魂不滅の証明
こうして、美しいものが美しい原因が、天上の世界に存在するイデアによるとされたのだが、そうなるとある困難が生まれることになる。それは、人はなぜ個々の美しいものや善いものなどを見て、美や善という概念を認識できるのか、である。
イデアとは、それそのものであり、個々の事物をそのようにする存在である。美のイデアであれば、美しさそのものであり、個々の事物を美しくする原因である。しかし、個々の事物は、イデアではない。つまり、美そのものではない。そもそも、個々の美しいもののなかには、美しさの原因がなかった。しかも、個々の美しいものは、常に誰にとってもどんな状況でも美しいというようなものではなかった。つまり、個々の美しいものは、美のイデアとは異なり、不完全な美なのである。
このような不完全な美であるにもかかわらず、それを見ることによって、美を認識できるのはなぜか。要するに、それ自身では美とは言えないような個々の事物を見ることで、なぜ美という定義上完全な美を認識できるのか。プラトンは、この問題を想起説と呼ばれる説を用いて説明する。
想起とは、思い出すということである。つまり、本来認識できないはずの美を認識できるのは、もともと美を知っていて、それを思い出しているからだ、とするのである。どういうことか。プラトンは以下のように説明する。
人の魂はもともと天上の世界に存在し、そこで同じ天上の世界に存在するイデアを知っていたのだが、肉体を具えこの世に誕生することで、肉体的な感覚によって惑わされ、いわば目を曇らされる。その結果、生まれる前に身につけていた知識を忘れてしまう。
しかし、誕生以前に知り得たイデアを完全に忘れてしまっているわけではない。何かそれと似たものを通して、イデアを思い出すこと、想起することができる。たとえば、個々の美しいものを通して、それ自体からは知りえない、美しさを知ることができる。これは、魂が、忘れてしまっていたイデアを、それと似た美しいものを見ることで、思い出すからである。
このように、なぜ美や善などの完全な概念を知りうるのかということに対する答えを通じて、プラトンは人の魂が誕生以前から存在するということを証明するのである。
魂を善くするための方法
プラトンは、以上のような魂不滅の証明(3-1)をもって、魂が人間の一生を貫き、それを超えて存在する、人間の核のようなものだとすることができた。その次のプラトンの目的は、魂を善くする方法であった。
魂を善くするためにはどうすればいいか。その方法は、二つの比喩によって語られている。一つは、対話篇『国家』に登場する「洞窟の比喩」で、もう一つは『パイドロス』に登場する「馬車の比喩」である。
まず、「洞窟の比喩」、次に「馬車の比喩」を論じる。
洞窟の比喩
洞窟の比喩とは、以下のような話である。
人間は、生まれつき洞窟の中で過ごしており、その洞窟で焚かれている篝火によって生じる影絵を見て過ごしている。生まれてからずっとその影絵を見ており、それ以外を見ていないため、人はその影絵こそが本物の存在であると思い込んでいる。
そんななか、哲学者は、この影絵が本物ではないことに気づき、その洞窟を後にし、真実の光である太陽のもとで、真実の存在を見る。そして、再び洞窟に戻り、その真実を人々に伝えるが、人々はそれを理解せず、嘲笑し、慣れ親しんだ洞窟にとどまろうとする。だが、そうした人々を真の存在へと導けるのは、洞窟を出て、真の存在を知った哲学者だけである。
以上が洞窟の比喩の概要である。
洞窟の比喩の意味
この比喩では、洞窟の中と外が対比されている。洞窟の中には、篝火があり、影絵がある。洞窟の外には、太陽があり真実の存在がある。そして、困難だが洞窟の外へ出るべきだとしている。
この比喩において、洞窟の内外はそれぞれ何を意味しているのだろうか。
まず、洞窟の中は、人が生まれてからその中に存在し、慣れ親しんでいる世界であるとされている。そして、その世界で人が見るものは、全て、影絵である。つまり、本物の存在ではない。これは、現実の世界でいえば、個々の感覚によって捉えられる対象や、人が通常価値を見出しているもの、たとえば、富や名声に相当するだろう。
そして、洞窟の外は、太陽に照らされており、真実の存在がある。この真実の存在とは、個々の事物を根拠づけるイデアである。
さらに、このイデアを照らしているのが太陽である。この太陽は善のイデアを表している。善のイデアとは、全てのイデアを根拠づけるイデアである。そして、国を統治する者が知るべきとされているものである。
したがって、洞窟の比喩では、人が感覚的に捉えている対象や、常識、富や名声などを重んじる価値観といった慣れ親しんだ世界が、全て影のように根拠のないものであり、その世界を抜け出て、イデアを探求することこそが重要であるとしている。
馬車の比喩
馬車の比喩とは、以下のような話である。
人の魂も神の魂も同じように、二頭立ての馬車を一人の御者が操っている様に例えられる。この馬車には、羽が生えており、天上の世界へと向かって走っている。神の魂の場合は、二頭の馬のどちらも優れた馬であるため、問題なく走ることができる。しかし、人の場合は、片方の馬が劣悪であり、これを制御することは大変である。
神の馬車は、人の馬車を先導し、天上の世界に存在するイデアを目指すが、人の馬車は、御するのが大変なため、必ずしもそれについていくことができず、地上の世界へと落ちていってしまう。
馬車の比喩の意味
この比喩では、魂の構造について説明している。人の魂が二頭の馬と一人の御者からなっているとされているのは、人の魂が三つの部分からなっているとされているからだ。その三つとは、理性、情念(気概)、欲望である。理性は御者に相当し、情念は片方の問題のない馬、欲望は劣悪な暴れ馬に相当する。
我々人間は、地上に落ちてしまった馬車である。地上に落ちる際に、翼は失われ、天上の世界のことは、忘れてしまっている。しかし、何か美しいものを見たときに、それは人の心を強く捉える。美しいものは、それが視覚を通して与えられるため、人の心を強く動かす特権をもつのである。そして、この美しいものは、イデア論で論じたように、美しさの原因であるイデアと関係している。ゆえに、この美しいものを通して、美しさそのもの、美のイデアを求めていくことができるのであり、それは天上の世界を思い出すことになり、それによって、魂は翼を取り戻すとされる。
このように、個々の事物から、イデアへとその思索を深めていくことによって、人の魂は再び天上の世界へと帰還できる、すなわち魂が善くなるとされるのである。
まとめ
プラトンは、それこそがその人間であるというような、核のようなものが魂であるとした。よって、その魂を善くすることが、自らを善くすることになる。ただ、魂が死後滅びるのであれば、生前に「魂の世話」をしても意味がない。よって、魂が永遠不滅であることを証明する必要があった。
そして、その魂を、肉体的なものから解放し、イデアを求めることによって、善くすることができると考えた。
総じて、プラトンの考える善とは、魂が、身体・肉体的なものや、世俗的な価値から解放され、純粋さを取り戻し、本来の世界である天上の世界へと還ることであるといえるだろう。そのため、プラトンは、哲学を「死ぬことの練習」であるとしたのである。(4-1)
注釈
(2-1-1)『哲学の饗宴』p.135
(3-1) 魂の永遠不滅の証明はこの他にも、『パイドン』に4通り、『国家』と『パイドロス』にもそれぞれある。『哲学の歴史 第1巻』のp.477の注では、魂の不死性がプラトン哲学の「要請」であるとされている。
(4-1) [67E] 『パイドン』岩波文庫だと p.38 『哲学の歴史 第1巻』p.478 参考
参考文献
原典:
プラトン 『国家』 岩波文庫
研究書(二次資料):
荻野弘之 『哲学の饗宴』 NHK出版 2003年
内山勝利他 『哲学の歴史1』 中央公論新社 2008年