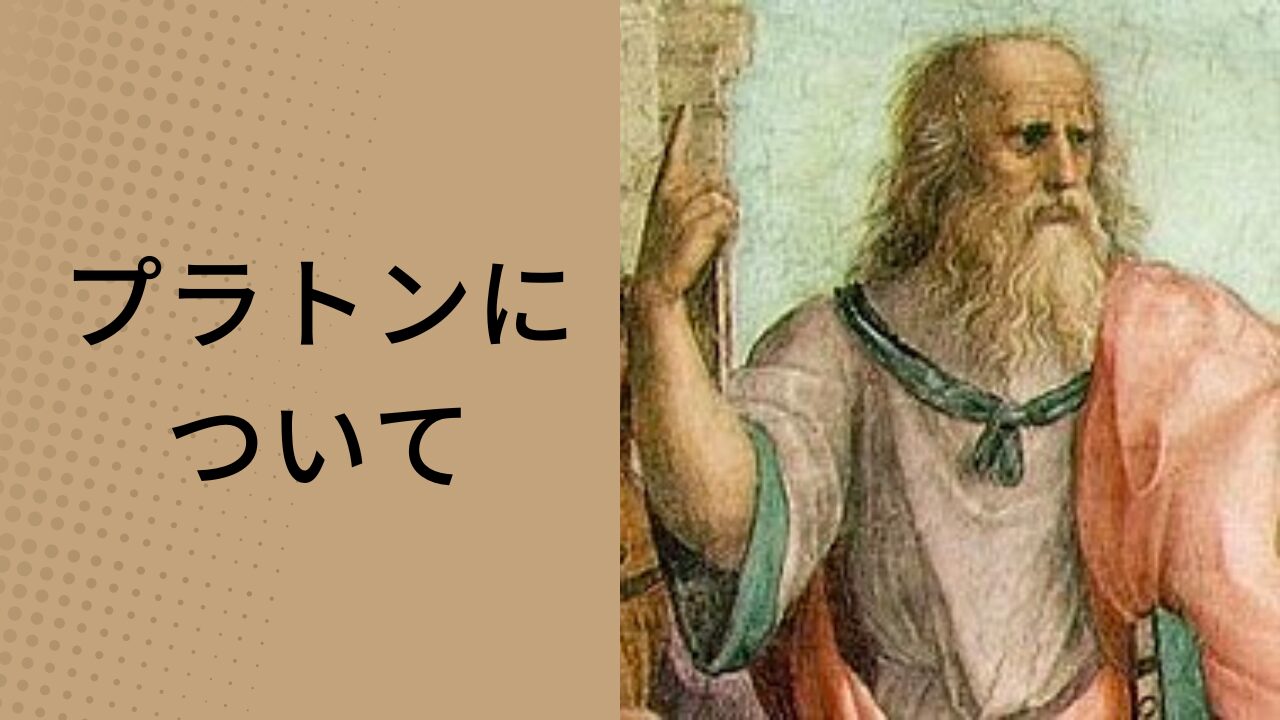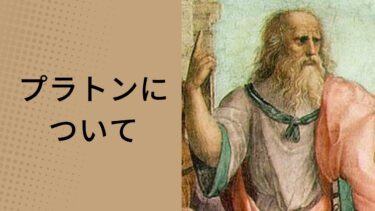今回から、プラトンの思想を初期、中期、後期の順に流れで扱っていく。流れでみていくことによって、プラトンの関心の一貫性と、その関心をもとに思想がどのように展開されていくかがわかるからである。
ということで、今回の記事では、プラトンの初期の思想を扱うことにする。(0-1)
初期プラトンの著作一覧
初期プラトンの著作は、以下の通りとされる。
・『エウテュプロン』 :敬虔について
・『ソクラテスの弁明』 :ソクラテスの裁判の様子
・『クリトン』 :裁判後、獄中で正義についての対話
・『リュシス』 :友愛について
・『カルミデス』 :節制について
・『ラケス』 :勇気について
・『エウテュデモス』 :ソフィストの詭弁について
・『プロタゴラス』 :徳は教えられるか
・『ゴルギアス』 :弁論術とは→善とは何か
・『メノン』 :人は想起(思い出す)によって学習する
等
初期プラトン著作の共通点
初期のプラトンの著作で問われていることは、倫理的な徳目(勇気・節制・敬虔など)を身につけるためにはどうすればよいか、である。なぜ問われているのかというと、徳目を身につけることによって、より善い人間になれると考えていたからである。つまり、プラトンは善い人間になる方法を探していたのである。
そして、プラトンは、この徳目を身につけるためには、その徳目とは何かを知る必要がある、と考えた。なぜなら、何であるかを知らないものをそもそも身につけることはできないからである。
たとえば、勇気とは何か(『ラケス』)を問うたときは、「戦列にとどまること」といった個々の事例ではなく、それらすべての事例に共通する勇気の本質を見出そうとする。確かに「戦列にとどまること」ができても、それは戦争時の限られた局面での勇気に過ぎず、他の場面には適用できない。そのため、そうであればいかなる時も勇気があるといえるような本質を知らなければならない。
プラトン初期の著作においては、このようにいくつかの徳目について、それは何かという問いを議論し、答えが出ないまま終わる。この答えが出ずに、議論が行き詰まることをアポリアという。
だが、プラトンは、アポリアに陥りつつも、後の思想につながる着想を得る。それは、どのような徳目であれ、それが何かを知るためには、善悪についての知が必要であるというものである。
たとえば、勇気とは何かを知るためには、対峙する存在が恐れるべきものなのか、恐れるべきでないものなのかをはっきり区別することが必要である。仮に恐るべきもの相手に対して、臆せずに対峙してしまった場合、それは勇気ではなく向こう見ずや蛮勇と呼ばれるだろう。つまり、勇気には、その対象に立ち向かうことで良い結果が得られるのか否かについての知が必要である。すなわち、その対象が自分にとって善なのか悪なのかの知が必要ということである。
このように、プラトンの初期著作では、人がより善くなるために、徳を身につける必要があるとされ、いくつかの徳目について、その個別の例ではなく、それが何なのかという本質が問われる。そして、それぞれ別の徳目であっても、それらには善悪の知識が共通して必要であることが指摘される。
中期への過渡期
初期の作品では、より善い人間になるために、どうすれば徳目を身につけられるのかが問われているが、初期から中期への過渡期とされる時期に、プラトンは、そもそも善い人間、善い人生、幸福とは何なのかを根本的に問い直している。
この問い直しは、徳目を身につけることがそもそも善い人間になることなのか。幸福をもたらすのかという、それまでの議論の前提に対する問い直し、吟味である。この吟味を通して、プラトンは、倫理的な正しさを求めていくことに人生を注ぐべきかを決断しようとする。
それがなされたのが、初期著作の中でも後の方に書かれたとされる、『ゴルギアス』と『メノン』である。
『ゴルギアス』
この『ゴルギアス』という著作は「プラトンの弁明」とも呼ばれており、作品の表面上ではソクラテスと対話相手の議論が描かれるが、その裏では、倫理的な正しさを生きることへのプラトンの決断が、描かれているとみなされている。(3-1)
『ゴルギアス』での議論の冒頭は、弁論術が有用であるか否かというようなテーマで進む。ここでの弁論術とは、説得内容の真偽は問わずに、とにかく相手を説得する術として扱われている。つまり、弁論術とは、相手を騙してでも自分の都合の良いように動かすための術であるという感が否めない。そのため問題の中心は弁論術から、不正(騙すことなど)を働いて権力を得ることが良いことなのか、つまり、不正は自分らを良くするのか、幸福をもたらすのかという点に移っていく。
カリクレスの思想
『ゴルギアス』では、議論が深まるにつれて、より過激な主張をする相手が現れる構造になっているのだが、最終的に現れたのは、最も過激な主張をするカリクレスという人物である。ちなみに、このカリクレスは、ニーチェに大きな影響を与えたことでも有名である。(3-2)
そのカリクレスの主張とは、世の中で良いとされているそれぞれの徳目は、弱者が強者を制約するための虚構に過ぎず、本来の人間にとっての善さ・正しさとは自分の欲望を無制限に満たし快楽を得るための力である、というものである。彼は当時の流行の思想であった快楽主義的なソフィストが主張していた、ノモス(法律・慣習)とフュシス(自然)を対立させ、自然界の摂理こそが真の摂理であり、法や慣習は虚構に過ぎないという思想を背景としている。
このカリクレスの登場によって、議論の内容は、善い人生とは何か、幸福とは何かという最も根本的なテーマに深まる。カリクレスは、善い幸福な人生とは、力によって自分の欲求を充足していくことだとした。プラトンはこれに対して、以下のように反論する。
プラトンの反論
自分の欲求を無制限に満たすことということが良いということは、常に何かを欲求する必要があることになる。欲求とは、例えば、食欲が空腹によって起きるように、欠乏を充足させようとするものである。そのため、欲求を無制限に満たすということが良いことであり、幸福なのだとしたら、常に欠乏を抱えている必要があることになる。
常に欠乏し、それを充足させたいという欲求をもっていることは、いわば欲求に囚われている状態だろう。欲求とは、自分自身の意志とは関係なしに、自分を駆り立てる。したがって、欲求とは、自分の中の自分でないもの、非自己のような存在だろう。そのような存在に駆り立てられ、それを満たすためだけに生きるということは、果たして良いことであり、幸福なのか。それは、自分自身を失い、欲求という非自己の奴隷になるようなものではないか。プラトンはこのようにカリクレスに反論を行った。
このように、プラトンは欲求を自分自身にとって非本質的な非自己とした上で、この欲求に従って生きることを、正しいこと、幸福なことではないとした。それは同時に、自分にとって本質的なもの、真に自分自身といえるようなもののために生きることを選択するということである。
以上のように、『ゴルギアス』は、プラトンが自らがどう生きるのかという人生の方向を定めるための内面の葛藤を描き、そして、真に自分自身であるようなものを善くするような生を選ぶという決意表明でもあった。
『メノン』
魂の永遠の存在の証明
『ゴルギアス』において、単にその場限りの快楽であり、その充足が真に自己を善くすることのない欲求の充足を退けたプラトンは、真に自分自身と呼べるものを善くする道を選んだ。ということは、現れては消える欲求とは対照的な、真に自分自身と呼べるような何かがあることを証明しなければならない。この自分自身とは、自分の人生を通して一貫して存在し、それ自体が自分であると呼ばれるようなもののことである。プラトンはこれを魂と呼ぶ。そして、その魂の存在について、初期の中では後期とされる『メノン』で扱い始め、本格的には、中期の作品群で論じることになる。
魂とは、その人がその人であるような中核であり、本質である。現代的にいえば、人格やアイデンティティといったものにあたるだろうか。それを磨き、善くしていくことが、直接その人を善くするような存在である。
しかし魂は人格とは異なり、個人を超えた存在だとされる。一般的な宗教において、死後も魂は不滅であるといわれるのと同じように、プラトンも魂を肉体的な生死を超えて、存在するものだとした。そして、『メノン』において、プラトンはそれを想起説と呼ばれる理論を用いて説明する。
想起説
想起説とは、人がこの世で何か新しいことを学習することは、実は魂がすでに得ていた知を思い出すことであるという理論である。プラトンは、これを説明する際のたとえとして、幾何学の学習を挙げる。よりわかりやすく、数学の学習といってもいいかもしれない。数学において、今まではよく分からずに使っていた定理などが、習熟してくると、それを会得したような腑に落ちた感覚があることがあるだろう。この腑に落ちるとき、何か今まで知らなかったような知識をきっかけとしているわけではない。いわば、自然と回路がつながるかのように、しっくりとくるようになる。
この新しいことを何も学んでいないのに、理解ができるということから、プラトンは、魂は肉体がこの世に誕生する前に、すでに天上に存在し、そこで全ての知識を得ている、と主張する。そして、この世に降った魂は、探究を通して、かつて得た知識を思い出しているとする。腑に落ちるやしっくりくるというのは、それを思い出したからである、とされる。
このような理論を用いて、プラトンは魂の存在とその不死性を説明する。こうして、魂という自分自身の人生を貫き、さらにその人生を超える存在を前提とすることができ、この魂を基に真の自己を確立し、それを究極的な善悪・幸不幸の基準とすることができるのである。
まとめ
以上、プラトン初期の思想の流れを見てきた。
当初、プラトンはソクラテスを受け継ぐ形で、徳についての探究を行った。そして、さまざまな徳があるが、それらに共通することは、自らを善くするか悪くするかについての知、すなわち善悪についての知の必要性であった。しかし、自らを善くする前に、そもそも善悪とは何なのか、善い人間、善い人生、幸福とは何なのかという問いに答える必要があった。そうして、『ゴルギアス』において、快楽主義を退け、真に自分といえるような魂があるとし、それを『メノン』や以降の著作で論じていくことになる。
こうしたプラトンの思想は、自らを善くし、幸福にするためにはどうすればいいのかに対する徹底的な反省の末に生まれたものである。この点において、この初期プラトンの思想は、以降のプラトンの骨格となり、さらには後の哲学者に絶えず参照され続けることになり、ここに「哲学とは何か」という問いに対する一つの答えがあるといえるだろう。
一方で、このようなプラトンの思想は、魂が真なる自己であり、それに資するか否かのみが善悪の価値基準となるということを意味しうる。もちろん、プラトンがそれ以外の一切を無価値であると論じたわけではないだろうが、このような主張は、人間やその人生を、究極的なものである魂に還元し、一元的なものにする思想であることは否めないだろう。
注釈
(0-1) プラトンの著作はほぼ全て対話篇であり、主人公として登場するソクラテスが思想の語り手となることが多い。そのため、ソクラテスとプラトンの思想をはっきり区別することは難しい。このことは、『哲学の饗宴』p.72で論じられている。
(3-1)『哲学の歴史 1』pp.454-6
(3-2)同書 p.455 注釈42
参考文献
原典:
『ラケス』
『ゴルギアス』
『メノン』
研究書(二次資料):
荻野弘之 『哲学の饗宴』 NHK出版 2003年
内山勝利他 『哲学の歴史1』 中央公論新社 2008年