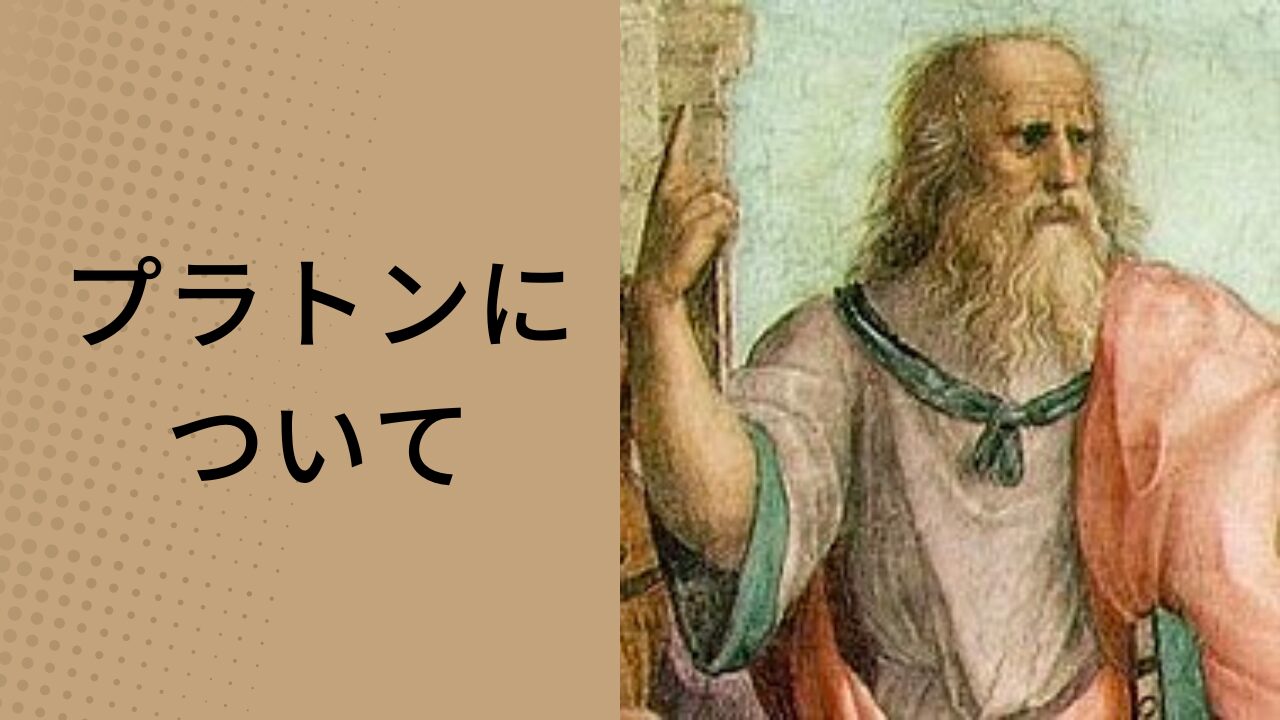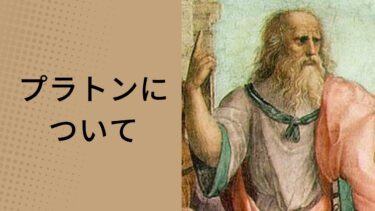プラトンは自身の著作をほとんど全て対話篇という形式で著した。対話篇とは、登場人物の対話によって、作品が進行していく戯曲・演劇形式である。では、プラトンはなぜこのような形式をとったのか。その意味・意義について、三つに分けて考えてみたい。
1つ目は、対話篇に描かれている対話を実際に行うことの意義についてである。その前提として、対話篇に描かれている対話がどのようなものなのかについて概観する。
2つ目は、プラトンにとっての対話篇の意義である。つまり、プラトン自身はなぜ対話篇を書く必要があったのかを考える。
3つ目は、読者にとっての対話篇の意義である。読み手にとって、対話篇であることがどのような意義をもつのかを考える。
前回の記事はこちら↓
プラトンは、哲学史上、おそらく最も重要な哲学者であり、「西洋哲学はプラトンの注釈である」(1-1)とまでいわれる。その著作は25巻を超え(1-2)、分野も多岐にわたる。そして、そのそれぞれが後の哲学の原型となっており、まさしく西洋哲学の基盤[…]
ソクラテスの対話とは何か
ソクラテスの対話と一般的対話の違い
一般的に、対話(あるいは議論)の目的は、対話者同士が納得する結論を出すことである。そのためには、互いが明確な意見をもっており、その正しさを主張しあうことが必要だ。そして、意見を主張し合なかで、両者にとって合意できそうな結論を作り出していく。このプロセスにおいて、両者はあらかじめ自分の意見をもっているため、その考えとかけ離れた主張に合意するとは考えにくい。そのため、合意を目的とする一般的な対話・議論は、折衷的な結論に至りやすいだろう。
その一方で、対話篇に描かれている対話は、この一般的な対話とはかなり異なったものである。異なる点を以下、三点挙げる。
一つ目は、ソクラテスが自らの無知を標榜することである。ソクラテスには、対話の内容についての明確な知識がない。そして、ソクラテスの対話相手は、大抵そのテーマについての専門家であることが多い。「勇気とは何か」をテーマをするときには、勇敢な将軍を相手にし、「敬虔とは何か」のときには、宗教家を相手にするといったようにである。
二つ目は、対話の進行である。ソクラテスは対話のテーマについて全くの無知であるため、自ら意見を主張し合うということはできない。そして、ソクラテスの対話相手は専門家であるため、その専門家が一方的に自らの意見を主張するような進行になる。その結果、対話というよりは、ソクラテスが相手に教えを乞うような形で、対話篇が始まるのである。
三つ目は、対話の結論が出ないことである。
上記のように、対話はソクラテスの質問から始まる。たとえば、勇気とは何か(『ラケス』)についての対話のときには、相手にまず、「勇気とは何であるか」と問う。そして、相手が「戦列に留まること」と答えると、さらに質問を続ける。たとえば、「歩兵部隊の場合は戦列に留まることが重要かもしれないが、騎馬部隊だと機動力が大事ではないか」というように質問をする。すると、相手も確かにそうだと言い、ソクラテスはあらゆる場合における勇敢さとは一体何かと問う。
このような問答を続けていくうちに、専門家であるはずのソクラテスの対話相手は、答えに窮することになる。こうして、ソクラテスの問いに答えられなくなった専門家は、実は自分は最初の問いである、「勇気とは何か」とか「敬虔さとは何か」といったことを知らないのだということを突きつけられることになる。つまり、当初から無知を標榜するソクラテスに、当初は知者を自称していた対話相手が、無知を暴かれて対話が終了するという結末になる。当然、勇気や敬虔さに対する答えも明確に出ることはないのである。
このように、一般的な対話・議論と比較しながら、ソクラテスの対話について述べてきたが、一体このような議論にどんな意義があるのだろうかについて、次の章で考える。
ソクラテス的対話の意義
対話は、当初の目的であった、勇気とは何かに対して答えを出していないが、この対話には一般的な対話とは異なる意義があると考えられる。その意義を以下、二つ挙げる。
一つ目は、前提知識の問い直しである。
ソクラテス的対話は、一般的な対話と異なり、互いの前提知識を元に出発しない。そのため、対話相手は、普段は当たり前だと思っていること、改めて説明するまでもないと思っていることを、言葉にして説明しなければならない。それによって、当然自分が知っていると思っていることを、相手に説明するという機会が得られる。こういった機会は、日常生活ではあまりない。なぜなら、普段はそれらの共通の知識、価値観を前提として対話を行うからである。
しかし、そういった前提知識を知らないということは案外多い。たとえば、こどもの素朴な疑問に答えられない大人は多いだろう。普段の当たり前を改めて問い直す、あるいは知っているつもりになっていることを問い直すというきっかけをソクラテスとの対話は提供しているといえる。
二つ目は、自らの意見の批判的な検証、すなわち吟味である。
ソクラテスは相手の主張に対して徹底的につっこみを入れる。相手が一見それらしい答えを提示しても、その反証がないかを探す。「勇気とはなにか」について、「戦列に留まること」と答えるのは一見それらしいが、その説明は騎馬隊には当てはまらず、勇気の本質を示したものではない。このように、問われていることに対して、正確に答えを出せているのかということを、徹底的に検討することは、問いに対して正しい結論を出す上で不可欠である。それも、自分自身で結論を出すと、対話篇に登場する知者を自認する者たちのように、知った気になっているだけという場合が多いので、他者による検討を経ることが重要なのである。
他者に対して、自分の意見を主張し、他者が抱く疑問や反論に応じる。そういった過程は、自分自身にしか通じない独断的な意見を排除し、誰にでも通じるような客観性をもたらす。これは、相手が厳しく徹底的に自らの主張を反証しようとすればするほど、自らの意見がより客観性をもち、真実に近くなるといえるだろう。そういった意味で、ソクラテスはその対話相手として適任であるし、ソクラテスとの対話はこうした意味を最大限にするといえるだろう。
このように、ソクラテスの行う対話は、一般的な対話と異なる独自の意義をもっており、その意義はこのような対話によってしか得られないものであるだろう。
プラトンにとっての対話篇の意味
以上、ソクラテスが行った対話の意味について考えた。次に、そのソクラテスの対話をプラトンが著した意味を考える。
当初のプラトンの目的としては、他の弟子たちと同じように、師の言動を記録しておくためのものだったかもしれない(2-1)。しかし、その本質的な目的は、ソクラテスが行った対話を著作という形で再現することで、その対話を体験し直すことであったのではないかと思われる。
プラトンはソクラテスが生きていた頃、ソクラテスの対話を、対話相手として、あるいは、同席者として経験した。プラトンはその対話によって、自らの無知を自覚させられるという経験をした(2-2)。それと同時に、この対話自体の有効性に気づいたのだろう。その有効性とは、上記のように、他者の厳しい追求によって自らの思想を吟味し、鍛え上げていくというものだ。
そのため、プラトンは、ソクラテスの対話の再現しながら、ソクラテスの対話をより思想の鍛錬にふさわしいものに磨き上げ、自らの思想を、仮想的にソクラテスに反論してもらっていたといえるだろう。つまり、プラトンは自身の著作の中で、ソクラテスの死後もソクラテスと対話を続けていたといえるかもしれない。
読者にとっての対話篇の意味
最後に、対話篇の読者にとっての意味を考える。
実はプラトンは、直接対話によって交わされた言葉に対して、対話篇のような書かれた言葉は「影」であると捉えていた(3-1)。これはどういうことか。
お互いが直接対面して、話しを行う対話においては、互いに主張を行う過程で、互いの理解を確認し合いながら進めることができる。相手が自分の主張を分からなかったり、誤解していたりすれば、相手が分かるように説明し直すことができる。つまり、直接の対話においては、相互に理解を確認し合うことができる。
これに対して、書かれた言葉の場合、言葉は書き手のもとを離れる。つまり、書き手が直接その場にいない以上、書き手は読者にその意図を説明することができない。すると、読者が書き手の思い通りに主張を理解したかどうかはわからないし、誤解していた場合はそれを正すこともできないということになる。こういった意図で、プラトンは書かれた言葉を「影」としたと思われる。
では、その「影」である書かれた言葉としての対話篇は、読者にとってどのような意味があるのか。その意味は、その対話を読者が追体験することにあるだろう。そのための仕掛けをプラトンはしているのである。
その仕掛けは、ソクラテスの対話相手にある。ソクラテスの対話相手は、上記したように、その分野の専門家である。その専門家は、ソクラテスの問いに対して、自らの意見を述べるが、その意見は極めて一般的であり、受け入れやすいものである。「勇気とは何か」について、「戦列にとどまること」という回答は、当時の社会での一般的な勇敢さの証だったのだろう。つまり、対話相手は、読者にとっても納得しやすいことを言っているのである。そのため、読んでいるうちに、読者はソクラテスの対話相手の立場に立つことになる。このように、対話篇は、読者が対話篇のなかの対話に、仮想的に対話相手として参加してしまうような構造になっているのである。
そのような立場を読者に取らせておいて、ソクラテスは、対話相手に反論を投げかける。読者も一度対話相手の立場に立った以上、その反論に答えようとする。こうして、読者は仮想的に対話相手として参加した上で、ソクラテスの反論に対して自分なりに考え、反論しようと頭を使うことになる。その結果、ソクラテスに反駁されるか否かは読者次第だが、少なくとも自分があたかも対話相手になったかのように対話に参加し、自らそのテーマについて考え、ソクラテスの厳しい反論に晒されるのである。
このように、対話篇を読むということは、あたかもその対話に参加するような体験であり、自分の考えが仮想的にであれ、ソクラテスの対話相手と同じように反論に晒されるという体験である。仮に対話相手と読者の意見が一致しなくとも、そこに書かれている対話はありうべき対話であり、参照すべき先例であり、読者にとっては思考の補助線となるであろう。
プラトン自身、対話篇を、「同じ足跡を辿って探究の道を進むすべての人のため」の「下書き」であると言っている(3-2)。確かに、書かれた言葉は読者に対して、それ以上のことを伝えることはないが、実際になされた対話を仮想的に体験することで、自分の考えをソクラテスによって吟味されるという経験ができるのである。このことを通して、対話相手のように、知った気になっていることを自覚し、真に何かを知るために必要とされるソクラテスの反論のようなプロセスを知ることができるのである。
注釈
(2-1) 弟子によるソクラテスの記録として有名なのは、クセノポンの『ソクラテスの思い出』がある。
(2-2) プラトンの著作にプラトンは登場しないが、『ソクラテスの弁明』には、裁判を傍聴している人物として、プラトンの名が登場する。また、弟子であり、数々の対話篇を著している以上、ソクラテスの対話相手になったことは間違い無いだろう。
(3-1) 『哲学の歴史1』p.445にて、『パイドロス』と『第七書簡』が挙げられている。
(3-2) 『哲学の歴史1』p.448にて引用されている。
参考文献
荻野弘之 『哲学の饗宴』 NHK出版 2003年
内山勝利他 『哲学の歴史1』 中央公論新社 2008年