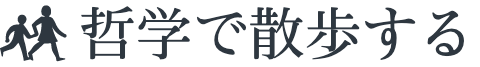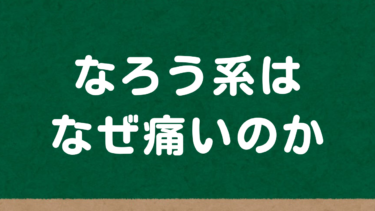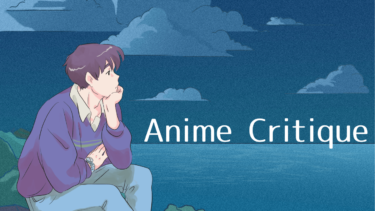『チ。 ―地球の運動について―』のアニメを観た。非常に面白く、また示唆に富んでいる話だと思う。この記事では、第1章にあたる1話から3話までの内容をまとめ、考察する。
以下、ネタバレ注意。
『チ。』第1話考察
合理的なラファウ
ラファウ:
「僕の信条は、合理的に生きるだ。愛とかに代表される無為な感情や、無駄な欲望に惑わされず合理的な選択すれば、この世は快適に過ごせる」
「合理的なものは、常に美しいのだ」
「規則正しく決まって動く星に、一時は合理的な美しさがあると思ったが、蓋を開ければ複雑な軌道計算と、バラバラな星の集まり。
天文を続けるのは、合理的じゃない。それにずっと遠くの世界の話だ。どんなに背伸びしたって人間は近づけない。」
この場面では、ラファウの根本的な考え方が示される。ラファウは、合理的であることを信条にしている。ラファウにとって合理的であることは、「世の中を快適に過ごすこと」と、「美しいこと」である。つまり、自分が社会的にうまくやっていくための行動基準=社会的な合理性と、何かが美しくあるための条件=美的な合理性が、両方とも合理性という同じ概念で捉えられているのである。それまでのラファウの人生において、合理性が、この二つを包摂していても、矛盾することがなかったのだろう。
そんななか、養父であるポトツキに天文をやめるように言われて、ラファウは初めて葛藤する。社会的にうまくやるためには、天文をやめ神学に集中した方がいい。だが、天文への興味を捨てきれない。もし、合理性を第一に考えるならば、天文をやめることを悩むことはないはずだ。なぜなら、社会的には神学のほうが重視されているし、ラファウ自身も天文に合理性と美しさはないと思っているからだ。
しかし、ラファウは悩む。悩むということは、ラファウのなかには、ラファウ自身も気づいていないような、何らかの合理性とは別の信条が存在しているということなのだ。そしてそれがラファウに天文をあきらめさせずにいる。それが何なのかは、まだわからない。
伏線:葛藤するラファウが窓の外の夜空を見る。
フベルトとの出会い
フベルト:
「私は君に利益を与えない。好かれようと作り笑顔をしなくていい」
「不純だな」
「天文をやれ」
フベルトは、ラファウに対し、好かれようとしなくていいと告げる。そして、神学をやることを不純だと言う。
これは、ラファウが今まで生きてきた信条である社会的合理性と真っ向から衝突する。ラファウはこれまで、賢く、愛想が良く、人々に好かれてきたのだろう。だからこそ、ラファウにとって、世の中はチョロかった。
だが、フベルトには、ラファウの合理性が通用しない。フベルトは今までラファウが対峙してきたような相手とは全く違う人物として、ラファウの前に現れるのである。フベルトは、いわば、社会的な合理性の外側の人物なのである。
そして、フベルトはラファウを脅し、天文を続けることを強制する。それによって、ラファウは天文を非自発的=強制的に続けさせられることになる。
こうして、ラファウは非自発的に天文をやらざるを得なくなったようにみえる。だが、フベルトと別れた後、ラファウはフベルトを異端であると通報すれば、天文をやらなくてもすんだ。にもかかわらず、ラファウは通報しなかった。ということは、ラファウは、非自発的に天文を続けることになったが、同時に、天文をやめることには自発的ではなかったということになる。これは、ある意味、天文を研究すること、そして、異端研究に近づくことへの自発的な第一歩である。(自発性1)
この時点で、ラファウは、社会的な合理性を放棄する第一歩を歩んでいる。そもそも天文をやることは、非合理的であった上に、異端者を通報しないという重罪を犯したからである。つまり、ラファウにとっては無意識的かもしれないが、ラファウのなかで、合理性とは別の信条が、合理性よりも優先されたのである。
美しいか否か
フベルト:
「では、この真理は美しいか。この宇宙は美しいか」
ラファウ:
「少し煩雑すぎる。(中略)共通の秩序をもたないバラバラな動きは、合理的には見えない。そういう観点からいえば、あまり美しくはない」
フベルト:
「私は、美しくない宇宙には生きたくない」
「地動説」
「バラバラだった惑星は連鎖して動き、宇宙は一つの秩序に統合される。(中略)美しさと理屈が落ち合う」
ラファウは、フベルトと天体の観測を行うが、そこで禁じられた研究の内容を自ら訊く。つまり、異端研究に興味をもち、自発的にそれに近づこうとしたのである。このことから、ラファウはどんどん天文に、そして異端研究=地動説に自発的になっていっているといえる。ここでは、フベルトを通報しないという消極的な自発性ではなく、自ら明確に異端研究に近づいている。(自発性2)
そうして、フベルトは、地動説を説明し始める。この地動説ならば、天体の運動を、すなわち宇宙そのものを合理的かつ美しく説明できる。これによって、ラファウはそれまで非合理的だと思っていた宇宙が、合理的で、美しい存在であるという可能性を手にいれる。
『チ。』第2話
ラファウの揺れ動き
フベルト:
「命を張る場面でこそ直感を信じる。不正解は無意味を意味しない」
帰り道、自分が動くと他のものが動いているように見えることに気づく。
ラファウ:
「この説を美しいと思ってしまう」
フベルト:
「怖い。だが怖くない人生などその本質を欠く」
ラファウは、地動説に対して、3つの異議を唱える。そして、フベルトは、3つ目の異議である「命をかけるなんて馬鹿げている」という社会的合理性に対して、「命を張る場面でこそ直感を信じる」と反論する。
フベルトは、自分の直感を命に変えても信じている。このことは、ラファウが信条としてきた社会的合理性がもたらす社会的な成功と快適な暮らしと正反対である。フベルトは、これら全てを捨て、異端として焼かれようとも直感を信じるというのだ。
こうして、ラファウは、合理性を捨て、直感に命をかけるという姿勢を目の当たりにする。その上で、フベルトは観測を終了し、ラファウは自由になる。
自由になった以上、ここから先、ラファウが天文を続けた場合、フベルトから脅されていたという言い訳が効かなくなる。つまり、異端研究を続けるならば、自分に対しても、世の中に対しても、自発的にやるしかないのである。そういう決断を迫られる。(自発性3)
地動説の継承・ラファウの転換
フベルト:
「あなたの理屈は、私の直感よりずっと強い」
ラファウ:
「地動説は、危険で、不適切で、不確か」
「燃やす理屈より、僕の直感は地動説を信じたい」
「本当の僕は、(中略)横柄で、傲慢で、軽率で、無力で、そして今から地球を動かす」
ここで、ラファウにとって合理性よりも優先される信条が明らかになる。それが、直感である。ラファウは、当初、天文をやることは合理的でないと考えていた。合理性には、社会的な利益と美しさが含まれていたが、そのどちらにも、天文は反していた。しかし、それにもかかわらず、ラファウは天文を捨てきれなかった。それは、直感が天文をやるべきだとラファウを突き動かしたからである。
この場面においても、ラファウの直感は天文をやめさせず、この場面においても、「危険で、不適切で、不確か」であるにもかかわらず、地動説を信じさせる。つまり、ラファウが認めている通り、ラファウは全くもって社会的に合理的ではない。本当のラファウはその正反対のような性格なのである。
こうして、ラファウの社会的合理性が直感よりも下に位置することになる。同時に、ラファウのなかでの二つの意味をもっていた合理性が分離することになる。これまでは、合理性が「社会的な利益」と「美しさ」の両方を含んでいても、それらが相反することはなかった。だが、今では、美しい地動説の研究は社会的に非合理的になった。
合理性が対立した結果、ラファウは合理的な美しさの方を自ら選ぶのである。火を消して、自ら地動説の研究を始めることは、対外的に何の言い訳もできない。フベルトの脅しとは全く関係なく、自らの意志で、地動説の研究を始めるのである。つまり、もしそれがバレたら、異端として捕まることになるということである。(自発性4)
ラファウとノヴァクら既存の社会
ノヴァク:
「この世の平穏を乱すような研究を見過ごせない」
「家族・友人の日々の信仰や生活を守るためならなんだってする」
ラファウ:
「言葉ではなんとでも言える。嘘ほど便利なものはない。培ってきた合理的判断力により、トラブルは回避する」
ここでのノヴァクは既存の社会の代表者として描かれる。既存の社会には秩序がある。それを壊すことは、社会の平穏を乱すことである。ラファウたちのやっている研究は、既存の社会を壊す意味で、ある意味暴力ともいえるのだ。ノヴァクは、暴力から身を守るために暴力を振るっているともいえる。
ラファウは、ポトツキに対して天文をすることを撤回する宣言をする。しかし、内心ではそう思っていない。嘘の撤回宣言をすれば、大学に行ける。大学に行ってしまえば、そこで天文もできるはずである。
これは、社会的に合理的な選択だろう。内心では自分の利益を計算しつつ、表向きは世の中に合わせている。多くの人は自分だったらこうすると考えるはずだ。この選択を一般的には合理的だというのだろう。
ラファウの合理性も、地動説への関心を偽り、社会的にうまくやっていく。「言葉ではなんとでも言える」のだ。ラファウは自らの本心に対しては社会的合理性を捨てたものの、対外的には天文を続けるために、社会的な合理性をもち続ける。つまり、ラファウは二面性をもつようになったといえる。
『チ。』第3話考察
言葉の重み
ラファウ:
「なんでみんなそうも言葉を重んじるんだか」
ポトツキ「地動説は証明できると思うか」
ラファウ「はい」
ラファウは、毒物であるケシの実を取り出して眺める。
ラファウは、ノヴァクに地動説を研究していないと誓う。言葉では何とでも言えるからだ。だが、ラファウは、みんなが言葉を重んじることを疑問に思う。というよりも、不満を抱いているようである。それは、「なんでみんなそうも言葉を重んじるんだか」という言い様に表れている。
おそらく、ラファウはここで、何度も本心でないことを言わされることに嫌気がさしている。そして、地動説への興味を押し殺し、興味がないフリをすることに抵抗を感じている。それは、ラファウのなかで、たとえ表面上であっても、地動説への興味を否定し続けることが、自分の直感を否定するようで嫌だったのではないか、と思う。嘘をつくことで、自分の心を偽るように感じられたのではないか。だからこそ、地動説を研究していた父であるポトツキに、地動説を証明できると思うと明言した。(自発性5)
こうして、ラファウは、社会的な合理性を捨てて、本心を口にした。つまり、ラファウにとって言葉の重みが変わったのである。
そして、最悪のことを考えて、ラファウは、ケシの実を用意している。まだ決心はしていないが、死の可能性を考えているのだ。
ラファウの最後の悩みと決断
ラファウは異端として引き渡される。
ノヴァク:
「この世で最も肝心な選択とは、何を諦めるかだ」
「正解を選べるはずだ」
ラファウは、宣言して資料を燃やすことを考える。まだ人生は詰んでいない。
だが、なぜ、今こうなのか。地動説に出会わなければ、周囲にもてはやされ、将来を嘱望され、快適な生活を送ることができた。世界はチョロいはずだった、と思う。地動説に出会いさえしなければと。
そのとき、独房の小窓から、月明かりを見る。この社会において、非合理的で意味のないはずの地動説。遠い空のはず。
ラファウ:
「あの頃(第一話伏線)よりもはっきりと、空がよく見える」
「こんなに美しかったのか」
「宣言します。僕は地動説を信じています」
独房でラファウは、最後の逡巡をする。これが、もとの世界に戻れる最後のチャンスだ。かつてのラファウは皆が期待する神童だった。だが、ラファウは今まで、社会的に合理的であること、社会的にまともである道を段階的に外れてきた。これが正真正銘最後の決断になる。社会的な合理性をとるか、美しさをとるか。
そして、独房の狭い窓から夜空を見上げる。すると、あの頃、すなわち地動説を知る前よりも、空よく美しく見える。天体は何も変わってはいない。だが、ラファウが変わることによって、ラファウの知性が、今までよりも空を美しく見せたのである。
これは、地動説と類比関係にある。地動説では、地球が回ることによって、天体が運動しているように見える。ラファウは、自らが変わることによって、まるで天体が変わったかのように見えるのである。つまり、ラファウが地球を動かし、天体の秩序を変えたからこそ、その美しさを味わえたのである。
こうして、ラファウは、地動説を信じていると宣言する。(自発性6)
知性と狂気
ノヴァクとの対話。
ラファウ:
「敵は手強いですよ。あなた方が相手にしているのは、(中略)ある種の想像力であり好奇心であり、畢竟それは知性だ。」(畢竟=究極的には)
「それは流行病のように増殖する。宿主さえ制御不能だ」
ノヴァク:
「この選択は君の未来にとって正解だと思うのか」
ラファウ:
「そりゃ不正解でしょ。でも不正解は無意味を意味しません」
ラファウがケシの実を飲む。狼狽えるノヴァク。
ラファウ:
「死の先なんか誰も知りませんよ」
ノヴァク:
「そんな言葉が何になる」
ラファウ:
「感動できる」
「多分、感動は寿命の長さより大事なものだと思う」
「命に変えてでもこの感動を生き残らせる」
ノヴァク:
「狂気だとは思わないのか」
ラファウ:
「たしかに。でもそんなの愛ともいえそうです」
そして、ラファウは死ぬ。その後、火炙りになった。
知性的な人物というと、自分をコントロールし、社会的に巧妙に振る舞い、成功するような人物を思い浮かべるかもしれない。だが、ここで言われている知性は、そのようなものではない。ここでの知性とは、人を狂気に陥れ、増殖する。それを宿主、その人間はコントロールできない。つまり、知性は、社会的な合理性、すなわち自己利益の勘定を超えるのである。
ノヴァクが問い、ラファウが答えたように、知性の導いた結論は、君の未来にとっては正解ではないのだ。つまり、知性はその持ち主の正解=社会的な成功をもたらさない。それどころか、その持ち主を破滅させる。
しかし、その人物にとっての不正解は、無意味じゃない。知性は宿主を乗り潰して、その成果を次に伝えていく。この増殖が科学の発展の歴史である。そして、宿主には感動が残る。この感動は、宿主以外の誰にもわからない。だから他人から見れば、狂気にしかみえない。
知性がもたらす感動に、自分の全てを賭けることは、通常の価値観からすれば、狂気である。普通の人は、あらゆる物事を自己利益に照らして判断する。今の自分にとって、あるいはこの先の人生にとって、何が良いのかを、選択肢を比較しながら選んでいく。そこでは、全ての選択肢を自分の利益に従属させる。自分の利益を通して、その視点で選択肢を考える。
それは当たり前のことだが、人間関係で考えれば、誰と付き合うのかを自分の利益のみで考えることは、不純なように思えるだろう。純粋な愛とは、自己利益とは関係なく、その人のことを愛することであろう。
それと同じように、ラファウは、地動説に全てを賭けた。自分を犠牲にし、他のもの全てを犠牲にし、それに100%を賭けた。そんなラファウのあり方は、確かに愛と言えるかもしれない。
なぜラファウは大学に行かなかったか
視聴者は、ラファウが嘘を突き通して、大学で天体をやった方が後の科学にとって有益だったのにと思ったかもしれない。
だが、知性や好奇心とは、そういうものではない。そういった後先を考えられるような合理性を超えて、人を突き動かすようなものでなければ、そもそもラファウはフベルトを引き渡し、地動説に出会うこともなかっただろうし、人類は、ここまで科学を発展させることはできなかっただろう、と思う。
自発性の段階の構造
ラファウの天文・地動説に対する自発性は、段階的に増していく。そして、それが増すのに比例して、ラファウの対外的・社会的立場は危うくなっていく。その移り変わりを段階ごとにまとめる。
自発性の第一段階(自発性1)では、フベルトによって天文を強制される。元々天文への興味があったとはいえ、この段階では、まだ主体性はほとんどなく、やらされている状態だろう。この段階であれば、対外的にも、脅されて協力していたのだと言えば、罰を受けることはないだろう。ただし、ラファウには、フベルトを通報する機会はあった。それをしなかったという消極的な主体性はあったといえるだろう。
自発性の第二段階(自発性2)では、ラファウは自ら異端研究について訊く。このとき、ラファウはついに異端研究への興味を抑えきれなくなっている。異端研究について、その内容を自ら進んで訊くこと自体が、異端とみなされてもおかしくないはずなのにである。つまり、この時点でのラファウは、消極的な主体性から、積極性へ移行し始めている。だが、この時点でもまだ、異端の内容を訊いたことを伏せさえすれば、対外的に言い訳できる状況にある。
自発性の第三段階(自発性3)では、フベルトに自由を突きつけられる。ここまでは、異端研究をやらされていたと言えば対外的には何とかなるが、ここからは自分の意志で、完全に主体的に研究をすることになる。その分岐点である。
自発性の第四段階(自発性4)では、火を消すことで、主体的に、積極的に異端研究=地動説の研究を続けることを決意する。こうなれば、言い訳のしようがない。ラファウの社会的立場は一気に危うくなり始める。だから、ラファウはバレないようにするのである。
自発性の第五段階(自発性5)では、自分のなかでは主体的に地動説の研究を行っているが、対外的にはそれを隠している状態だったが、何度も地動説を否定する誓いをすることができなくなり、ついにポトツキに対して、打ち明ける。こうして、対外的にごまかすことをやめ始める。社会的立場は危機に瀕している。
自発性の第六段階(自発性6)では、全ての人に対して、公開の場で、地動説を信じていることを宣言する。それによって、ラファウのなかでの信念と対外的な姿勢が一致する。完全に社会的立場を無視して、自分の信念のみを通し、人生を終えることになる。
まとめ
『チ。』の第1章を振り返った。たった3話の中に、これだけのテーマ性を詰め込んで、かつストーリーとしても非常に面白いのは、驚嘆せざるを得ない。この記事では、まとめきれなかったことや、今後の展開についても、書いていきたいと思う。