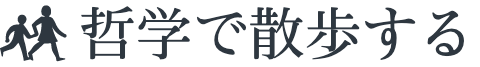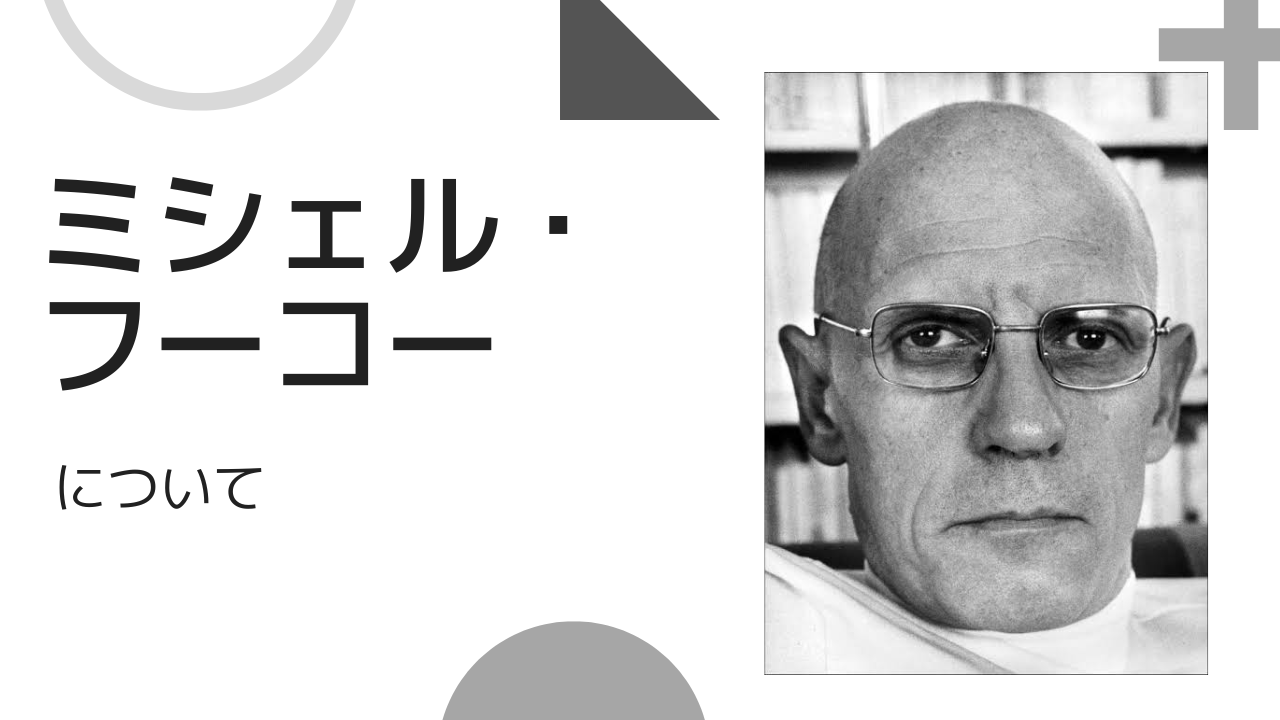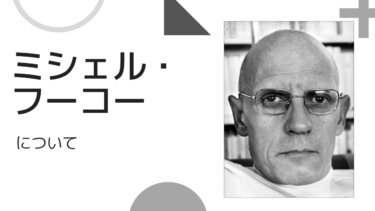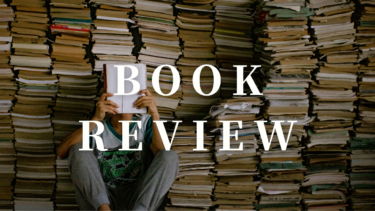この記事では、ミシェル・フーコー(1926-1984)についての基本的な情報、著作、経歴、人物像、活動、思想の概要について触れる。
フーコーとは
ミシェル・フーコーは、フランスの哲学者である。だが、フーコーは哲学者であると同時に、研究分野は多岐に渡り、心理学者、歴史学者、社会学者、文学批評家でもあるといえる。
フーコーは思想史の流れで言えば、ポスト構造主義の代表的な思想家とされる。
代表的な著作は、
・『狂気の歴史』(1961)
『言葉と物』(1966)
『知の考古学』(1969)
『監獄の誕生』(1975)
『性の歴史 第一巻』(1976)
『性の歴史 第二巻・第三巻』(1984)
フーコーの死後、『性の歴史 第四巻』が出版された。
フーコーの経歴
フーコーは、1926年にフランスのポワチエで生まれた。19歳のときに第二次世界大戦が終結した。22歳で哲学の学士を取得し、その1年後の23歳のときに心理学の学士を取得する。その後、フーコーはしばらく心理学者としてのキャリアを歩む。その間に心理学の著作としては、『精神疾患とパーソナリティ』と『夢と実存』(ビンスワンガー著)の翻訳の協力と序論の執筆(フーコーが訳書の序論を書いた)がある。
この青年期に、フーコーは精神的な問題を抱えており、何度も自殺未遂を行う。これは、フーコーが同性愛者であり、当時のフランス社会が同性愛をタブー視していたことによる精神的抑圧が原因であると分析されている。(2-1)
1961年に『狂気の歴史』で博士号を取得した。その後も、心理学や歴史学、文学的な著作を発表するが、一般的には哲学者であると考えられるようになる。その理由は、「哲学の伝統的な批判的プロジェクトを新しい(歴史的な)方法で行うことと、伝統的な哲学者の思想との批判的な関与」(2-2)である。
フランス国内外の多数のアカデミックな役職を経験した後、1970年にコレージュ・ド・フランスの教授に就任する。
1971年に、GIP(監獄情報グループ)を創設するなど、社会的・政治的運動を活動的に行う。
1984年、58歳でエイズで亡くなる。
フーコーの思想的背景
フーコーは、1946年にパリ高等師範学校に入学し、メルロ=ポンティの講義に大きな影響を受けた。また、ヘーゲル、マルクス、ハイデガーへも強い関心を寄せており、上記したフーコーの心理学者時代の著作は、実存主義とマルクス主義の影響を強く受けていた。
『夢と実存』序論においては、覚醒した意識によって夢を解釈する精神分析を批判し、夢それ自体からその真の意味を抽出する方法が必要だとされる。この夢の分析においては、夢を世界の形式をもちつつ、最も自らに固有である「私的世界」と捉え、この夢を分析することで、必然的な世界に投げ込まれつつ、主体的に自らを世界に投げ込むという「世界内存在」としての自己を分析できる、とする。ここには、ハイデガーの影響が強く見られる。(3-1)
また、『精神疾患とパーソナリティ』においては、精神疾患の原因が、社会構造にあるとされ、社会が人間から人間的なものを疎外することによって病が発生するとしている。ここには、マルクス主義の影響が見られる。(3-2)
また、フーコへのサルトルの影響も無視できないだろう。フーコーの思想的特徴として、ブルジョワへの反感と疎外された人々への共感があるが、こうした特徴はサルトルにも見られるし、後年のフーコーの積極的な政治参加もサルトルに共通する。しかし、フーコーは思想的にも個人的信条においてもサルトルを否定している。(3-3)
他にも、博士論文やその後の研究のサポートをしたカンギレムは、フーコーの科学史の見方に影響を与えた。文学においては、ジョルジュ・バタイユやモーリス・ブランショといったフランス前衛文学が影響を与えている。(3-4)
フーコーの思想的特徴
フーコーの思想においてキーワードになるのは、「好奇心」だろう。フーコーは、好奇心について、「自分自身から離脱することを可能にしてくれる」と論じる。哲学についても同じように、「別のやり方で思考することがどのようにして、そしてどこまで可能であるかを知ろうと企てること」が任務である、とする。(4-1)このように、フーコーは、同一であることから脱すること、特に、同じであり続けるような自己から離脱することを執拗にもとめているといえる。
通常、自分という存在は、時間的に同一の存在であり続け、周囲の存在とも同一の関係を保ち続ける。緩やかな変化は時間の経過とともにあるだろうが、基本的には固定的な同一性が保たれる。その同一性があるから、人は安定することができる。
しかし、フーコーはこれを拒絶する。自分自身であるということから逃れようとする。こうした、自分自身から離脱し、常に新しい別の自分であろうとする営みが、フーコーの思索全体を貫いている。彼の著書である『狂気の歴史』や『監獄の誕生』において、監禁施設の分析がなされるが、おそらくは、フーコーにとって、監禁施設のイメージは、自己の同一性に監禁されているという感覚と重なっていたのではないかと私は思う。
そして、その方法として、今までの自分を規定してきた数々の前提・常識・慣習をその起源まで遡って問い直し、その自明性を検討に付すという「考古学」、「系譜学」的手法が、彼の著作において用いられるのである。
まとめ
以上で、フーコーの基本的な前提情報を整理した。次回から、フーコーの思想について詳述していく。
注釈
(2-1)Wikipedia 注26
(2-2)SEP 1.Biographical Sketch(以下、題は省略)
(3-1)『ミシェル・フーコー —自己から脱け出すための哲学』(以下『フーコー』) (pp.12-5)
(3-2)同書(pp.16-7)
(3-3)・(3-4) SEP 2.
(4-1)『フーコー』(p.4-5)
参考文献
慎改康之著 『ミシェル・フーコー —自己から脱け出すための哲学』 岩波新書 2019年
千葉雅也著 『現代思想入門』 講談社現代新書 2022年
鷲田清一(他)編 『哲学の歴史 12巻』 中央公論新社 2008年