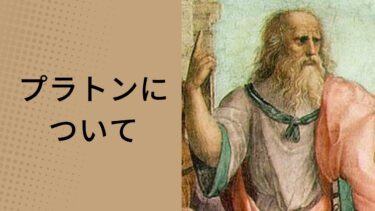この記事では、実存主義の創始者と呼ばれることの多いキルケゴールについて紹介する。
この記事で扱うのは以下の三点である。
まず、キルケゴールの人物像、特に彼にとって重要な出来事であった「父親の呪い」と「婚約破棄」について紹介する。
次に、キルケゴールの思想の中心点について扱う。それを一言で言うならば、真の幸福を求めるか、仮初の幸福に満足するかどちらかしかない、というものである。
最後に、キルケゴールにとっての実存について触れる。
キルケゴール(1813-1855)の人物像
キルケゴールの出自
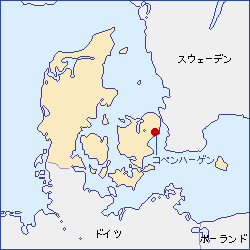
引用:https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/denmark/index.html
キルケゴールの本名は、セーレン・オービエ・キルケゴールであり、ローマ字では、Søren Aabye Kierkegaardと綴る。
キルケゴールは、1813年にデンマークのコペンハーゲンに生まれた。当時のデンマークは、対外的にも、経済的にも苦境にあった。
キルケゴールの父親は毛織物商で財を成した人物で、母親はその使用人であった。
キルケゴールは、自身の母親についての記述をほとんどしていない。ゆえに、キルケゴールにとっての母親の存在がどのようなものだったのかについては、不明確である(1)。
一方のキルケゴールの父親に関する記述は多くあり、影響もまた多大であった。キルケゴールのキリスト教へ強い信仰は、父親による厳格極まりない信仰教育の影響が大きかった(2)。
神に罰せられた父親
その父親は、幼い頃に神を呪ったことがあった。またキルケゴールの母と婚前交渉をし、子を成した。このことから、自分は神に呪われており、罰を受けると思っていた。その罰とは、彼の子供は皆、34歳(イエスの没年)になるまで生きられないというものであった。
実際、キルケゴールは7人の兄弟がいたが、そのうち5人が若くして亡くなった。この呪いと罰のことを聞かされていたキルケゴールは、自分が34歳になったことに驚いたという。それほどまでに、キルケゴールは父親の罰を真剣に信じており、彼が34歳までに多くの作品を著しているのもそういう理由であった。また、この「罰」は彼の思想へ大きな影響を与えている(3)。
婚約破棄
キルケゴールは二十代の時に、彼の婚約者であったレギーネとの婚約を破棄する。その理由は明かされていないが、彼がこれ以降、現実生活での女性との関係を断ち、修道士的な生活を送ることから、世俗から離れ宗教的な生き方を選んだのだと推測される。
その一方でこの後、現実生活で断たれた女性との関係を、詩によって表現することになる。詩において、自らの婚約破棄を暗示する作品を作ったり、青年が女性によって詩的になるテーマが繰り返されることになる(4)。ここにキルケゴールの未練ともいえるような分裂が垣間見られるだろう。
キルケゴールの人物像まとめ
このように、キルケゴールは、一方でキリスト教徒としての厳しい教育を受け、自らも厳格なキリスト教徒であらざるを得なかった。さらには、父親から受け継いだ憂鬱な性格、罪の意識や不安を抱えていた。このような生まれながらの性格と教育によって抑圧されつつも、異性への感情や美的な感性は消え去ることはなく、あたかも人格が分裂したかのように、彼はいくつもの偽名を用いて哲学的著作や詩を発表した。
以上より、キリスト教徒としての理想像と、感覚的な快楽や美を求める欲求の間の葛藤や自己矛盾を抱えるキルケゴールの人物像が立ち現れてくる(5)。
そして、キルケゴールは自身のこの境遇から哲学を作り上げる。
キルケゴールの思想
キルケゴールの思想の根幹は、真の幸福、すなわち至福とは何なのかであり、そのために必要なのがキリスト教批判であった。
キリスト教批判
キルケゴールの生まれた19世紀初頭は、啓蒙主義の全盛期であった。啓蒙主義の申し子であるイマヌエル・カントが亡くなってから10年ほどしか経っておらず、カントの影響を受けたヘーゲルが、その啓蒙主義的時代を推し進めていた。
啓蒙主義とは、人間は理性的であり、理性の力を発揮していけば、自然についてより理解しコントロールできるようになるという考えである。また、社会についても、人々が理性的に考えることによって、古くて不合理な慣習は撲滅していけるし、その結果、より平等で自由な個人が可能になるとする。要するに、楽観主義で人間の力や可能性を信じる進歩主義であるといえる。
このような啓蒙主義的な価値観と反発し合うのが、従来の価値観であるキリスト教である。キリスト教の教えの核心は、人は生まれながらに原罪を持っているというものである。この原罪ゆえに、人は神の恩寵を受けることでしか、救済され天国に行くことができない。この教えは、神中心かつ、人間の弱さを突きつけるものである。この価値観が、進歩主義と対立することは当然だろう。
このような時代と相容れない思想と化した教会は、時代に歩み寄る。つまり、人間がより進歩していき、この世での幸福を実現しつつ、同時に教会の教えも守りましょうと言う。悪く言えば、俗世に迎合したのである。そんな教会をキルケゴールは徹底的に批判し続ける。
『あれかこれか』
キルケゴールの目的は、世俗の幸福も天上の幸福も得ようとする折衷的な世界において、真のキリスト教徒であることだった。真のキリスト教徒とは、イエスの生き方に学ぶことである。つまり、迫害され、十字架に磔られてもなお、神を信仰し、それを述べ伝える生き方である。イエスのように生きるには、貧しくあらねばならない。なぜならば、この世の富に執着するものは、神を忘れ、自己を過信し、傲慢になるからである。端的に言えば、この世の幸福は、死後の神の国のために、捨てなければならないのである。
この極端ともいえる信仰が真の信仰であり、ほどほどにこの世の幸福を楽しみつつ、信仰を守るということはあり得ない、とキルケゴールは言うのである。この世の幸福を選ぶか、それとも天上の幸福を選ぶか、あれかこれか、その二者択一を迫るのだ。そして自身も、婚約者であったレギーネとの婚約を破棄し、この世の幸福を捨て、信仰に生きることを選択した。その頃に書き始めたのが、『あれかこれか』という著書であった。
しかし現実として、そんなことを言っていたら、誰ひとりキリスト教徒ではなくなってしまうではないか、と思われるかもしれない。この世の幸福を全て捨てて、迫害と嘲笑の中、天上の幸福を目指すことなど人間にはできないのではないか。これに対してキルケゴールは、こう言う。
私が意図したのは、キリスト教徒となることを困難にすることだ
全集9巻 p.124
その結果、誰一人キリスト教とがいなくなったとしても、それでかまわないとキルケゴールは考えるのである。信者がいなければ存続できない教会と、キルケゴールが対立するのは当然だろう。
キルケゴールの思想まとめ
このように、キルケゴールは、世俗的な幸福と宗教的な幸福の二者択一を迫った。そして、宗教的な幸福、天上での幸福を得ようとするならば、世俗の幸福は全て捨てなければならないとする。それゆえに、どっちつかずであった教会を批判したのである。
どちらを選ぶのかは、個人の選択の問題であろうが、キルケゴールが宗教的生き方を選んだのには理由がある。それが実存の問題である。
実存とは何か
自己認識の難しさ
実存とは、生き方といったようなことを意味する。あるいは、生きる姿勢、構えといってもいいかもしれない(6)。生き方、生きる姿勢は自らが選択して、決断するものである。どのように実存するのかが、キルケゴールにとって最も重要な問題であった。
人は日々、理想と現実の間を生きている。自分が今現実として何者であるのかをしっかりと認識し、そこから自分はどのようになりたいのかを認識し、行動する必要がある。
この自分自身が何者であるのかを正確に認識し、それに基づいて生きることは、想像以上に難しい。多くの人は、自分をより良く評価したいし、実現してもいないことを実現したかのように考えるし(取らぬ狸の皮算用)、自分ではないものを自分であるとすり替えてしまう。たとえば、日本人の活躍を自分の活躍かのように捉えることもそうだろう。
キルケゴールも実存、生き方を考える上で、自己認識を間違えるなと主張する。まさに、ソクラテスの回で扱った自己認識の問題が、キルケゴールの時代にも、現代にも同じように通用するのである(7)。
自己欺瞞から単独者へ
人は自己認識を誤りやすい。キルケゴールがその槍玉として挙げたのが、ヘーゲルである。ヘーゲルの思想を簡単にいえば、人は理性の力によって、神の精神と同一になり、世界の全てを知ることができるというものである。キルケゴールからすれば、まさにこれは、自己認識の極端な誤りであろう。
キルケゴールは、ヘーゲルが絶対精神とかいう大層なことを言っているが、それを言っている本人はまるで犬小屋に住んでいるみたいではないか、と批判する(8)。
人間は世界についての知識を持つことで、まるで自分自身が世界を支配したかのように錯覚する。現実の自分を忘れ去り、可能性の世界へ飛び立ってしまう。これをキルケゴールは『死に至る病』において、自己の客観化・抽象化という。自己認識に対する自己欺瞞である。
自分の現状をよく見てみろ、とキルケゴールは言う。あなたは、時間的にも空間的にも、今ここにしか存在しないではないか。つまり、あなたは、ただ一人の個人でしかないではないか、と。キルケゴールは、この本来の自己を、単独者と呼んだ。
世俗的幸福の否定
自己欺瞞を否定し、抽象的な知識への逃避を禁じたキルケゴールは、同様に、美的なもの、倫理的なものへの逃避も禁じる。
美的なもの、つまりはaesthetic(=感性的)なものに生きることを、美的実存とキルケゴールはし、これを退ける。美的なものは、その美しさによって感性的な快楽を与える。これは確かに幸福と呼べるものだろう。しかし、それは一時的なものに過ぎない。つまり、現実逃避に過ぎない。その快楽が過ぎ去れば、もとの自分自身に連れ戻されるのである。
同様に、倫理的に生きることも退ける。ここでの倫理的とは、カントのいう普遍的な格率に従うことである。格率とは、行動の指針のようなものであり、これが普遍的であるとは、あらゆる時と場合に対して正しいような格率に従って行為せよというものである。これは、自分の行動が他人の存在によって決定されるということであり、自分の固有性・主観性を喪失し、抽象的・客観的になっていると批判する。
こうして、キルケゴールは、徹底的に、自分ではないもの、自分を自分から遠ざけ、抽象的・客観的にしてしまうもの、すなわち美的実存や倫理的実存によって得られる幸福を否定した。その理由は、これらの実存は本質的には自分を自分ではないものであると勘違いした状態での幸福に過ぎないからである。美的な快楽も終わってみれば、自分が取り残されているだけだし、倫理的な幸福も、社会的評価という自分ではないものを自分であると思い違えているということである。
至福へ
自分ではないものを自分であると思い違えること。そして、本来の自分を忘却させるものを幸福であるとみなすこと。これに対して、キルケゴールは、実存忘却だと批判をし、実存すべしと主張する。これは、本来の自分をよく思い返してみろということである。どんなに偽りで仮初の幸福に浸ってところで、あなたは孤独で、無力で、死すべき存在で、罪深いのだ。ここでも、キルケゴールはソクラテスの問答法をなぞっているのである。
ではそのように生きるべきか。どうすれば、幸福になれるのか。キルケゴールは、宗教的実存を選択する。
人は自らを可能性として、どこまでも拡大することができる。それこそヘーゲルが唱えたように、絶対精神として神の精神との合一すら可能であるとされるほどだ。しかし、それは自分の本来の姿を見失うことになる。そして、その偽りの姿によって得た幸福は、自らを真に至福へと導き、自らを救うことはない。
宗教的実存とは、有限で罪のある人間としての自覚を持ち、神の前に一人生きることである。この実存方法は、前述したように、この世での幸福を放棄するものである。しかしその代わりに、神による救済によって、永遠の幸福が約束される。キルケゴールはこれを至福という。
まとめ
キルケゴールにとって重要なことは、キリスト教徒であるとはどういうことなのかを問うことと、真の幸福である至福を手に入れることだった。そして前者は後者を可能にするものである。
キリスト教徒であるとは、イエスの生き方に倣い、迫害されながらも信仰を貫くことである。そしてそれは、時代の思想である啓蒙思想に逆らって、自らの真の姿である無力さをそのまま生きるということでもあった。
このように、キルケゴールは、最も原理的な信仰・実存・幸福を求めたといえるだろう。そしてそれは、一切の不純物が混じることを禁じた。それは、彼が父親から受けた教育同様に、非人間的といえるのではないか。そしてその完全な純粋さを求めるというのは、極めて理想主義的であるといえるのではないか。またそれは、地上の幸福の魅力を知っているからこそ、極端な拒絶反応を示しているのではないか。ソクラテスが酒を飲み、ご馳走を平らげ、若者に恋をしても、自らを失わなかったように(ソクラテスの基本情報を参照)、両者の間には二者択一以外の選択があるのではないか。そんなことをとりあえずは考えたが、皆さんはどう考えるだろうか。
いずれにせよ、キルケゴールの実存の概念は、20世紀に入ってからさまざまに援用され、以後実存主義として流行する。そこにこめられている本質は、キルケゴールのいう、人間の本来の姿で実存すべしというものである。ともすれば、美的なものや世間などの外的なものに埋没しがちな人間への警鐘として、それは、現在に至るまで響き続けている。
注釈
(1)Stanford Encyclopedia of Philosophy Søren Kierkegaard (以後StSKと略す。chapterと段落を1.1のように記す。)の1.6には、直接言及されない母親の影響として、キルケゴールの母国語であるデンマーク語への愛が述べられている。
『哲学の歴史9』においては、「母親はほとんど存在すらしなかったかのようだ」(p.247)と述べられている。
(2) 『哲学の歴史9』p.226において、自然な欲求に対立するという意味で「非人間的」と形容される。
(3)StSK 1.7
(4)同上1.8
(5)『哲学の歴史9』p.227の注釈において、キルケゴールにとって滑稽さもまた重要概念であり、必ずしもまじめくさった人物であったわけではないとしている。
(6)『哲学の歴史9』p.237
(7)キルケゴールの博士論文は、ソクラテスのアイロニーを論じている。StSK 2.2『哲学の歴史9』p.230を参考。
(8)『哲学の歴史9』p.243-4 あるいは全集11巻p.64 『死に至る病』より
参考文献
白水社 キルケゴール全集
特に扱ったもの
- 『アイロニーの概念ーーたえずソクラテスをふり返りつつ』(1841)20-21巻
- 『あれかこれか』(1843)1-4巻
- 『死に至る病』(1849) 11巻
あるいは、講談社で文庫版が出ている。講談社の訳が最も新しい。他に岩波文庫、筑摩書房からも出ている。
The Stanford Encyclopedia of Philosophy
McDonald, William, “Søren Kierkegaard”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/kierkegaard/>.
須藤訓任(他)編 『哲学の歴史 第9巻』 中央公論新社 2007年