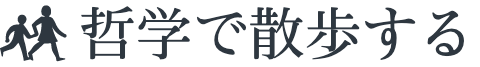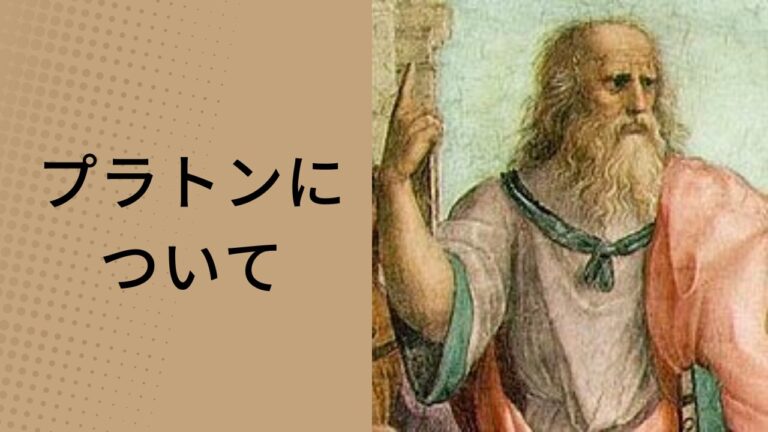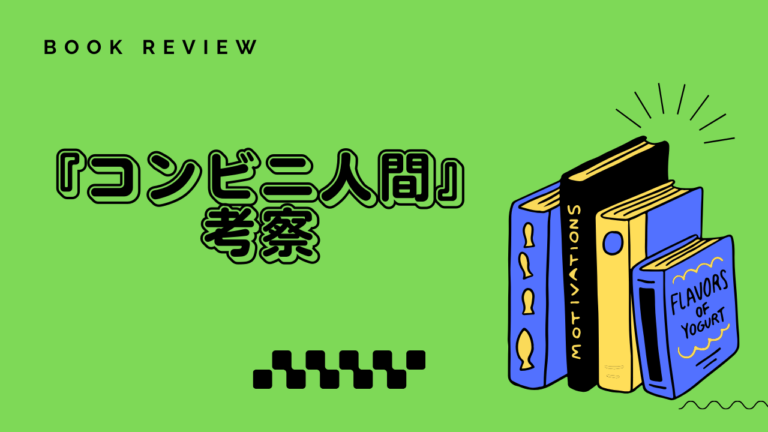- 2024年2月9日
- 2025年3月13日
プラトンの対話篇という形式にはどういう意味があるか【古代ギリシア哲学9-2】
プラトンは自身の著作をほとんど全て対話篇という形式で著した。対話篇とは、登場人物の対話によって、作品が進行していく戯曲・演劇形式である。では、プラトンはなぜこのような形式をとったのか。その意味・意義について、三つに分けて考えてみたい。 1つ目は、対話篇に描かれている対話を実際に行うことの意義についてである。その前提として、対話篇に描かれている対話がどのようなものなのかについて概観する。 2つ目は、 […]