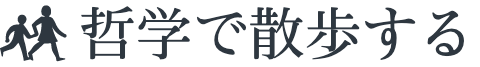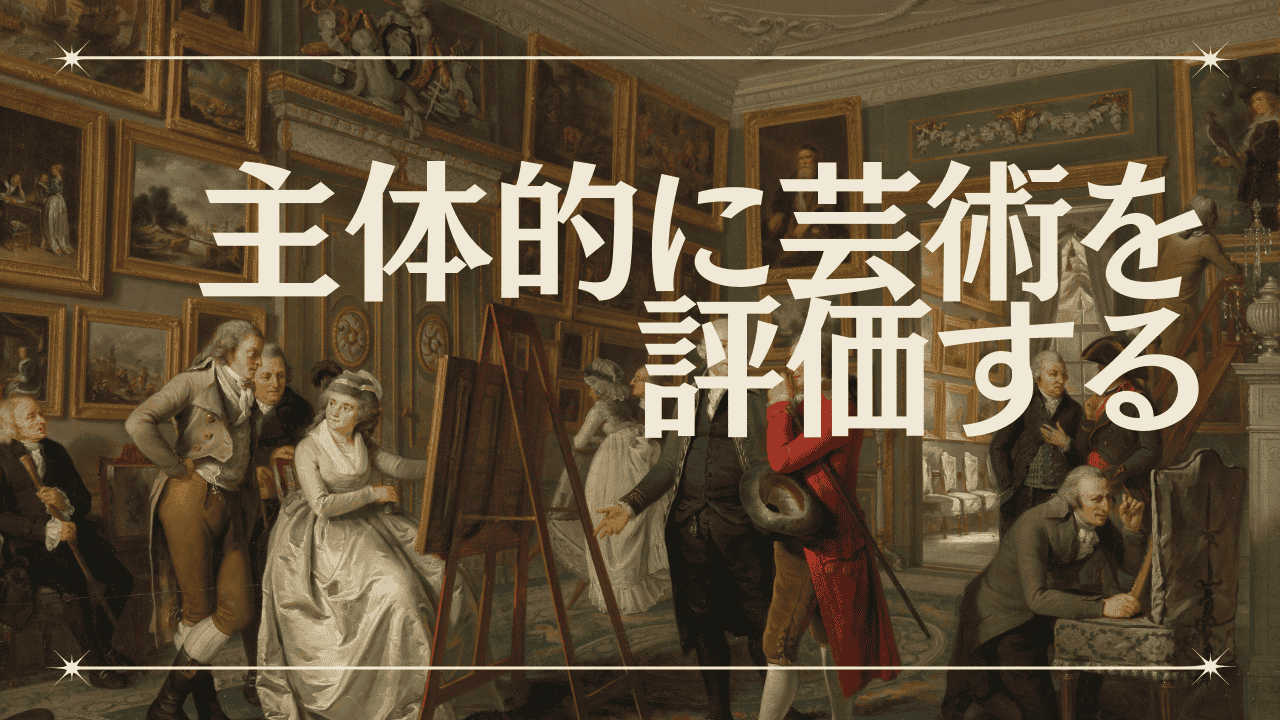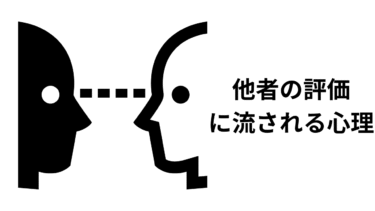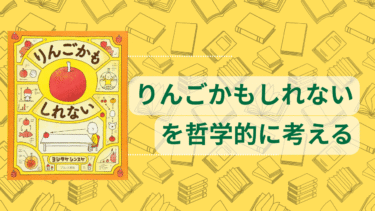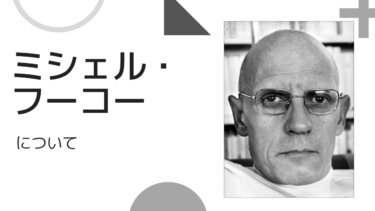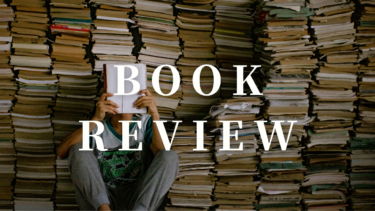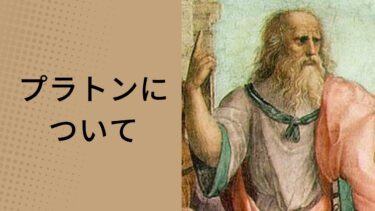前回の記事では、何かを評価することについて分析し、他者の評価に流される理由を論じた。そこでは、自分自身で評価する直接的な評価と、別の誰かの評価によって評価する間接的な評価を分け、直接的な評価の重要性を論じた。
そう論じたものの、世の中には間接的な評価が多く存在し、それが重要な場合もある。その典型例が、芸術作品の鑑賞である。
この記事では、芸術作品の鑑賞を例にとって、間接的な評価を参考にしつつも、自分自身で評価するためには何をするべきかを考える。
芸術作品の評価が間接的である点
芸術鑑賞は、以下の点において、他者の評価に依存した評価ともいえる。
1、価値があるとされているものを観る
そもそも美術館にある絵画は、価値があるとされているからそこにある。その作品が生み出されてから、歴史上のさまざまな人物の評価を受け、その結果として、美術的価値が認められた結果、美術館で展示されるに至ったのである。
つまり、その絵画に価値があると評価したのは、その場にいる鑑賞者ではない。
2、その作品についての情報を含めて観る
美術館には、画家や絵画についての情報が、作品と合わせて展示されている。それらの情報は、作品についての見方を提示してくれる。それはつまり、その作品が、どのように評価されてきたのかを提示することでもある。
そして、鑑賞者はその情報を見て、それを参考に、あるいは影響を受けてその作品を評価する。つまり、他者の尺度・基準で評価をしているということになる。
3、前提知識によって作品を観る
美術館に展示されている情報だけでなく、鑑賞者は自らの前提知識や経験をもとに、作品を観る。
前提知識は、それが〇〇派であるというような情報や、その作品の技法に関するものなどである。前者は、その作品の背景を想像するのに役に立つし、後者は直接的に作品を鑑賞する方法として役立つ。
また、経験も作品を鑑賞する際に重要である。直接的に影響を与える経験は、過去に作品を鑑賞した経験である。鑑賞の経験があれば、作品をどのように観るのか、どの点に注目するのか、過去のものとの比較などができる。また、単純に同じ作品を何度も鑑賞することで、一度観ただけでは気づかなかったことに気づくこともあるだろう。
そして、一般的な経験もまた重要である。何年か経ってから同じ本を読むと、当時はわからなかったことがわかるようになるのと同様に、経験を重ねることで、作品から読み取れるものも増えるだろう。
間接的な評価は不可避である
評価に含まれる間接性
このように、経験に基づいた評価以外は、他者の評価や、情報・知識をもとに評価することである。
また、経験に基づいて評価することは、他者の評価や情報には依存していないが、評価対象を評価者が評価する際に、経験という第三者が介入しているともいえる。そして、その評価が経験に大きく依存するならば、その評価は作品を直接的に評価したのではなく、経験によって間接的に評価しているといえるだろう。
たとえば、恋愛を題材にした作品を観るときに、鑑賞者に失恋の経験から、この作品の恋愛を悲恋であるとみなすことは、作品の評価が評価者の経験に歪められており、作品を直接的に評価しているとはいえないだろう。
純粋な直接的評価の不可能性
であれば、作品の直接的な評価とは何なのか。
作品を何の先入観も情報も経験ももたずに鑑賞し、その印象のみが直接的な評価になるのだろうか。しかし、その場合は、前提知識が必要な作品や、知性的なものの評価はそもそもできないことになる。
この場合、よく二項対立にされるのが、知性と感性である。そして、上記のような知性に歪められた評価に対する批判として、反知性主義が唱えられることがある。
だが、上記したように、知性による鑑賞と感性による鑑賞を厳密に分けることはできないのである。また、感性的な評価、つまり、感覚や印象による評価にも、情報や経験は入り込む。
したがって、評価の際に、間接的な基準を用いつつも、自分自身で評価することができるのかが問われることになる。
自分自身で評価するために—統合的な自己
知性はもちろんのこと感性も過去の経験の影響を受け形成される。そもそも、自分自身が自分自身でないものを含んで成り立っている。
問題に立ち返れば、評価されていることを理由に評価をすること自体は悪くないのだ。その評価をあたかも自分のものであるかのように取り違ってしまうことが、問題なのである。そうなってしまうと、他者の考え・言葉をただなぞって、拡散するだけの人間になる。宮台真司が言うところの「言葉の自動機械」である。これは、その人自身であるという個性の喪失であろう。
つまり、評価されているという理由で評価することも、評価の際に他者の評価や情報を参考にすることも、自分の経験を振り返ることも、最終的に評価自体が自分のものであると言えれば問題はないだろう。
そのためには、評価の主体としての自己を保っていなければならない。要するに、評価の最終決定権を自分がもっていなければならない。最終決定権をもっているとは、自分がその評価をするに至った経緯に対して自覚的であり、その経緯を自分が検証でき、納得できるということである。
そのためには、自分自身を振り返り、自分の思考プロセスを辿ることが必要である。そして、それを辿るためには、自分自身の思考に光を当て、顕在化する論理的な思考力が必要である。
なぜなら、非言語的で混然とした自己の頭のなかを整理し、秩序を与えるためには、論理的な構造を付与する必要があるからである。
したがって、間接的な評価の影響を受けつつも、自己が主体的に直接的に評価をするためには、自己批判の精神と自己を反省する知性が必要であるということだ。
実際、なんとなくの思いつきが実は何かの影響を受けていたということはよくあることだろう。印象も含めて、評価のプロセスを明示できるほどに、考えを論理によって秩序化することは、評価するときだけでなく、何かを考えるという行為一般において重要なのである。