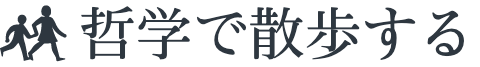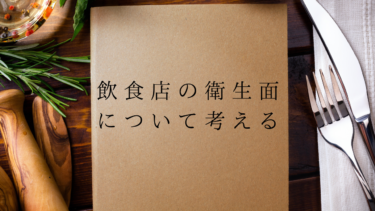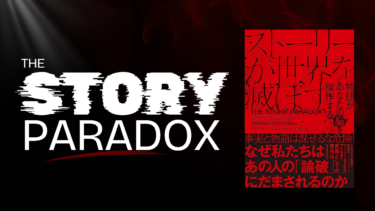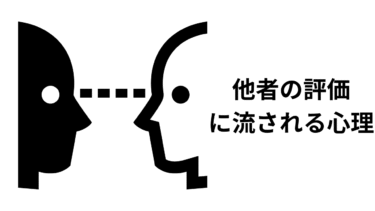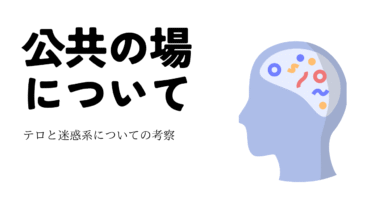現代を表現する言葉として、「疎外感」と「閉塞感」という言葉は定番であった。現代を批判的に論じる文脈では、それらに類する言葉は、哲学、批評、小説などジャンルを問わずに登場してきた。
しかし、おそらく疎外感や閉塞感は今後、さほど問題にされなくなるだろう、というのが今回論じるテーマである。その原因は、「世間」という概念が消滅しつつあるからである。
世間とは
世間とはどのような意味か。世間という言葉は、「世間では、〇〇である」のように使われる。これは、〇〇が、社会の一般的な常識であるというような意味合いだろう。
ということは、世間という言葉には、ひとまとめにされた同じような傾向をもつ人々による社会というような意味があるだろう。すなわち、世間とは、同質性をもつ集団を前提としている。
ゆえに、「世間が許さない」といった言葉が生まれる。同質な集団である以上、同質な価値観が存在しており、そこからの逸脱を許さない。いわば、同調圧力が存在するのである。
日本において、このような世間が存在してきた背景には、民族・文化の均質さや、外国の影響の少なさなどによって、この均質さを揺らがせるものが少なかったことが原因としてあるだろう。要するに、従来、日本人は、食事からメディアに至るまで、同じものを消費してきたがゆえに、均質性を意味する世間という概念が生じたのである。
世間が疎外感・閉塞感を生む
疎外感
世間という概念が存在することは、疎外感を生む原因になる。
疎外感とは、何かから疎外されている感覚だが、この何かが具体的で個別な組織であれば、疎外感はそこまで生じないだろう。
仮に、ある組織から追放されたとして、追放されたときは、疎外感を覚えるだろうが、その組織は他にも多く存在する組織の中の一つに過ぎず、また別の組織に属せば良い。そう思える限りは、疎外感は持続しないはずだ。
実際に、拒絶された集団や組織は、個別の存在であり、カテゴリーのなかの一部にすぎない。それゆえ、それぞれ別の基準をもっており、同じわけではない。
しかし、それらの集団は社会の中に属しているため、世間という集団がそれらを包含する。世間が同質である以上、それらもまた、同質性をもっていることになる。
仮にある集団から疎外されたとしても、また別の何かを探せばいいのだが、世間という最も包括的な集合体が均質であるならば、それに属するあらゆる組織が均質になってしまい、結果的にあらゆる集団・組織から疎外されていると感じることになる。
したがって、世間という概念が疎外感を生むのである。
閉塞感
世間という概念が存在することは、閉塞感を生む原因になる。
上述したように、世間とは、社会に存在する人々をひとまとめにした概念である。ということは、世間とは、人が所属する組織なかの最上位の組織である。
人は、階層的に様々な組織に所属している。ある会社に属し、その会社の中のある部門に属し、その中のある部署に属している、というようにである。そして、程度の差はあれ、より上位の組織の雰囲気は、より下位の組織に影響を与える。たとえば、上層部が不祥事を起こした会社は、全体的に不安感が漂うだろう。
であれば、世間の雰囲気は、良くも悪くも人々に影響を与える。社会全体がバブルのようにお祭りムードであれば、直接関係なくても、浮かれ気分になるだろう。その逆で、世間に閉塞感があれば、その影響を個人も受けるだろう。
したがって、世間という全体感が存在するがゆえに、社会規模の閉塞感が存在する。
世間の崩壊
しかし、現在、世間という概念は崩壊しつつあるだろう。それは、あらゆるものが多様化しているからである。メディアにせよ、職業にせよ、今までの同質性の前提が崩れている。
世間とは、人々を同質なものとしてひとまとめにした概念だったが、この同質性が崩れれば、ひとまとめにできなくなる。すると、当然、世間という概念は崩壊する。
世間は全体であった。この全体が崩壊すると、残るのは、個別の集団のみである。となると、他人同士を同質性によって結びつけてきた世間がなくなるため、個々人がその個人の世界を別々に生きることになる。
このように、世間がなくなると、すべての人々に覆い被さるように影響を与えてきた全体がなくなるため、疎外される全体も、その雰囲気もまた存在しなくなり、全体に由来する閉塞感・疎外感がなくなるのである。
空白化するパブリック
以上で、世間がなくなると、疎外感・閉塞感がなくなることを論じ終えたが、以下でその先の社会について少し考えてみる。
世間という見知らぬ他人同士を結びつけていた概念が消滅すると、公共性の質が変わると思われる。その変化はおそらく、均質な世間によって統制されていた公共の場が、無秩序化することだろう。
そして、おそらく、公共の場でのテロがなくなるのではないかと思われる。いままでの日本でのテロは、社会に対する憎悪を、社会の象徴であった公共の場にぶつけるものであった。だが、世間が解体されると同時に、全体としての社会が消滅し、公共の場は、単なる人の多い場所に変わるだろう。
その代わりに増えるのが、公共の場の私物化だ。今現在も問題になっているが、マナーが悪い客が増えるだろう。そして、公共の場を私物化する象徴的な行為が、SNSの撮影だ。これも増加するだろう。
これらの根本には、世間の崩壊によって、他人を自分と同じ存在であると考えられなくなり、共感や配慮が喪失することによって、モラルが低下することがあるだろう。
今後の展望
ここでは、世間という全体の崩壊を論じた。今後、全体は解体され続け、個々の所属する組織のみが存在する世界となるだろう。フィルターバブルという言葉があるが、その言葉のように、個々人が小さなバブルのなかを生きていく世界になると思われる。
しかし、今後、全体の復活を望むという可能性も残されている。かつては国民全員が関心をもっていたイベント、たとえば、オリンピックや紅白歌合戦などの関心が低くなっており、全体の崩壊が進みつつあると思われる一方で、最近では、特に政治において、国民の関心の高まりが見られる。
この関心の高まりが、「日本国民」という全体的な概念の復活を意味しているのか、それとも、個々人が個別に現状の生活に不満を持っており、その不満が集積した結果、全体のようにみえているのか、これはまだなんとも言えないだろう。