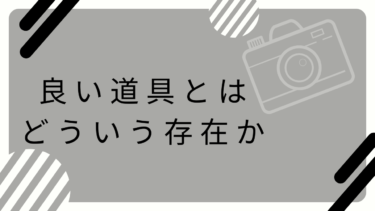哲学チャンネルはこちら↓
前回の沁みるを哲学する2では、沁みる体験と沁みない体験を日常と比較することで非日常として沁みる・沁みない体験を捉え、日常の抑圧の形態について論じ、そこからの逸脱としての沁みる・沁みない体験を論じました。
今回は日常と沁みる体験について重点的に分析し、論じていこうと思います。
日常と現在
日常と非日常の間としての現在
前回の記事においても行ったものの、日常と沁みる体験についての区別について、今回はより重点的に分析していこうと思います。
日常とは何なのか。前回、日常とは冒険によって新たな領域が確保されていくため、拡張されるものであると述べました。拡張されうるということは、日常は非日常と接続しているということです。子供にとって、お使いが冒険であるのは、最初の何回かだけで、しばらくするとそれに慣れます。学生のクラス替えや、配置換えも1ヶ月もすれば、日常になるでしょう。このように日常は、非日常と接しており、非日常を受け入れることで、少しずつ、あるいは一気に変化しうるのです。つまり、非日常は日常と地続きであり、跳躍ではないということです。
では、日常が非日常と接しているのは、どの地点でしょうか。それは、行動を選択する今この瞬間です。すなわち、今この瞬間において、非日常が日常に混入する可能性が存在します。新しく日常となったお使いも、そのお使いを初めてした瞬間は、非日常であったわけです。その選択をし、行動をした瞬間は、可能性として日常と非日常が混在し、どちらにでも転びうる状況であったといえます。仮に、お使いをせずに、今までどおりの日常の選択をしていたら、その瞬間に非日常に触れていた境界線は消滅し、いわゆる分岐点のようなものも消滅します。そこで非日常へと踏み込むと、日常の境界線が揺らぎ、非日常と日常の領域が混じり合い、混乱します。この混乱が徐々に収まり、落ち着いていくと、それが新しい日常となります。その収束には、一定の期間が必要となります。したがって、非日常の日常化は、ある程度の時間が経った後に、この混乱の収束後に振り返ることで可能になるのであり、過去となった非日常に対して生じるものなのです。つまり、日常とは、もともとは、日常化された非日常であり、時間の経過が日常を形成したということになります。そのため、過去には非日常との接点は存在しないことになります。
その理由は、今この瞬間が非日常という未知に接していますが、選択された非日常はすでに過去であるからです。過去の瞬間は、非日常という未知なる可能性には接していません。それはすでに決定されたものであり、揺れ動くことはなく、境界線を持ちません。そのため、過去の時点では、非日常への選択であったとしても、それは選択された瞬間に、可能性から現実へと変わり、日常の領域へと組み込まれていくということになります。これは、論理的な必然であるといえるでしょう。
従って、今現在の瞬間の各場面において、選択の余地として、非日常が存在することになります。これは前回の冒険と安定でも述べた通り、ある選択に対して、冒険的な選択と安定的な選択が両方あり得るということです。つまり、目の前の選択・決断は、すでに日常と非日常の境界線上に立っているといっていいでしょう。日常とは、過去に選択された非日常の堆積であり、もともと非日常だった領域へ拡張された領域であるということになります。
場所なき現在
現在が、日常と非日常の境界線上であるということは、現在は、日常でも非日常でもないということになります。現在とは、いわば、幅を持たない境界であるといえるでしょう。
それは、常に次の選択の可能性を秘めており、その可能性は常に日常の外側を含んでいるからです。現在という行為選択の瞬間には、常に今までの延長である日常を否定しうる契機(モーメント)が含まれているということです。
ということは、原理的には、現在とは、その行為選択の可能性としては、無限の可能性を秘めており、その瞬間においては、日常と非日常の枠組みが影響を及ぼさないといえるはずです。例えば、駅から家まで歩く道のりにおいて、まさに今この道を歩いて家に行くという、いつも通りの選択=日常的行為をする瞬間には、実は無限の非日常への可能性があるのです。今から別の道を通ることもできますし、そもそも家に帰らないで、そのまま旅に出かけてしまうこともできるのです。その瞬間に能力的にしうることならば、あなたは何だってしうる、というのが現在であり、今という瞬間の可能性です。そこには、普段していることをしなければならないという必然性はなく、自由であるのです。そして、この日常の外に出ることは、それが小さな逸脱だとしても冒険であるのです。
このように、原理的には、現在は、無限の行為選択の自由があり、その瞬間においては、日常と非日常は混ざり合い、次の瞬間は全くの未知なる可能性であるということです。
現在の異邦性
上の論述において、「原理的」という言葉を多用しているのは、確かに原理的にはそうなのですが、現実としては、日常の枠組みが強固に今この瞬間を規定しているということを意図しています。日常の枠組み、例えば習慣は、強固であり、通常人は疑いもせずにこれに従っています。それは、なぜなのか。
現在という瞬間は、原理的には、無限の行為の可能性があります。朝起きて、家を出て、電車に乗るときに、ふと反対側の電車に乗っている人の顔を見ると、彼らには彼らの生活があって、それは、自分とは反対の電車に乗ることなのだと不思議に思うことが、私にはありました。そして、確かに自分も今からあの電車に乗ることはできるのだと考えます。しかし、それは想像上のことで、実際に反対側の電車に乗ることはありません。この電車に乗ること、そして決められた場所へ毎日通うこと、これが私の日常だったからです。
しかし、いうまでもなく、その日常とは、私が自分で選んで行為していることにほかなりません。別に想像上ではなく、実際に反対側の電車に乗ることもできるわけです。そうして、日常を放棄して、反対側の電車に乗ってみます。すると、最初は逸脱の奇妙な興奮が味わえるはずです。しかし、徐々にこのまま私はあてもなくどこへ行くのだろうか、と不安を感じるかもしれません。なぜなら、そこには、目的が欠けているからです。行くべき場所がない、その先がない。つまりは目的がない。これが人を不安にさせます。
確か、夏目漱石の『夢十夜』にも同じような話があったと思います。どこへ向かうのかわからない船から飛び降りた主人公は、身を投げた瞬間、しかし、どれほどその船が気に入らなくとも、それでもやはり、それに乗っていたほうがましだったと後悔しながら海へ落ちていく。その行き先がどこであれ、無目的の海に彷徨うよりはましである、かもしれません。
日常を逸脱したとき、そこに待っている無目的は、人を不安にさせる。そして、再び人は日常へと戻る。それ自体は可能でしょう。たとえ、学校や職場を1日無断で休んだとしても、退学や退職にはならないでしょう。しかし、問題は、一度逸脱することで、無目的という影が、日常に付き纏い始めることです。逸脱に突きつけられた無目的は、翻って今の日常にも突きつけられるのです。「一体何のために?」という問いが、日常に侵食し始めるとき、すでに日常という強固な枠組みは崩壊しているのかもしれません。
なぜならば、今この瞬間が、目眩のするほどの自由に満ちており、一体何をすれば良いのかわからないということを避けるために、人は強固な日常を拵えたからです。元来原理的に存在する自由を制限し、私は何をするべきなのか、私は誰なのかを与える構造が日常なのです。
日常と沁みる体験
回帰する場所
人は、無際限な現在を制限する日常を求めている。と同時にやはり、この日常の檻から逃れようとする欲求を持ってもいる。この相反する引き裂かれた本性が人間にはあります。このことは、前回にも論じたことでもあります。
現在の瞬間には無際限の選択肢があり、そのどれもが別に何によって正当化されるわけでもない。そこには特別な目的もない。この無目的性がおそらく日常の基底にあると暴かれたとき、日常は無垢な存在ではなくなります。日常は内側に疑念を抱えた存在になり、日常という枠組みが、自由な現在の瞬間をコントロールすることへの不信感を抱えることになります。こうして、ぼんやりとした、言い知れぬ不安を人は抱えることになります。この不安とは、それまでの日々を制御し、正当化し続けてきた日常への懐疑からきており、これが現在という瞬間に常に日常とは別の道を誘うことになるのです。あたかも束縛が緩んだかのように。
そのような疑念の中にありつつも、日常の枠組みを何とか保っている。それは、たとえ日常に無目的が忍び寄っているのだとしても、それが自由を封じる枠組みとして機能することは確かだからです。それは、かつての非日常の堆積が日常という領域を作り出し、その領域が主観的な世界を形成しているからです。
また、慣れ親しんだ行為や思考は、体に染み付いているかのように、考える必要なく、反復されます。習慣は考えることなく人を動かし、熟練もまた意識的な運動なしに人間に高度な運動を可能にします。積み重ねられた思考や行動は、形状記憶のように人間に蓄積し、日常の枠組みを形成します。これは、身体の次元を作り出します。
身体的なものは、人間にとって最も身近で、原始的なものです。身体運動は、考える必要がありません。身体はあたかも意識と切り離されたように、自律的に動いています。私は、私の意思に関係なく、生理的な欲求を覚えます。勝手に腹は減るのです。そこに合理的な理由は存在しません。ただ単に腹が減るのです。そして、それは苦痛となり、その解消を求めます。理由や目的なき、自律的な身体の運動と欲求の次元が、こうして再び顕になるのです。それは一旦は成長とともに社会性の陰に隠れ、社会的な評価を求める方向へと向かっていた人間に対して、無目的性の基底が暴かれたのちに、再び現れる最終的な拠り所のようなものといえるかもしれません。
結局、全てが無根拠であるならば、空腹を満たすという、いわば原始的で野蛮な欲求こそが最終的に行為の目的になる。拡張して言えば、自らの身体的な欲求こそが、無目的性の中で、最も本来的な行動の指針であるということになります。
身体への回帰
さて、どうも難しい話が続いてしまっているかもしれません。しかし、これは単に抽象的な話ではないのです。現実に、さまざまな場所で、具体的に生じている現象でもあるのです。
現在の瞬間がもつ無限の自由に幻惑され、かえって不自由を望むということは、古今東西語られていることです。ある種の宗教や占いは、この類のものでしょう。また、日常の持つ無目的性が密かに、しかし明確に暴かれているという現状は、現代社会には顕著でしょう。少し前に、とある駅の広告で、「仕事は楽しいですか」といったような趣旨の文言が掲載され、批判にさらされました。「一体何のため」が欠落していると叫ばれて久しい社会です。さらには、既存の価値形態が崩壊しつつあることもこれに拍車をかけています。一時期、Youtuberやプロゲーマーが社会的に胡散臭がられていたのですが、そもそも現代の文化産業が支配する現状において、真に「意味のある」仕事など存在するのでしょうか。そもそもそれを誰が決めるのでしょうか。「私にとって意味があれば良い」と言って、アイドルなどの推しに高額の金銭をつぎ込むこともよく見る光景です。Vtuberなどのライブを見れば、会ったことも、顔を見たこともない人間に対して、金を注ぎ込む人間が実に多くいることに驚かされます。しかし、これも、以上の議論からすると驚くことではないのです。むしろ、必然的な帰結とすら言えるでしょう。
目的を失い、意味を失った日常は、無目的となります。すると、無目的の中から、同じ無目的な欲求が蘇ります。外部に依存しない、本性的な欲求である身体的な欲求が復活するのです。こうして、本能的な欲望がいささか下品に見えるほどに、社会的に蔓延していくわけです。それは、身体的な欲求しか、もはや確たるもの、確かに意味があるといえるものが存在しないからです。
こうして、異邦的な日常を埋める身体的なものが要求されるようになります。それは、身体に直接働きかけ、精神を強制的に充溢させる機能があります。甘いものを食べると、人は強い快楽を感じ、その快楽は、日常の空虚さを覆い尽くします。ジムで筋トレをするとき、人は身体的に追い詰められます。そのハードワークの最中に、あるいはその後の開放感を感じるときに、人は日常の空虚さを忘れます。最近のトレンドは基本的にはこの線で動いているといっていいでしょう。
身体に訴えかけ、直接作用するものは、今この瞬間をまぎれもなく占有します。温泉に入るとき、身体が溶け出していく感覚に、身を委ねることができます。その瞬間の全てが、温泉に浸かっている感覚によって占領されます。何も余計なことを考えることなく、その瞬間に没頭すること、これが異邦性を孕み不安と化した日常を、さらに原始的な次元に、疑問の余地のない没我の次元に連れ戻してくれるのです。これが、沁みるものに特有のノスタルジーの一つの側面でしょう。
身体の共有と精神化
身体への刺激、身体的感覚はあくまでも個人のものであるでしょう。温泉に浸かって気持ちがいいのは、私だけで、他の人まで気持ちよくさせるわけではありません。しかし、人には共感するという機能がそなわっています。人は他人に自分を投影することができます。そうすることで、あたかも自分がその体験を味わっているかのような感覚さえ得られるのです。「飯テロ」という言葉はまさにそれを表しているでしょう。
身体的感覚は、共有し、集団として感覚することができます。その共有は、その感覚が低次元のものであればあるほど、伝播しやすいのです。なぜならば、低次元の感覚は、普遍性を持つからです。痛そう、美味しそう、気持ちよさそう、などの身体的感覚は、単純であるがゆえに多くの人を動員できます。貧しい国の子供の写真、ふわふわパンケーキの映像、あるいは見た目のいい人間の画像、こういったものは、多くの人に感情的に訴求できるのです。このことは、テレビやネットニュースを見れば一目瞭然です。これが仮に、高次元な感覚、たとえば極めて微妙なニュアンスを表現するものであった場合、それは伝播しずらいのです。食・絵画・音楽・映画・小説など、単線で複雑さのないものは、低次元のものです。タレの味しかしない食べ物、単に似ているだけの絵、ヒーローが悪者をやっつけて終わるだけの映画、こうしたものは、単にそれだけでしかないものです。高次元なものは、色々な味わいが複雑に絡み合うもので、その中のどれもがバランスよく含まれており、単に一方向からだけのものではなく、さまざまな視点が組み合わされ、あるものを肯定せざるを得ないとしても、その肯定に対して自己批判的であるものなのです。
身体という基盤において、共有されている感覚を媒介して、熱狂が生じます。熱狂とは、集団と一体化した身体における高揚であるといえます。熱狂は熱狂を作り出すこと自体を目的ともします。そのため、集団的な感覚の共有は、自己目的であるといえるのです。
身体的感覚の共有を媒介とした集団化は、ファシズムの形成において典型的に見られる現象です。あるいは、カリスマと呼ばれる人物とその周辺の人間に生じる関係ともいえるでしょう。こうして、接続された身体的感覚が、集団による高揚を生じ、熱狂し、そして、その中心点に象徴的人物が担ぎ上げられる。この中心点の創出によって、価値の階層化が生じ、制度化された価値体系が生まれる。こうして、身体を中心に構築された熱狂が制度化され、身体を離れた価値を創出することになります。
元来身体に基づいた価値であったものが、身体を離れていき、それ自体としての価値として自立していく。この過程がおそらく文明化であり、社会化であるということでしょう。どこにも根拠はないが、それが価値として認められるということは、人が他人に価値があると思われているものに価値を見出す性質を持っているということを物語っています。こういった性質がなければ、おそらく単なる利便性からのみでは、貨幣は存在し得なかったでしょう。欲望・感覚の共有が、欲望・感覚を一律的な基準で計るということをそもそも可能にしたと考えられます。
まとめ
要約
現在の瞬間が持つ自由という無規定性、そこから逃れるための枠組みとしての日常、しかしその日常には客観的な妥当性はない。実は無目的である。このことに気づき、日常が基盤としていた社会的生活、社会的価値観を解体せざるを得なくなる。こうして、人は自分にとっての真実、主観的なものを求めるようになる。その結果、究極的な主観性である身体、そして身体感覚へと行き着く。この身体感覚は、全くの個人の感覚で、個人を集団から閉ざすものである。パンケーキのおいしさも、筋トレのきつさも当人にしか感じられない。しかし、一方で、人は共感し、共有しうる感覚を持つ。それは熱狂となり、感覚の共有、熱狂の蔓延、集団による感覚が自己目的化する。すると、集団が一体化するようになり、個人が集団に吸収されるようになる。個人は集団の中で各々の場所を与えられるようになる。一体化は、個人を一つの集団の内部に集約し、外部を与えない。つまり、人は、集団の中においてその人としてのアイデンティティを与えられることになる。そのアイデンティティは、集団が集団の都合によって、集団の内部の観点から、個人を規定するものである。集団化したい個人は、集団によって自らを規定されることを望む。こうして、集団は内部に独自の価値体系を持つように仕向けられるのである。この価値体系とは、社会的な価値観へと拡大し、それが内面化され、それに則った日常が個人に枠組みを提示する。
このように、一周して戻ってきてしまうわけです。この意味でも、人は引き裂かれた存在であるということが当を得ているのではないでしょうか。
身体への回帰とそこからの集団化が、身体という無根拠であるがゆえに固有で、本質的で、本来的なものとして、既存の価値体系を打破するものとして現れるとき、身体がすでに与えられているものであり、本来的であるという思想が生じ、それが身体を共有する集団としての国家へと拡大していく。これがナチズムの本質的な思想であることをレヴィナスは指摘しています。
まとめ
沁みる体験とは優れて身体的な体験であり、同時に精神的な体験でもあります。この感覚を思い起こして、私が最も特徴的だと思うのは、沁みるという感覚が、自己への退却であり、周りとの接続を断つことであることです。沁みる感覚は、それを味わっている最中に、その感覚に全てを委ねることができ、その瞬間に没入します。これは、普段の状態がさまざまなものに接続されている、注意を向けていることと対照的でしょう。この感覚を中心に据えて、これまで沁みるについて考えてきました。
徐々に思索を深めると同時に、多方面の問題を巻き込みすぎ、回収不能となった感は否めませんが、まずは風呂敷を広げてから整理するのが重要と思い、あえてこのままにしておこうと思います。