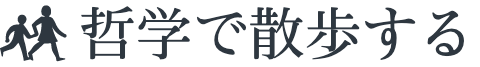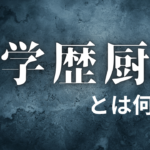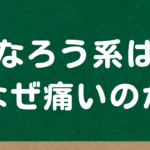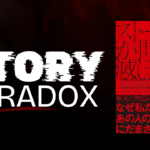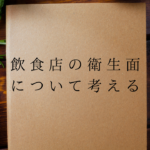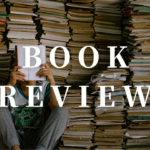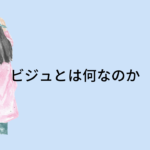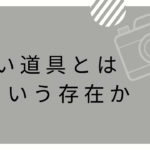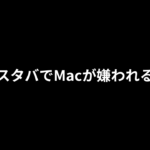様々なことに関する批評、感想等々です。
現代は感情が過激になっていると思われる。その理由は、主にSNSの普及によって、不特定多数に通じやすく、より感情を掻き立て、注目を集める言説が流布しやすく、それが感情的に過激なものだからだろう。(前回の記事で詳しく論じた) この記事ではまず、現代において感情が過激化している事例を取り上げ、分析する。その上で、そのような過激な感情から自己を保ちつつも、どのように社会と関係していくべきかを考える。 &n […]
「学歴厨」という言葉が存在する。学歴厨とは、学歴至上主義で、学歴の高低で相手を判断し、見下してマウントをとったり、尊敬したりする人間を指す言葉である。比較的最近生まれたネット上のスラングのような言葉だ。 そもそも、学歴自体は昔から存在しており、ひと昔前のほうがその重要度は高かった。企業の採用においても、ひと昔前のほうが学歴を重視していた。最近では、さほど学歴を重要視しない企業も多いと聞く。また、イ […]
最近、「なろう系」と呼ばれる作品が、ライトノベルやアニメに増えており、人気が増している。しかし、それと同時に、「なろう系」は「痛い」や「うざい」と言われてもいる。この記事では、なぜ「なろう系」が「痛い」と言われるのかについて考察する。 目次 1 なろう系とは2 なろう系はなぜ痛いのか2.1 1、主人公の能力に必然性がない2.2 2、主人公に苦難がない2.3 3、主人公が調子に乗ってい […]
内容についてはこちらから↓ ストーリーが世界を滅ぼす posted with ヨメレバ ストーリーが世界を滅ぼす Amazon Kindle 楽天ブックス 目次 1 『ストーリーは世界を滅ぼす』の考察2 寛容さ3 物語と人の関係の研究4 科学の権威5 悪役のいない物語6 まとめ 『ストーリーは世界を滅ぼす』の考察 本書では、ストーリーの負の側面に対して、4 […]
現代を表現する言葉として、「疎外感」と「閉塞感」という言葉は定番であった。現代を批判的に論じる文脈では、それらに類する言葉は、哲学、批評、小説などジャンルを問わずに登場してきた。 しかし、おそらく疎外感や閉塞感は今後、さほど問題にされなくなるだろう、というのが今回論じるテーマである。その原因は、「世間」という概念が消滅しつつあるからである。 目次 1 世間とは2 世間が疎外感・閉塞感 […]
先日、とある飲食店に行ったところ、出された取り皿が、洗い残しと油で汚れているようだった。結局、その取り皿を取り替えてもらい、その後、問題はなかった。だが、こういったことがあると、その店の衛生管理を疑問視してしまう。 社会全体でみても、飲食店での食中毒や、不衛生な管理体制は、度々ニュースにも取り上げられているが、こうした経験やニュースがあると、飲食店が信用が信用できなくなり、安心して外食ができなくな […]
前編はこちら↓ 前編では、物語とは何か、物語の人への効果とは何か、物語の良い点・悪い点についてまとめた。 後編では、そのような物語にどう対処すればいいのか、その解決策をまとめる。 ストーリーが世界を滅ぼす posted with ヨメレバ ストーリーが世界を滅ぼす Amazon Kindle 楽天ブックス 目次 1 不可欠な存在 […]
SNS上ではさまざまな情報が飛び交っている。それらは、単なる情報なのではなく、発信者の感情や立場を背景に、加工された情報であることが多い。同様に、従来のメディアである新聞やテレビも、長らくそのような加工をしてきたことが、視聴者の知るところになった。 特に最近は、メディアの影響力を争う過程で、SNSと従来メディアが対立する言説を発信することも少なくない。このような有様は、まるで語り部同士のストーリー […]
この記事では、社会が暴力的になる背景を分析する。 昨今、社会は徐々に暴力的な傾向を帯び始めていると思われる。世界各地で分断が叫ばれ、違う立場の人間が互いを罵り合うというような光景は珍しくない。そういった政治的な領域だけではなく、日常生活においても、従来の調和を重んじる人間関係から、より直接的で対立を厭わない人間関係に移行しつつあるように感じる。 「意見が合わない」や「対立を厭わない」ということそれ […]
『これからの男の子たちへ』太田啓子著の批評1のつづきである。 『これからの男の子たちへ』太田啓子著の批評1 目次 1 疑問点1.1 潔癖にしすぎることによる弊害2 まとめ 疑問点 潔癖にしすぎることによる弊害 次の疑問点は、子供の世界を、クリーンにしすぎていいのかというものである。いわば、倫理的に潔癖にしすぎてはいないかということである。 本書において、男の子だからという理由で、問題行為を放置する […]
『これからの男の子たちへ』という本を読んだ。内容は、旧来のステレオタイプ的な「男らしさ」の価値観がもたらす弊害について論じられている。 論じられている内容は、どれも原理的に正しく、そうあるべきだと思えるような内容になっていると思う。一方で、その原理的な正しさゆえに、理想論的な要素があるように思えた。また、やや著者個人の主観性に傾いているようにも思えた。 以下、本書の賛同できる点と疑問点を論じる。 […]
今回は、内田樹著『勇気論』の第二章について考察する。 第一章はこちら↓ 内田樹著『勇気論』第1章への同意と反論 目次 1 第二章の要約1.1 編集者の質問1.2 著者の回答2 批評2.1 質問と回答の不一致2.2 質問の分析2.3 質問の回答3 まとめ3.1 疑問点3.2 学べる点 第二章の要約 この章も第一章と同じく、往復書簡(手紙のやり取り)の形式をとっている。 以 […]
「ビジュ」とは、ビジュアルを略した言葉であり、容姿(顔のみならず全体的な雰囲気やスタイルを含んでいる)と同じような意味である。この「ビジュ」という言葉は、若者の間でよく使われている一方で、この言葉が嫌いだったり、気持ち悪いと思う人も多いようだ。 実際、「ビジュ」という言葉について、批判的に論じている記事を読んだ。 その記事(以下、参照記事)では、「ビジュ」という言葉は、従来の言葉(たとえば「美人」 […]
今回は、ショートコンテンツの人気について考察する。 ショートコンテンツとして念頭においているのは、TikTokやYouTube Shortといったプラットフォームに投稿されている1分未満の動画である。 ただ、このような動画コンテンツの他にも、ショートコンテンツ化されているものは多い。例えば、音楽においても、近年尺が短くなっているというデータがある(1)。スポーツでいえば […]
内田樹著『勇気論』を読んだ。この本は、勇気についてを中心としつつも、各章は独立している。そのため、まずは第1章の内容についてまとめ、賛同と反論を論じる。 勇気論 内田樹著 posted with ヨメレバ 勇気論 Amazon Kindle 楽天ブックス 目次 1 本書について2 本章のまとめ2.1 感情的な側面2 […]
浜田寿人著『ウルトラ・ニッチ』を読んだ。実に興味深く、2時間ほどで読了してしまった。 この本において、特に気になったのは、p.160-178にかけて、そしてその後も言及される、コストパフォーマンスや安売りに対する批判である。 コスパという言葉はダサいので、なくすべきだという主張までなされている。(p.165) 本記事では、その著者の主張をもとに、コスパとは […]
Kindle UnlimitedというAmazonがやっている電子書籍のサブスクサービスがあります。月額1000円弱で、対象の書籍が読み放題というものです。 私はこのサービスを利用していて、よく作品をダウンロードするのですが、ダウンロードしたものの、読んでいない本や読みきっていない本がかなりあることに気づきました。書店で買った本にも、積読状態の本は多くあるのですが、体感 […]
2024年公開の劇場版名探偵コナン『100万ドルの五稜星』の感想・批評をnoteにアップしました。 映画は、観ていて楽しかったですし、楽しませようという制作者の意図も伝わりました。 ただ、やはりストーリー的な問題点が多かった印象です。そのあたりの批評がメインになっています。 コナンの映画は毎年楽しみにしているので、その分内容が辛辣になったかもしれませんが、お許しください。
先日、喫茶店で、少し高級な万年筆を使う機会がありました。その万年筆を使っていると、なんともいえない「いいものを使っているな」という満足感を覚えました。そして、この満足感の原因は何だろうかと考えてみたくなりました。 そこで今回は、良い道具とは何なのかについて考え、良い道具を使う体験について考えます。 目次 1 良い道具についての分析1.1 良い道具とは1.2 良い道具の使用体験1.3 […]
この記事は前回の続きです。 目次 1 ダサい自意識1.1 社会の基準への盲従1.2 他者の視線が自意識である1.3 他者を利用して自意識をつくる2 まとめ3 注釈 ダサい自意識 以上のことを前提に、「〜している自分かっこいい」がなぜ煙たがれるのかを考える。 その理由は簡潔にいえば、自意識が未成熟であるからである。そして、その未成熟性が、他者を巻き込むからである。 この未 […]
スタバでMacを開いている人が、「スタバでMac開いている自分かっこいいって思ってそう」と煙たがれることがある。他にも、洒落たこと、「意識高い」とされていることをする人が、『「〜している自分かっこいい」と思ってそう』、と煙たがれることがある。よりはっきり言えば、嫌われる。 それは一体なぜなのかについて哲学的に分析する。結論を先取りすると、自意識が未熟であり、さらにその自意識の形成のために他者を利用 […]
この記事は前回の続きです↓ 目次 1 アトラクション的楽しみ2 世界との直接的なつながり3 まとめ アトラクション的楽しみ 第二に、「写ルンです」には、アトラクション的楽しみがある、ということが挙げられます。アトラクションといえば、ジェットコースターや観覧車がまずはじめに思い浮かぶと思います。それらと「写ルンです」は、全く違うものだと感じるかもしれません。しかし、両者に […]
今回は、「写ルンです」(簡易フィルムカメラ)がなぜ人気なのかについて、哲学的に考えていきたいと思います。 今では、スマートフォン(以下、スマホ)で簡単に高画質の写真が撮れます。にもかかわらず、「写ルンです」が再び注目されているといいます。その原因を考えていくことで、 多機能であることの問題点とは何か 不便さ・レトロさが人気なのはなぜか 現代は、世界と直接つながることが求められている こうした、さま […]
前回は、リラックスとは何かについて、具体的なリラックス方法を挙げ、それらの方法に共通する点を考えました。 今回は、そのような性質をもった行為が、なぜリラックスになるのかについて、そもそもリラックスの意味である緩める・和らげるとは、一体何から緩和するのか、そしてどのように緩和するのかを論じたいと思います。 目次 1 リラックスを求める原因は何か2 なぜ日常がストレスとなるか2.1 タス […]
今回の哲学チャンネルのテーマは、リラックスとは何かについてです。 現代人の忙しさやストレスが叫ばれるようになって久しいですが、それと同時に求められるようになり、今では日常に定着しているのがリラックスでしょう。そんな現代社会を象徴するようなリラックスとはいったい何なのかについて、哲学的に考えてみたいと思います。 目次 1 リラックスという言葉の意味と具体例1.1 言葉の意味1.2 リラ […]
今回は、村田沙耶香著『コンビニ人間』について、考察したいと思う。 今回の考察のテーマは、「まとも」と「まとも」じゃないということについてである。言い換えれば、「正常」と「異常」である。このテーマは、この小説を読んだ人ならば、考えざるをえないものであるため、この小説の核心的なテーマであるといっていいだろう。 具体的には、「普通の人」がもっている「普通さ」とはいったい何なのか。そして、主人公は「異常」 […]
よく、「今年も1年あっという間だったね」といった言葉を聞く。「時間が経つのは早いね」という言葉も聞く。そして、年齢と時間の流れが関係しているということも聞く。それによると、年をとるほど体感時間が早くなるというのだ。では、年をとったから時間は早く流れるものだといって済ませてしまうのは癪に触る。どうすれば、「あっという間」をなくせるのか。どうすれば、しっかりその時間を過ごした感覚を得られるか。それを考 […]
前回の記事はこちら↓ 集中とはなにかの基本的な分析 前回、集中についての基本的な分析を行なった。そこでは、集中状態が選択肢の排除であることを論じた。そして、選択肢の浮上は、集中の途切れであり、この状態が集中と対照的な迷いであるとした。今回はこの二つの概念がどういった価値をもつのか、集中すべきときと迷うべきときについて考える。 目次 1 不可逆な選択2 選択の留保による空 […]
今回は、集中することについて論じる。 「集中すること」は、今日的なテーマである。その原因としては、現代社会には集中を乱すような刺激が多いため、集中力を欠きやすいということが第一にあるだろう。それゆえに、集中力向上を求める人が多いことも事実だ。しかし、そもそも集中するとは一体どういうことなのかを改めて問う必要があると思う。 今回の記事においては、集中することとは一体何なのか、集中状態の典型例を用いて […]
家に帰ったらまず手洗いをしましょう。この言葉を、私は幼い頃から何度も聞いてきた。そして、その通りにしてきたため、何も考えずとも帰ったら手洗いをするようになっている。手洗いができないときは、気持ちが悪いほどである。これに同意してくれる人は多いのではないか。 しかし、なぜ手洗いをすると手が清潔になるのか、私を含め多くの人は、よくわかっていないと思う。よくわかっていないのに、きれいになると思っている。こ […]
この批評はもともと「人それぞれの価値観とは何か」という題で公表したものですが、2022年6月末に大幅に書き換えられ、タイトルも変更しました。基本的な論題は変わっていませんが、論理展開や結論にも変更があります。 「人それぞれ」という標語が昨今あふれている。 好きな食べ物、音楽、本。どんな将来を目指すか。どういった価値観を持つか。 価値観について言えば、結婚は最たる例かもし […]