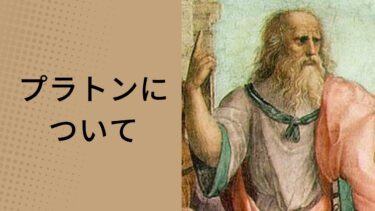前回は、ソクラテスが無知の知を自覚するきっかけとなった、デルフォイの神託とその謎、そして自己認識の正当性の条件について論じた。
今回は、ソクラテスにとって、知者であるとは何なのかを論じ、ソクラテスが自身を知者であると評価すること=自己評価の正当性と、誰かを知者であると評価するためにはどうすれば良いのかを論じる。結論から言えば、それこそが対話であり、それはその人が知者かどうかを吟味するものであった。その結果、ソクラテスは対話相手に恨みを買うことになるのである。しかし、それでもなおソクラテスは対話をやめないその理由を最後に論じる。
知者である基準
知者にふさわしい知とは何か
前回、ソクラテスの自己認識の正当性について検討した。そこでは、ソクラテスにとっての知者とは何なのかを明らかにする必要があった。そこで、今回はまず、知者であるとは何なのかを、ソクラテスの考えに即して考えていく。
さて、知者とは、何かを知っている人物であろうが、その知は何でもいいわけではないと思われる。たとえば、ちょっとした雑学のようなものも知である。だが、このような知をもっていても、その人を知者とみなすことはないだろう。このように考えると、知者に値する知というものが、他の一般的な知と区別されて存在するようである。
また、これを知っていれば知者であるといえるような知は存在しない。確かにある分野の知者でなければ一般に知らないような知はあるが、その一つの知をもって、その人を知者であると判断することはできない。むしろ、専門家のように、ある分野の集合的な知を満遍なく知っているということが、ある分野の知者である条件であろう。
以上より、知者にふさわしい知を、満遍なく知っている者が知者であるということになる。それでは、知者にふさわしい知とはなんであろうか。
この問いに対して、ソクラテスは、善美なるものについての知であるという。善美なるものの知とは、何かが善くあるとか美しくあるその原因についての知である。たとえば、ある花が美しい場合、その美しさの原因となっているものについての知である。同様に、なにかある存在や行為が善いものであるための原因についての知である。
この知は、他の一般的な知とは異なる次元にある。一般的な知とは、その存在が現にどうあるかについての知である。たとえば、目の前に花があったとして、その花が赤いことや、いい匂いがするということは、ある存在が現にどうあるかについての知である。これは、言い換えれば、情報ともいえるだろう。
こうした赤いとか、匂いがするとかいった情報が累積していき、目の前の花に関する情報を超えて、より一般化された情報となったとき、その情報は知識となり、学問となる。たとえば、チューリップという名前をつけ、その花が他の花と比較してどのような分類にあるのかといったより全体的で体系的な情報の集合が学問的な知であるといえるだろう。
しかし、こうして学問的に洗練された知もまた、一般的な花(種としてのチューリップ)の存在についての知であることに変わりはない。つまり、それは、ある存在がどのようにあるのかについての知である。
これに対して、善と美についての知は、どのようにあるべきかについての知である。善と美の両者は、ある存在がその存在のとりうる最高の状態を意味している点で共通する。つまり、良いとか美しいという概念は、存在があるべき理想の姿を指している。
たとえば、馬について考えると、よい馬、美しい馬とは、理想的な馬であり、これは大抵は速く走れる馬であろう。なぜならば、一般に馬の価値の尺度、基準は、その走力であるからである。
このように、善美なるものについての知とは、ある存在がどのようにあるべきか、その理想像についての知であり、言い換えれば、あるものが良いとか美しいと呼ばれるための原因についての知である。そして、ソクラテスは、ある個別の存在を超えて、すべての存在についてそれが善美であるための条件についての知を、善美なるものについての知と定義した。(1)
こうしてソクラテスは、善美なるものについての知、すなわち存在者一般が善美であるための原因についての知を知っていることが、知者の条件であり、自らはこれを知らないがゆえに、知者ではあり得ないと考えたのである。
知っているとはどういうことか
「この善美なるものについての知を知っている」という評価基準は、「知者であるかどうか」という評価基準よりは客観的であるようにみえる。なぜなら、この知を知っていることを示せば良いからだ。
何かを知っていることを示すためには、他者にそれを言葉で説明できればよい。たとえば、「日本の首都はどこか」と聞かれたら、それについて「東京」と答えることで、自分がその知をもっていることを証明できる。逆に、言葉で説明できない場合、正確に知っているとは言えないだろう。ソクラテスは、『弁明』において、自分が何も知らないがゆえに、人に教えたことはないと証言したのも、このことを言葉で説明できないからであった。
したがって、善美なことについて、それが何であるかを知っていれば、それに答えられる、すなわち言語化できる。たとえ、ソクラテスのように、それについて知らない人に対しても、それが言語化されうる限り、そしてその言語を理解できる限り、説明することによって伝達可能なはずだ。
逆に、知らなければ、答えられない。知らない場合に、知っている振りをしたとしても、問いに答えられなければすぐに知らないということがわかってしまう。ということは、自分がこれを知らないのに知っていると思い込んでいた場合、他人にその説明を求められて、それが明確に言葉で説明できないときには、未だそれを十分に知ってはいないということになるだろう。自分では分かった気になっていたが、うまく説明できず実はよく分かっていなかったという経験は、よくあることだろう。したがって、ある知を持っているか否かは、その知が言語化され、他人の問いに答え、他人によって検証されることで、評価されるものである。
これと同様に、「善美なるものの原因」についての知を持つか否かも、それについて言語化し、他人の問いに答え、検証されることで、客観的に評価される。
知者を訪ねるソクラテス
当時の知者とは
ソクラテスは、以上のように、自分が無知であるという自己認識を確固たるものとする。その上で、神託が提示する謎を解明しようとする。そのために、ソクラテスは、知者であると言われている人々を訪ねて歩く。『弁明』において、ソクラテスは、政治家、詩人、技術者を訪ねたと証言している。彼らは皆、人々から知者であるとみなされ、また権力者でもあった。
まず政治家は、立法者として、つまり、法律を作るための知識が必要であった。また、前回のソフィストの回でも述べたように、政治家には民衆を説得する弁論術が必要であり、この弁論術は説得力を増すために詩や格言などを引用するといった、現在でいうところの教養的な知識も含まれていた。そのため、知者の筆頭として、ソクラテスの候補に挙げらたのだった。また、詩人については、詩の中で立派なことを神に語らせることで、ソフィストの回で触れたように、アテナイ社会の道徳教育を詩が担っていた。また、ギリシア全体でオリンピックと並ぶ詩の祭典が催され、三大悲劇詩人といわれる詩人たち(アイスキュロス、ソフォクレス、エウリピデス)などが相当な名誉を得ていたことから知者とされた。職人に関しては、一般的な知者ではないが、その分野の専門的な知に関する知者であるということは間違いがない。
哲学的問答、エレンコス
そのような彼らに対して、ソクラテスは、「あなたは知者であるか=善美のことに対する知をもっているか」と尋ねるのである。そうして、ソクラテスは自身の納得する答えが相手から引き出されるまで、しつこく質問を続け、もし相手の答えに矛盾が生じれば、それを遠慮なく指摘する。このようなソクラテスの対話は、問答法(エレンコス)と呼ばれ、『弁明』において原告を問いただすシーンを初め、様々な著作に登場する。
この結果、彼らは人々から知者であるとみなされているし、彼らも自分自身を知者であると思い込んでいるが、実際は、善美の事柄の知を持っておらず、知者ではありえないと、ソクラテスは結論づけたのである。つまり、彼らは善美のことに関する知を知らないどころか、自分がそれを知らないということすら知らないということである。これは、「無知の無知」といえるだろう。
人間的知恵としての無知の知
こうしてソクラテスは、自らが無知であるにもかかわらず、神託の言うとおり、ある種の知者であることに気がつくのである。それは、自分が無知であるということを知っているという意味での知者であり、他の知者と呼ばれる人々が持っていない知であった。
これが「無知の知」または、無知の自覚と呼ばれるもので、ソクラテスの自己認識と神託をどちらも正しいものとして調停するものである。
無知を暴かれた知者たち
さて、このような問答を、アテナイの権力者であり、アテナイ市民からは知者であるとみなされている人物たちに長年にわたって、仕掛け続けることが、どのような結末を招くのかは想像に難くない。しかも、ソクラテスは、この問答を公衆の面前で行い、若者たちが見る目に前で、権力者らを論駁してしまうのである。
当然、アテナイの権力者らは、ソクラテスに対して恨みを抱くことになる。と同時に、権力者が論破されているのを見た若者たちは、それを面白がって、自らも試すようになる。こうして、ソクラテスは、権力者の面子を潰しつつ、若者にも影響を与えていったのである。その結果、ソクラテスは、「何やらよからぬことを信じ、それを若者に吹き込んだ罪」で訴えられたのである。
実際は、ソクラテスは何も若者に対して教えることはなく、むしろ、ソクラテスは権力者に教えを乞うていたのだが、その彼らが実は「善美なること」について何も知らないということが若者の面前で明らかになってしまった。そして、若者がソクラテスの真似をしだし、いよいよ面子が潰された権力者たちは、実際には何も教えてはいないが、ソクラテスが「よからぬこと」を吹き込んだことにし、それゆえに若者を堕落させたとして、訴えたのである。この「よからぬことを教えた」というものは、彼らが自らの無知を暴かれたことを隠蔽するためのでっち上げだったのである。
無知の知は何をもたらすか
アテナイにくっつけられた虻
ソクラテスのこの問答法は、権力者たちの恨みを買っていった。それはそうであろう。公衆の面前で論破され続け、面子を潰された彼らが、ソクラテスを目障りに思わないはずがない。ソクラテスもそのことには気づいていた。(2)
それにもかかわらず、ソクラテスがこの問答を続けたのは、それを神からの命であると考えたからである。それは、ソクラテスの神託の解釈の結論であった。ソクラテスは、神託の意味を、デルフォイの神殿にある言葉である「汝自身を知れ」という意味に解釈した。つまり、人間というものは、自分を過大評価してしまいがちであり、それゆえに傲慢になることがないようにという諌めの言葉であると考えた。実際、ギリシア神話には、古くから驕り高ぶった人間が、神の裁きを受け、その身の程を知ることになるというテーマが繰り返されている。この自己認識の誤りは、2000年以上前から存在する人間にとって普遍的なテーマともいえるのである。
そのように神託を解釈したソクラテスは、毎日広場へと繰り出し、善、美や徳とはなにかについて知っていると公言する、自称知者を見つけては、彼を問いただし、彼が実は何も知らないことを明らかにし続けた。
この問答法は、彼らに自分自身が本当は善美の事柄について知ってはおらず、それゆえ知者ではないということを突きつける。つまり、やや過激な方法ではあるが、彼らに無知の自覚をさせようとしたのである。
ソクラテスは、こうしてアテナイ市民たちに、自身の無知を自覚させていった。それは、まるで眠っている巨大な馬を眠りから目覚めさせる虻である、とソクラテスは言う。(『弁明』p.46)まさに、自分が無知であることすら知らない、すなわち自分がどういう存在なのか知らないという眠っているも同然の存在を覚醒させる役割を神から命じられているとソクラテスは考えていたのである。
無知の知の可能性
自分が無知であるということを知ること、これをソクラテスは人々に促していった。これは、自分が知者であると思い上がり、傲慢になっていることから抜け出させるものである。このことは、間違った自惚れた自己認識を正すことができると言う意味で、価値のあるものだろう。
だが、無知の自覚も、つまるところは、自分が無知であると言うことに留まることではないか。ソクラテスは、無知の自覚を人間的な知と呼び、善美なる事柄についての知を神的な知としたのではなかったか。
確かにその通りで、無知を自覚したからといって、知者になれるわけではない。むしろ、自分が無知であると知り、無力感に襲われることにもなるだろう。そんな無知の自覚に、積極的な意味はあるのだろうか。
ここには実は重大な問題が潜んでいるだろう。真実が時として残酷で、偽りの自己認識の方が本人にとっては幸せかもしれないのだ。しかし、ソクラテスはそうは考えない。常に正しくあることこそが幸福であると考えるのである。それゆえに、別の著作において、ソクラテスは、危害を加えるよりも危害を加えられる方が良いことだ、と主張している。ここにソクラテスの考えの根幹がある。不正を犯すことは、自らの魂を棄損する。そして、魂をより良いものにすることが、幸福であり、そのためには善とは何かを知り、それを行うしかない、と言うのである。
無知の自覚は確かに過酷なものであろう。知者であるという評価もなくなり、自己評価も下がることになるだろう。しかし、自分が無知であると自覚するからこそ、知を求めることができるのである。つまり、正しい自己認識からしか、自分をより良いものにすることはできないのである。
一生を偽りの自己認識と他人からの評価の中で、安寧に過ごすか、目を背けたくなるような自分の真の姿に目を向け、自分の欠点や課題に向き合っていくか、どちらを選ぶべきであるか。それは各々が決めることであろう。ただ、偽りの中にいるのでは、現状を偽りのまま肯定することしかできない。知ろうとするためには無知であることを知らなければならないように、自分をより良く変えていけるのは、自分を変える必要性、すなわち、正しい自己認識が必要だ。
注釈
(1) このことは『弁明』の場合、pp.24-5, p27から、読み取れる。また、他の著作ではより直接的に、善美なる事柄そのものについて対話をしているシーンが多くある。
(2)『弁明』p.27他
参考文献
プラトン (1927)『ソクラテスの弁明・クリトン』 (久保勉訳) 岩波文庫
こちらは新訳で読みやすく、KindleUnlimitedにて無料で読めます。
荻野弘之 『哲学の饗宴』 NHK出版 2003年
内山勝利(他)編 『哲学の歴史』 中央公論新社 2008年