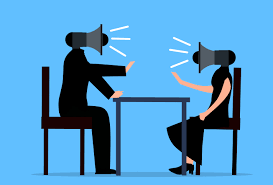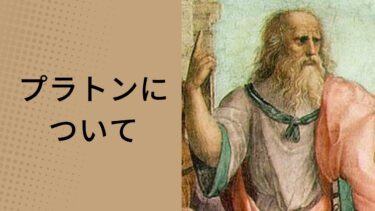はじめに
前回の記事で予告したように、今回は個々のソフィストについて紹介していく。
今回紹介するのは、ソフィストの中でも有名な人物で、プロタゴラス、ゴルギアス、アンティポンである。
ソフィストとは何かについては、こちら!
↓
ソフィストとは、紀元前5世紀中頃のギリシアで誕生し、後の古代ローマまでさまざまな形で続いた職業教師である。彼らは、それまでの古代ギリシアの伝統的な教育であったホメロスなどの詩に代わって、新たな事柄を青年に授業料をとって教育した。 この[…]
徳(アレテー)とは何か
さて、前回述べたように、ソフィストの教育内容は個々人によってさまざまであったが、彼らは徳(アレテー)を教えることを共通としていた。
この徳とは、ギシリア語でアレテーといい、そのものの持っている卓越性を意味する。たとえば、鎧のアレテーは丈夫であることであり、馬のアレテーは早く走ることである。このように、そのものの本質的な特性や目的に対する優越性を徳(アレテー)といった。このようなアレテーを、人間に対して、教育によって身につけさせるとソフィストは謳ったのである。
それでは、人間にとってのアレテーとは何か。それは、人間の人間たる本質的な能力の優越性であろうが、それは鎧や馬のように単純化することができるのだろうか。そしてまた、そのアレテーは人に教えることで身につけさせうるのだろうか。こうした問題に、ソクラテスやプラトンは取り組んだのだが、今回はソフィストたちの回答を見ていく。
プロタゴラスについて
プロタゴラスの人物像
プロタゴラスは、ゴルギアスと並んで代表的なソフィストだが、残された資料は少ない。現在残されているのは、数行の著作断片と、間接的な証言のみである。また、プラトンの対話篇『プロタゴラス』に登場するプロタゴラスの思想についても、それが本当にプロタゴラスのものであったのかはわからない。
プロタゴラスの作品が散逸した原因は、彼の過激な思想にあったとみられる。それは神の存在を否定するかのような思想であった。
神々については、私は知りえない。あるとも、ないとも、またどのような姿形をしているとも。
というのは、それを知るには妨げとなることが多いから。事柄は不明瞭で、人間の人生は短いのである。
(プロタゴラス断片4)
彼のこの発言は、直接的に神を否定しているわけではないが、神に対して疑いを投げかけている。こうしたことは、当時のアテナイにおいては、不敬罪の対象となった。その結果、彼の書物は焚書(言論統制のために本が燃やされること)とされてしまったという。それゆえに、彼の著作は、古代ギリシア後期にはもう残されていなかったようである(納富 2008, p.274-276)。
プロタゴラスの思想とは〜相対主義、万物の尺度は人間である〜
プロタゴラスにとって、人間のアレテーとは、言論を操る能力であるとされた。これは、前回見たように、アテナイが直接民主主義の国家であったため、言論によって人を説得する能力がもっとも必要とされていたからである。この言論を操る能力、弁論術に関して、プロタゴラスは相対主義を唱える。
プロタゴラスは、言論の本質として、
すべての事柄について、相対立する二つの言論が成り立つ(ディオゲネス・ラエルティオスによる証言『哲学者列伝』より)
とした。これは、当時のアテナイの国会である民会や裁判において、人々の賛成をとりつけたり、有罪を無罪にするためのテクニックであった。この弁論術は、相手さえ説得できれば自分の意見が押し通せるという直接民主制の制度を利用し権力を得るためのもので、言論の内容いかんにかかわらず、とにかく相手を説得することを目的としていた。そのため、内容が乏しかったり、実際は疑わしいことがらを技術によってもっともらしく見せるものであるとして、「弱論を強弁する」という標語のもと非難の対象となっていた。野心をもった若者たちは、このテクニックによって権力を手に入れようと試み、プロタゴラスに教えを乞うたのである。
しかし、この弱論強弁の技術はプロタゴラスにおいては、単なる政治的テクニックにとどまらなかった。この「すべての事柄において、相対立する二つの言論が成り立つ」ということは、それを主張する人間次第で、ある命題は真にも偽にもなりうるということである。これはつまり、真偽は人間から独立に存在せず、人間の論じ方次第であるということになる。これが有名な、
人間はすべての物事の尺度である
という、人間尺度説である。また、プラトンによると、プロタゴラスは、反論することの不可能性を主張していたが、このことも、真偽が絶対的には決まらないことを意味している。
このような、価値の尺度を人間おく思想を、相対主義という。この相対主義は、日常的にも使われており、個人の好みとか個人の問題とされるときには、個人間の相対主義であり、集団や国家間の相対主義もある。特に、倫理の領域において相対主義は強力であり、善とは何かという問題に関して、絶対的な基準が設けられないことを反映しているといえる。
当時のアテナイにおいても、前回扱ったように、外国のさまざまな文化・思想が入り込んできたため、それまでのアテナイにおいて絶対的な権威をもっていた法律や慣習の力が弱まったということも、この相対主義の出現と関係している。
ゴルギアスについて
ゴルギアスの人物像
ゴルギアスについては、プロタゴラスと対照的に、『ヘレネ頌』と『パラメデスの弁明』のに作品と、『あらぬものについて』という議論が残っており、プロタゴラスと同様にプラトンの対話篇において語られているゴルギアス像とは独立に、ゴルギアスの思想を知ることができる。また、いくつかの重要な後世の資料も残っている(納富 2008, p.275)。
ゴルギアスもプロタゴラスと同様に、アテナイではないポリスで生まれている。彼は、祖国レオンティノイの外交官であり、BC427年にアテナイの民会で演説を行い、独特の修辞技法(言葉を飾る技)で人々を魅了した(同上 p.282)。
ゴルギアスの思想とは
ゴルギアスの思想は、プロタゴラスの相対主義の延長線上にあるといえる。プロタゴラスは、ある事柄についてそれを真ということも偽ということもできるとする。それに対して、ゴルギアスは、言論を魔術や呪文と喩え、言論によって相手を操ることが徳であると考える。
このことは、彼の著書『あらぬものについて』に表れている。『あらぬものについて』のなかでは、まず、「(この世界には)なにもない」こと、次に「あるとしても人間には把握不能であること」、最後に「把握できたとしても他人に伝えられないこと」が示されている。この著作はパルメニデスの思想「あるものはあり、あらぬものはありえない」をふまえたもので、それを批判し、揶揄しているのである。最初の「なにもない」とは、パルメニデスのあらぬ=非存在=無と同じであり、それが把握できず言語化できないということはパルメニデスと同じことを言っている。つまり、パルメニデスとの違いは、存在=有そのものを認めないことである。しかし、この「なにもない」とは一体どういう意味なのかについては、議論の尽きない問題である。その理解の手がかりとなりうるのが、ゴルギアスの他の著作であると私は考える。
ゴルギアスの他の作品、特に『ヘレネ頌』において、ゴルギアスの言論に対する考え方がわかる。ヘレネとは、トロイア戦争の原因となった悪女と名高い美女なのだが、ゴルギアスはこの著作において、ヘレネのことを弁護する。その弁護は一見もっともらしく見える。ただ、ゴルギアスの目的は、この著作を通じて、当時のアテナイにおいて悪女とみなされていたヘレネを弁護する論述をすることで、実際に読者が説得されるということを示すことであり、これはゴルギアスの弁論術の実践なのである。つまり、ヘレネは悪人であるという強固な通念が、弁論術を伴った言論によって容易く崩されてしまうということを、読者に身をもって体感させているのである。
このように、ゴルギアスは弁論術を、皮肉や揶揄、読者への挑戦とも取れるような形で用いる。これはなぜかというと、ゴルギアスは言葉を大いなる権力者であると考え、その権力を実際に読者に対して振るっているからである。ゴルギアスによると、言葉は、その使われ方によっていかようにも効用を変えることができる。たとえば、相手を説得したり、相手を感動させたり、同じ事柄について相手に信じさせることも疑わせることもできる。
ゴルギアスは、このような言論の力で、人々を説得し操作することが徳(アレテー)であると考えた。そのため、何かが存在するのか否かといったことや、善悪についても、それは言論によって操作されるべき概念であり、それ自身言論から独立して存在する事象なのではない。つまり、言葉はあるがままを語るのではなく、言葉が対象を支配するのである。このように、ゴルギアスからは、自分の目的に応じて言論を通じて対象を規定するという点で、全てのものは自分の利益に従って人間によって規定されるべきだという主張を導出できる。この主張は、プロタゴラスのいう単なる相対主義を超えて、恣意的な相対主義とでもいうべき思想を表しているといえるだろう。
ノモスとピュシスとは
正確には誰によって提唱されたのかは不明であるが、ソフィストの言説を通じて広まり、現代にわたって用いられている対概念が、ノモスとピュシスである。ピュシスとは自然を意味するギリシア語であり、ノモスは法律・秩序を意味する。この二つの概念は、ソフィストの誕生以前にも存在したが、ソフィストの議論において両者が対置されるようになり、特有の意味を帯びるようになった。
ソフィストの文脈において、ピュシスとは、人が自然に持ち合わせている性質のことで、ノモスとは社会によって課された法や慣習のことである。この本来人間が自然に持っている性質=ピュシスが、社会の法や慣習によって不自由に歪められているという意味で、この概念対は用いられる。これは、法や慣習の絶対的権威が崩壊し、それらが相対化された結果として、あらゆる法・慣習に先立つ人間本来のあり方を想定してそれをピュシスとしたもので、この概念対もまた相対主義の帰結であるといえるだろう。
アンティポンについて
アンティポンについて、その人物像は定かではないが、アンティポンの著作『真理について』が、ノモスとピュシスの対比を用いた議論をおこなっている。アンティポンは、ピュシスとは人間の自然な性質であり、人間は必然的にピュシスに従って行為する。一方のノモスは誰かによって作られたものであり、偶然的であるため、人はそれを根拠に行為することはない、とする。むしろ、ノモスはピュシスを制限し抑圧するため悪であると論じられる。
まず、アンティポンは、ギリシア人と異邦人の区別について扱う。ギリシア人がギリシア人であるのは、法・慣習においてのことで、ギリシア人のみを尊重する根拠は、ピュシスの上にはなにもない。事実、人はその国籍に関わらず、人としての共通の性質をもっている。このように、人間がある国や集団に属しているということの根拠は、自然においては存在せず、それゆえに自国の法・慣習に従うことも根拠をもたないとする。
次に、アンティポンは、ノモスに従って行為する場合と、ピュシスに従って行為する場合を論じる。人がノモスに従って行為するときには、その行為の根拠が人為的に作られた法・慣習であるため、行為者の自発的行為ではない。これは、特にあるルールを守るか否かの場面において、説得力を持つ。たとえば、歩行者が横断歩道で信号待ちをしていて、車の気配がないときを考える。このとき、ノモス、すなわち法律上は、信号に従わなければならない。しかし、ピュシスにおいて、すなわち人間の本性においては、信号待ちを無駄な時間であると考え横断歩道を渡ろうとするだろう。このように、ピュシスは人間本来の行為を促すのに対して、ノモスはそれを制限する。
そして、最後に、人がノモスに従うことが人にとって悪になるということを、アンティポンは論じる。これは、法廷での弁論の際に際立って問題となる。法廷において、法に忠実に証言、弁明、弁護を行うことがノモス上の正義である。しかし、このように法に忠実に行為をしたとき、相手が弁論術を用いて詭弁を論じると、こちら側が不利益を被ることになる。つまり、法に忠実であるということは、自らをなんら助けることはなく、むしろ相手のノモス上の不正によって不利益すら被るのである。こうして、アンティポンはノモスの基づいた行為が、自らに害や不正を与えるということまで論じるのである。
これらの理論は当然、粗雑なものであり、ツッコミどころが多々ある。なかでも問題なのは、ノモスが必ずしも常にピュシスと対立することはないだろうということである。そもそもノモスは少なくとも原理上は、国家の成員に利益をもたらすように制定されたはずである。また、ピュシスを人間の行動を導く自然の性向であるとすると、そこにはむしろ個人や集団に害を与えかねないものも含まれるはずである。人間のもつ衝動を完全に制限なく発揮するとすれば、そのことは自明である。よって、ノモスは害ではなくむしろ善をもたらすことも事実である。
しかし、アンティポンの理論が完全に誤っているわけではないだろう。特に、ノモスの根拠が人々の約束に基づいており、それが国家や集団に相対的であることは事実であろう。また、法に従うことでむしろ、法に従わない人々によって害を被るのもその通りであろう。たとえば、ごく日常的に考えると、人は基本的には他人に対して誠実であり、これはノモス的な規範だ。この規範を守らない人々は、これを悪用することによってさまざまな詐欺を行う。この場合、ノモスに従った人はむしろ害を被っている。こうした例は枚挙にいとまがないだろう。このことは、ノモスを悪用することでノモスに従うことよりも利益を得ることができるということを意味している。もちろん、ノモスはそれに対する処罰という形で、ノモスに反したときに利益を超える損害を用意する。だがこのことは、ノモスに反したときに、後から別に制裁を加えるもので、ノモスに反することそれ自体からは損害を受けないことをノモス自身が証しているともいえるだろう。すなわち、仮にノモスに反することに罰則がないのであれば、人々はノモスに従わないとノモス自身が認めているとみなせるのである。
まとめ
アテナイの社会の動乱期において、権力を得る手段として弁論術が必要となり、それを教えるソフィストが誕生した。個々のソフィストは、その主張や、弁論のテクニックも異なっていただろう。実際、上記の相対主義やノモスとピュシスの対比は、全てのソフィストに共通する思想ではなかった。しかし、相対主義とノモスとピュシスの対比は、ソフィストの姿勢を貫徹させた先にある思想と言えるだろう。それゆえに、後世ではこの両思想がソフィストに帰されたのである。
こうしたソフィストに対して、人間の卓越性である徳(アレテー)とは何なのかを徹底的に吟味し、慣習に相対的な徳や善悪を探求したのが、ソクラテスとプラトンである。次回はそのソクラテスを扱おうと思う。
参考文献
[1] 納富信留 (2008)「ソフィスト思潮」、内山勝利(他)編『哲学の歴史』、中央公論新社
内山勝利(他)編 『哲学の歴史』 中央公論新社 2008年