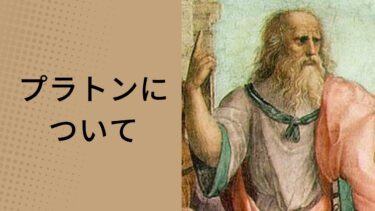思想的背景、振り返り
前回扱ったパルメニデスらエレア派が、古代ギリシア哲学に与えた影響は大きかった。それまでの哲学者は、現象を支配する根源的な原理を探求した。イオニア学派はそれを、自然の物質とし、ピタゴラスはそれを数とし、ヘラクレイトスはそれを争いとし、火を象徴とした。彼らは皆、現象世界の真のあり方、その原理、根源は何なのかという問いから出発した。それは、今、目の前にある多様な世界について、その隠れた真実を知ろうというものであった。
しかし、パルメニデスは、現象世界を否定した。彼は、経験に基づかない方法で=純粋に論理的な方法で、存在とは何かを考えた。そして、経験的な常識とは相容れない結論を、存在に関する純粋な考察から導き出した。
この純粋に論理的な思考は、経験的な根拠をもたないがゆえに、かえって強固な理論となる。
現象世界の解明を目的としたパルメニデス以前の哲学者は、世界が現にあるようにあるということが思想の無自覚的な前提としてあった。それは、彼らが、その根源を自然的な存在者としたことにもあらわれている。それは当たり前のことで、彼らの探究の目的が、現象世界の探求である以上、彼らの探究は現象世界に適合したものでなくてはならない。また、彼らの探究の目的が現象の解明にあるため、現象の枠内を超えることができない。そもそも世界があるのか否かという問いは、世界がどうなっているのかを問うことからは生じ得ない問いである。よって、彼らの探究は、世界があるということ、世界にはその要素として物質や運動があることの地盤の上で、それがどのようにあるのかを問うていることになる。
それに対して、パルメニデスの理論は、世界の存在そのものを問うている。そのため、世界の存在や、世界の中にあるとされているすべての要素(物質や運動など)を前提としない。前提とは、理論がそこから論証されるものであり、それ自体には根拠を求めないものである。そのため、前提の数が多いほど、理論の依存する対象が多くなり、脆弱性が増す。したがって、前提のより少ない理論であり、かつ以前の理論を包含する関係にあるパルメニデスの理論は、より強力なものとなっているのである。
さて、パルメニデスの理論の強固さについて長々書いたが、パルメニデスの思想はしかし、乗り越えを必要としている。それは、現象の救済である。我々は、現象世界に生きている。それを全く無視した理論は、たとえ論理的に正しく見えたとしても、それが我々にとって何になるだろう。理論が価値を持つためには、現象世界を無視してはならないのである。少なくとも、今、目の前に見える多様な世界について、理論は語らなければならない。
こうして、パルメニデスが提起した純粋に論理的な真理と、現象についての説明という両者を統合する理論を展開する必要に応えたのが、これから見ていく、多元論者たちである。
エンペドクレス
エンペドクレスとは
エンペドクレスは、BC493年ごろの生まれで、南イタリアのシケリア(シチリア)島の出身である。彼は、医者であり、詩人であり、政治家であった。また、予言者でもあったらしく、その存在は神格化され、自身が神であることを証明するために、火山であるアイトナ山の火口に身を投げたらしい。身を投げた後、青銅でできた靴の片方のみが浮かんできたという。もっとも、この話は逸話に過ぎない。
また、エンペドクレスは、パルメニデスと同じく六脚韻の詩を二つ書いており、自然哲学的宇宙論の『自然について』とそれと対応した宗教論『カルタモイ』である。それらの詩の断片は、前ソクラテス期の哲学者としては、最も多く残されている。このことからも、パルメニデスの影響がどれほど大きいかが伺える。
エンペドクレスの思想〜宇宙論〜
そんなエンペドクレスの自然についての思想についてみていく。
エンペドクレスは、このこの世界の構成要素として、万物の四つの根(テッサラ・パントン・リゾーマタ)があるとする。それは、火・空気・水・土である。そして、この四つの根が混合したり、分離したりすることで、存在者は生成される。どのような存在者になるのかは、この四つの根の混合する比率によって決定されるという。
この四つの根は、素材としての原理であり、イオニア自然学派と似てはいるが、イオニア自然学派とは異なり、あくまでも素材でありそれ自身は神的な力や生命はもたない。また、イオニア学派とは異なり、一つのものを原理とするのではなく、多数のものを原理とする多元論である。
さて、これら四つの根が究極的な構成要素であることを認めるならば、エンペドクレスはパルメニデスの存在の定義である均一性を否定したことになる。これは、エンペドクレスが現象の多様性を説明しようとするとどうしても認めざるを得ないことであった。確かにエンペドクレスは多数性を導入したが、この導入によって、パルメニデスの存在の定義である生成消滅の否定と世界の多様性を同時に説明することができるようになった。
エンペドクレスは、火・空気・水・土をそれぞれ根(リゾーマタ)とし、その根は生成も消滅もしない存在で、根が混合したり分離するしたりすることで、多様な存在者を形成しているとする。ここで注意しなければならないのは、根も根によって形成される存在者も、生成消滅するのではないということである。特に、根によって形成される存在者は、あくまでも根がそれぞれ動かされることによって生成したり消滅したりするようにみえるだけで、実際には常に変わらず根があるだけである。つまり、存在者は、根によって表現されているに過ぎないといえるだろう。
エンペドクレスは、生成消滅を、四つの根がこの世界に常に存在し続けていることによって否定する。つまり、世界は始まりも終わりもなく、そこには同じように始まりも終わりもない根が存在し、この根以外何ひとつ存在せず、すべては根の運動によって表現されるということである。人間の目には何かが新しく生まれたり、消えたりするように見える。しかしそれは、すべて元々存在する根の運動にすぎないということである。
このように、エンペドクレスは、多様に変化する現象世界の生成消滅を、それ自体は生成消滅しない根の運動によって説明することで、生成消滅しているようにみえるということと実際に生成消滅していることを区別し、現象と実在を調停しようとしたのである。この現象と実在の違いは、「そうみえる」と「実際にそうである」の違いであり、イオニア学派以来哲学的思考が避けては通れない区別であった。人間の目から見ると、根の運動が原因とはいえ、何かが生まれたり消えたりしている。たとえば、机を考えると、机は確かに生産されるし解体される。つまり、存在者のレベルでは生成消滅しているのである。しかし、エンペドクレスが否定する生成消滅とは、実在のレベルでの生成消滅であり、それは完全に何か新しいものが生まれたり、消滅したりすることである。これは、無から何かが生じうるかという問題であり、宇宙に初めからなかったものが全くのゼロから新しく生じうるのかという物理学的な問題でもある。最先端の物理学についてはわからないが、一般に質量保存の法則は、このゼロからの生成とゼロへの消滅を否定する法則である。このように考えると、エンペドクレスの思想は、一切の生成消滅を否定するパルメニデスの思想の非常識さを、実在レベルでの生成消滅を否定するというものに限定し、常識の範囲に収めたとも言えるだろう。
では、この四つの根は何によって運動するのか。この根は、イオニア自然学派の原理とは異なり、単なる素材であり、それ自身では運動する力を持たない。そのため、根の外部に純粋な力が存在し、それが根を動かす必要がある。エンペドクレスはその力を、愛と憎しみとする。愛は根同士を混合させ、憎しみは分離させる。
エンペドクレスによると、宇宙は当初、愛によって支配された状態にあった。愛が混合させる力を持つため、四つの根は互いに入り混じり、一様な球のような形をなしていた。この状態は、パルメニデスの存在の球のイメージを想起させる。だが、この状態の時には球の最外核に追いやられていた憎しみが、球の内側に入り込み始める。すると、それぞれの根が入り混じり、一体となっていた宇宙が徐々に分離し始める。憎しみの力が完全に達し、今度は愛が最外核に追いやられた時、それぞれの根は完全に分離し、バームクーヘンのような層状になる(球層体)。そしてまた、愛が力を取り戻し……、とこのように周期的な変動をくりかえす。従って、宇宙は、常に運動し続けてはいるが、それは周期的に繰り返される運動で、その法則は不変であるとするのである。
このようなエンペドクレスの宇宙論は、宇宙内部の多様性と運動を認めはするが、宇宙を一つの存在として見るならば、その存在には何もつけ加わらないし何も消え去らない。また、同じ周期の運動を繰り返している。この点を考えると、宇宙が一定で、不変であるという結論を、エンペドクレスの宇宙論から引き出しても良いかもしれない。いずれにせよ、エンペドクレスは、パルメニデスの存在論と現象の調停を行う際、仮象(そのように見えるだけ)と真実(本当にそうである)を区別し、それは運動の結果としての生成消滅のようなものと無と関係する生成消滅を区別することになり、それは宇宙の内部からの視点と宇宙を外から見た視点を区別することとなった。
なお、どうして愛と憎しみの運動が交互に入れ替わるのかは、不明である。おそらく、エンペドクレス自身、説明をしていないと思われる。仮にそうだとすれば、エンペドクレスの思想は、パルメニデスの影響を受けながらも、その出発点として生成消滅する世界を前提としていたのであり、運動が自明である以上、愛と憎しみの交代には説明が不要であったのかもしれない。
エンペドクレスの思想〜宗教詩・人体〜
エンペドクレスの人物紹介で述べたように、エンペドクレスは医者であり、政治家であり、予言者でもあった。彼は、自然哲学的宇宙論の著作『自然について』(ほとんどすべての著作を残した前ソクラテス期の哲学者がこのタイトルの著作を著したとされている)と対応する宗教的な著作『カルタモイ』というものを著している。
この宗教詩は、ピタゴラス派(活動した場所が両者ともに南イタリア)の影響を受けており、輪廻転生するダイモーンについての詩である。ダイモーンとは、神と人間の中間のような霊に近い存在であり、そのダイモーンが罪を犯し、神の大いなる誓いによって神々の下から追放され、3万年にわたってさまざまな死すべきもの(動植物)の間を輪廻転生をする。その間、苦悩に耐え禁忌を守ると、やがて人間に転生し、そして再び神との混合が可能になる、という宗教である。
この宗教詩と宇宙論の関係については、研究がさまざまなされているが、宇宙の運動の循環と、ダイモーンの罪とその赦しの循環に、並行性が見出せる。
また、このダイモーンの輪廻転生は、動植物間を輪廻転生するわけだが、その輪廻転生を可能にする根拠として、動植物間の類似性がある。例えば、植物の葉と動物の体毛は類似しており、この類似性はもともと全ての存在者が四つの根からできていることに由来する。このように、各存在者は共通の原理をもち、人間も他の存在者との共通するものを有している。人間の感覚は、この共通するものを対象としての存在者との間に共通して持つゆえに可能になる。エンペドクレスは、感覚について、人間の側にある根を受容する器官である通孔が、流出体という対象からやってくる根を感覚することで可能になるという。
このように、エンペドクレスは自身の宇宙論から、さまざまな理論を統合的に導出している。
まとめ
以上見てきたように、エンペドクレスにおいて、世界の多様性が不変の根と力によって説明された。この思想は、イオニア学派以来の、万物の原理の探究に回帰したものであると同時に、パルメニデスによって提起された存在の不変性を考慮したものでもある。このようにして、現象世界と論理との間を両立させていくことが、より多くの対象について説明可能な理論を打ち立てることになる。
次回は、同じく多元論の思想をもつアナクサゴラスについて見ていこう。