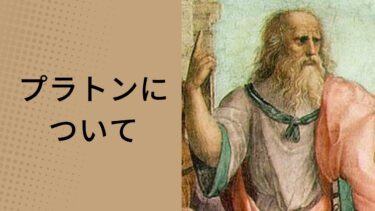今回は、ヘラクレイトスと好対照をなすパルメニデスを祖とするエレア派についてみていく。
パルメニデスはヘラクレイトスと同じように、今までの哲学者たちと異なる思想の枠組みをもつ。今までの哲学者は、万物の原理を求めた。原理はギリシア語でアルケーであり、なにかの始原、始まりの原因を意味する。つまり、今までの哲学者は、今目の前に見えている世界の根底に、目に見える世界(現象)とは異なり、その現象の原因となっている真の存在(実在)が存在すると考えていた。これは、世界を、現象と実在二つに分けて、実在が現象を根源として支えているという構造をもつという思想である。このように二重に重なった世界観とでもいうべき思想は、ヘラクレイトスによって、生成変化する世界のみを肯定する形で、一元化された。
パルメニデスは、ヘラクレイトスとは真逆な方向で、世界の一元化を試みる。それは、生成変化の否定である。彼は生成変化する多様な世界を否定し、永遠不変の世界を真のあり方だと主張するのである。この常識外れな思想は、当時も大きな反響を呼んだ。多くの批判も受けた。しかし、その論理はしぶとく、以後のギリシア哲学、とくにプラトンの哲学に大きな影響を与えている。また、それ以降、現代においても言及され続ける哲学史上の大きな問題を提示したのである。
パルメニデス(BC515-445頃)とは
パルメニデスについて、確かなことはあまりわかっていない。というのも、パルメニデスについての資料があまりないからである。分かっているのは、ピタゴラスが宗教集団を開いた場所と同じ、南イタリアのエレア出身であるということくらいで、生年や出自、人柄などもわかっていない。
ただし、パルメニデスに関する重要な資料としてプラトンの著したソクラテスの対話篇がある。そこには、当時20歳前後であったソクラテスが、65歳くらいのパルメニデスが弟子のゼノン(40歳くらいか)に会って、対話をするシーンが描かれている。このことから推測するに、前回のヘラクレイトスよりも25歳ほど年下で、BC515年くらいに生まれたとされている。
今まで扱ってきた哲学者は、慣例的に前ソクラテス期の哲学者と呼ばれているが、このパルメニデスになってようやくソクラテスと生きた年代が重なるまでに時代が下ったのである。
そのパルメニデスは、弟子のゼノンを筆頭にエレア派と呼ばれる集団をつくる。エレアとは、パルメニデスの出生地である。このエレア派もまた後世に大きな影響を及ぼす。特にゼノンは、師のパルメニデスの説を強固にするために、現在でもなお論争のある有名なアキレスと亀というパラドックスを唱えた。
パルメニデスの思想 3つの道とは
パルメニデスの表現方法
ヘラクレイトスには短い格言のような断片が残されているのに対して、パルメニデスにはパルメニデス自身が書いた詩の一部が残されている。つまり、パルメニデスは詩の形で自らの思想を残したのだ。後の回で紹介するの哲学者プラトンは劇の形で自身の思想を残しており、哲学を表現する形式は実は多様なのだ。
そんなパルメニデスの詩の内容は、謎めいたものである。主人公の「私」が夜の館から馬車に引かれ、昼と夜を隔てる門に至る。そこで女神に門を開けてもらい、昼の世界へ進んでいく。その時に、私は女神ディケに語りかけられるというストーリーになっていて、女神の語る内容に哲学的な意味が込められている。登場人物は、女神と案内人を除けば私一人で、他になんの情報もない。
このような謎めいたストーリーは、ヘクサメトロン(六脚韻)という韻文で綴られており、読み手側からすると、さらにその思想がわかりにくい表現になっている。そもそも哲学者の文章は概ねわかりにくいものなのだが、パルメニデスはヘラクレイトスと同様に、わざとわかりにくいものにしていると思われる。その理由は、ヘラクレイトスもパルメニデスも、大衆を真理を認識しない粗野な人間であると考えており、自らの思想が大衆にはそもそも理解不能であると考えていたと思われるからである。もちろん、彼らが実際のところどういう意図でその記述形式を選んだかはわからないが、両者共に大衆の無知を指摘していることは事実である。
そもそも大衆に理解できないのならば、どうしてわざわざわかりにくく書くのかと疑問に思われるが、その答えのヒントはのちに扱うプラトンに見出されるだろう。詳しくは、のちの回で扱うが、端的に言えば、大衆の下手な理解、誤解によって、自身のテクストの真の意図が埋没しないためである、と思う。実際、その哲学者の代表的な言葉とされているセリフ自体が間違っていたり、誤解されていたりすることはよくあることだ。身近な例で言えば、タイトルだけでなんとなく決めつけていた小説や映画が、実際鑑賞してみると全くイメージと違うものだったという経験はないだろうか。そのような先入観は、真の理解を妨げる。また、誤解の流布も同様である。だから、初めから大衆に対して思想へのアクセスを禁じるためにわざと難しい表現を用いるのだと思われる。
パルメニデスの思想とは
では、そのパルメニデスの思想とは何であるか。今までの哲学者は、万物の根源を求めた。その結果、さまざまな自然的な存在や秩序が原理として見出された。それらの存在が、生成変化する世界を形作る材料であり、生成変化を導く動力でもあった。つまり、この考えは、生成変化する世界を前提とし、その裏には、それを支える見えない原理があるというものである。ヘラクレイトスにおいては、そのような世界の二重性から生成変化そのものを世界の原理とする世界の一元化とでもいうべき思想があった。パルメニデスにおいても一元化が唱えられている。しかし、その一元化の方向はヘラクレイトスとは正反対のものであった。
パルメニデスは、
と考えた。つまり、今目の前に見えている全てを否定し、そんなものはないと言い張ったのである。
パルメニデスは、詩の中で女神が探求の道と呼ぶ道を三つに分ける。一つ目は、「ある」の道であり、二つ目は「あらぬ」の道である。三つ目は「あるとあらぬが入り混じっている」道である。パルメニデスはこのうち二つを偽りの道とする。それは、「あらぬ」道と、「あるとあらぬが入り混じっている」道である。なぜならば、パルメニデスにとって、「あらぬ」ということがありえないことだったからである。
「あらぬ」とは、ないということであり、ないということは、無ということだ。無とは、そもそも何も無いことなのだから、存在しないし、思考の対象にもなり得ない。よって、無=「あらぬ」は、文字通りあらぬのであって、それについて考えることは、無いものをあるもののように扱うということで誤りであることになる。
また、「あるとあらぬが入り混じっている」ということは、「あらぬ」が無であり、その存在を否定されている以上、入り混じることはありえない。
よって、ただ「ある」ことのみが真であるということになる。しかも、この「ある」とは、「あらぬ」を含まないため、単に「ある」のみである。パルメニデスは、単に「ある」ことしか認めないがゆえに、世界から生成消滅、運動、部分、多数性をすべて否定する。どういうことか。
今目の前に、現にあると誰もが信じている世界は、生成消滅し、運動し、無数の部分に分かれた多数の何かによってできている。このことは、あまりにも当たり前の事実である。しかし、パルメニデスは「あらぬものはあり得ない」という理論を盾にこれを否定する。生成消滅とは、かつてなかったところに何かが生まれることと、かつてあったところから何かがなくなることである。つまり、無から有が生じ、有が無へ転じることである。同じように運動も、移動することによって元あった場所は無になり、今いる場所が有になるものである。部分と多数性についても、それが存在するということは、異なる区別可能なものが存在しなくてはならない。区別可能ということは、AはBでないし、BはAでないということである。つまり、お互いの存在に無を混入させることによって初めて、区別が可能になる。要は、区別とは無の仲立ちが必要なのであり、無が否定されるならば部分と多数性も否定される。あるいは、部分と多数性とは、空間的な隔てが必要であるとも考えられる。ある場所までがAであり、そこから先はBになるという境目が、部分と多数性には必然的に生じる。その境目は、AでもBでもない領域でなくてはならない。これを仮にまた別の存在Cとしたとしても、今度はAとC、CとBの間が生じてしまう。よって、そこには無が想定されなくてはならないのである。こうして、無を否定すると、部分や多数性も否定されることになる。
このように、すべての無が否定された後に残るのが、端的な「ある」であり、それは前述したように、永遠不滅で、不動で、全体として一なる存在である。パルメニデスはこの存在を、完全な球というイメージを用いて説明する。その球は、どこから見ても同じ球であり静止したまま動かないとされる。こんな球のようなものが、世界の真の姿であるとパルメニデスは言うのである。このことは、常識的に考えて、受け入れ難いことだ。実際、パルメニデスやエレア派の思想は、当時から多くの批判を受けている。しかし同時に、このパルメニデスの存在の定義は、長らく西欧の神の定義として受け継がれてもいる。プラトンにおけるイデアも、アリストテレスにおける神も、キリスト教神学における神も共通してこの定義に行き着く。それは、何か完全な存在を考えた時に、あらゆる無を排除していった結果、後に残るものとしてパルメニデスのこの球のような定義に行き着くということである。もっとも、この定義を思い浮かべるためのイメージとしては、球ではなく、たとえば神の肖像など別のイメージが当てはめられうる。
エレア派〜常識と理論の乖離〜
このようなパルメニデスの説明は、論理的には妥当だと思われる。少なくとも、この論理自体は、「常識外れである」という反論以外、その論理性においては、反駁されていない。ということは、どんなに常識はずれでも、理屈としては正しいと言えるのである。
一方で常識的に間違えのないとされている世界がある。それは、今目の前に見えている多様な世界である。もう一方で、パルメニデスのいう世界がある。それは、理屈の上では正しいとされている。これら両方は相反しながら、両方とも正しいとされる。これをパラドックスという。矛盾する両者が共に正しいということ、すなわちパラドックスをどう決着させるか。パルメニデスの問題は、以降の哲学者たちにどちらの立場を取るのかを迫っている。そして、このパラドックスが解消されない以上、どちらか片方を選択するしかない。
ここに、常識をとるのか、理論をとるのかという立場の違いが現れることになる。
パルメニデスを開祖とするエレア派の有名人ゼノンは、当然、師と同じ理論を重視する立場をとる。上でも触れた、アキレスと亀などいくつものパラドックスを提出し、パルメニデスの説を裏付けようとする。そのアキレスと亀について説明しよう。
アキレスと亀とは、運動が存在しないということを証明するために考え出された一種の思考実験である。アキレスは足の速い英雄で、亀は足が遅い。当然競争すればアキレスが勝つ。では、亀にハンデを与え、たとえば数メートル先からスタートするとする。すると、スタートした最初は亀が先にいるが、徐々にアキレスが差をつめていき、いずれは追いつくはずである。常識的に考えれば、人間は数秒で亀に追いつき、追い越してしまう。しかし、運動を否定するエレア派のゼノンは、アキレスが亀に追い付かないことを証明する。
スタート直後、アキレスと亀の間には10mの差があるとしよう。アキレスは一秒間に10m進む。すると、1秒後にはアキレスと亀の差はなくなるだろうか。そうはならない。なぜなら、亀もまた少しは進むからだ。アキレスは、また走って、亀がその時いた場所にたどり着く。すると、また亀は進んでいる。こうして、アキレスがその差をつめようとしても、亀はその間に多少は先に行っているため、いつまで経っても差が埋まらないということを証明したのである。
もちろん実際には、どこかのタイミングでアキレスは亀を抜きさる。しかし、亀が進み続ける限り、今亀がいる地点にアキレスが到達したとしても、亀は先に進んでいるということも論理的には正しいように見える。このようにゼノンは、パルメニデスが唱えた常識と理論の対立を、具体的な形で示したのである。
ちなみに、このパラドックスの解答は、現在に至るまでさまざま出てはいるが、今のところこれという回答に定まってないようである。さながら、2500年前に出発した亀に未だに追いついていないアキレスのようでもある。
反常識的見方に対して〜パルメニデスとヘラクレイトス〜
さて、哲学的な営みは、日常的な常識、目の前の世界を観察し、時にはそれを疑い、その背後にある原理を明らかにしようというものである。その考えは、イオニア学派からパルメニデスにいたるまで変わっていない。
「実は、世界とはこうである」ということの探求は、目の前の世界を前提にしながらも、目の前には現れない原理へと向かう。つまり、原理の探究や、根拠づけという営みは、目の前の世界を否定していく方向に進みがちである。事実、ヘラクレイトスとパルメニデスにおいて、その傾向は頂点に達する。すなわち、今目の前に見えている世界は、「本当の世界」=実在ではなく、本来は、〇〇なのだという主張をするのである。
ヘラクレイトスの場合は、世界とは運動し続けており、何一つとして一定の存在者ではないというもので、パルメニデスの場合は、世界は生成変化も、運動も、部分も多数性もない単なる球のような存在であるという。このふたつの思想は、原理へと遡ろうという意志の結果生まれた、究極の思想であり、目の前の世界、人間の経験とはかけ離れた思想となっている。確かに、論理的には正しく、また彼らのように考えることも可能な場面もあるかもしれない。しかし、我々の感覚とは相容れない思想であることは否めないだろう。
原理へと遡る学問は、大抵この方向性を持っている。そうして、現実を疎かにしているという批判がなされる。たとえば、地動説に対しても、普通は空が動いているように見える。それが実際は地球が動いているということが発見された。この場合、その発見によって、宇宙科学は進歩しただろう。しかし、空が動いているように見えることは変わりない。その時に、「実際は」、地球が動いているのだから、空が動いているように見えるのは誤りであり錯覚であるということは、正しいのだろうか。たとえどんなに、人間の目からは、常識の中からは、そうは見えなくとも、原理的に正しいのだからそのように見なくてはならないのだろうか。
こうした問題は、一時は、科学によって世界の全てが説明されうるという思想が蔓延し、いまのところ保留に付されている現代において、重要な意味をもつ問題だ。
一体、なにが「実際」なのか、どんな資格をもって「本来はこうである」ということが言われうるのか。また、原理によってすべての見方が規定されるのは正しいのか。重要でありながらも、容易には答えの出ないこうした問いを考えることも、古代ギリシアの哲学が我々に突きつけた課題でもある。