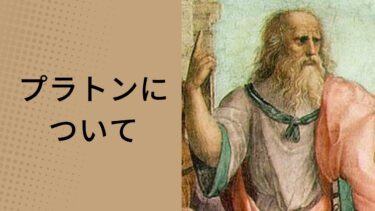前回は、ソクラテスが訴えられた理由と、それが事実無根であることを述べた。そして、それにもかかわらず、ソクラテスが訴えられたのは、彼が人々、特にアテナイの有力者から恨みを買っていたからだった。そして、その原因は、ソクラテスが始めた対話・問答にあった。
ソクラテスがなぜ対話を始めたのかという経緯と対話の結果について、今回と次回の2回に分けて紹介する。
今回は、まず、「無知の知」の概要に触れ、「無知の知」を自覚するに至る過程の発端から辿っていく。まず第一歩目は、デルフォイの神託であり、その神託は、ソクラテスに謎を突きつける。そして、その謎が謎である所以たる自己認識について考える。最後に、その論考をベースに、ソクラテスの自己認識が正しいのかどうかを考える。
無知の知のきっかけ
無知の知という人間的知恵
ソクラテスは、『ソクラテスの弁明』にて、自身を知者だとは思ったことはないと語る。それどころか、自らをなにも知らない者であると思っている。それにもかかわらず、ソクラテスは、青年によからぬことを吹き込んで、堕落させたと訴えられた。もし、なにも知らない者であるならば、何かを教えることも、青年を堕落させることもできないではないか。
ソクラテスはそれについて、自らの推論を語る。
ソクラテスは、自分は確かに何も知らず、知者ではないが、ある人間的な知恵をもっていると言う。その人間的な知恵とは、自分がなにも知らないということを知っているという知恵である。つまり、無知を自覚しているということである。そしてこの自覚を、多くの人々がもっておらず、その点において、すなわち無知であるのに知者であると自覚しているのか、それとも無知であることをそのまま自覚しているのかという点において、自分の方がわずかに他の人々よりも知者であると、ソクラテスは考えている。
ソクラテスは自分が無知であるということには、初めから気づいていた。しかし、無知の自覚が、他の多くの人々、とくに知者だと思われている人にはできておらず、無知の自覚が一つの人間的な知恵であるということは気づかなかった。それを気づかせるきっかけとなったのがデルフォイの神託であった。
デルフォイの神託
ソクラテスが、無知の知を自覚をするきっかけは、デルフォイの神託であった。デルフォイの神託とは、アテナイから少し離れた場所にあるアポロン神を祀った神殿からのお告げのことである。このアポロン神殿は、古来から神託を授ける神殿として、ポリスの政治的決定の際に重用されていた。(1)
ソクラテスの場合は、彼の親友であるカイレポンという人物を通して、間接的にソクラテスに対して神託が下された。カレイポンはかねてからソクラテスの知恵や道徳心を尊敬していたため、アポロン神に「誰か、ソクラテス以上の知者がいるだろうか」というお伺いを立てた。それに対して、神託を告げる巫女は「誰もいない」と言った。つまり、ソクラテス以上の知者は誰もいないという神託が下されたのである。ソクラテスは、この神託を聞き戸惑った。なぜならば、ソクラテスは自分自身を知者であるとは、全く思っていなかったからである。そしてこの神託を謎であると捉えた。(2)
謎とは古代ギリシア語で、アイニグマ(ainigma)であり、英語のエニグマ(暗号)の語源である。ソクラテスにとって、神託とは謎であった。それは、二つの事実が相反しているということである。
一つは、「ソクラテスは無知である」ということである。これは自己認識である。もう一つは、「ソクラテス以上の知者はいない」という神託である。これは、神託=神の言葉である以上間違っているはずがないということである。
つまり、どちらも正しいはずの事柄が、二律背反になってしまっているのである。そのため、ソクラテスはしばらく思い悩み、やがて一つの解決策を思いつく。それが、神託探求法(『弁明』p.24)と呼ばれるものである。これは、自分より賢いと思われる人間を訪ねていき、自分の知らないことをその人々から聞き出すことで、神託の反証をしようというものである。
この策は、実はかなり危険なものではないだろうか。ソクラテスは、自身にとって矛盾する二項のうち、自己認識の方に信を置き、神託の方を検証したのである。しかも、『弁明』には、明確に「反証」という言葉が使われている。(p.24) したがって、このように信仰を危険に晒してまで、ソクラテスは自己認識に対して自信をもっていたといえる。
評価の正当性とは〜自己評価の困難さ〜
ここで少し本論を外れて、自己認識とは何か、どのような自己認識があり得るのか、どのような自己認識が正しいといえるのかについて論じる。この章は独立した一つの論考であるため、要点を押さえたい方は飛ばしても問題ない。ただ、ソクラテスは、この自己認識を、ある意味神託以上に信じたのであり、それゆえ、自己認識についてここ考えておく意味があると思う。
自己認識とは、文字通り、自分が自分を認識することである。基本的には自分自身のことは、自分が一番よく知っていると言われるが、自分で自分を認識するがゆえに陥りやすい問題もある。たとえば、人は自分のことを過大評価、あるいは過小評価することがあるだろう。このように自己自身についての自己認識を誤る条件を考えてみると、主に二つあるのではないかと思われる。
まず第一に、認識の基準が曖昧なときである。たとえば、「私は子供っぽい・大人びている」などのように、認識基準が曖昧で定まっていない場合に認識を誤りうる。子供っぽいと大人びているという両者を隔てる基準が明確には存在しないし、大抵の場合、ある側面では前者で、別の側面では後者であるからである。
しかし、「私はアメリカの首都を知っているか」というような基準を採用するとき、自己認識を誤まることはない。なぜならば、この基準は明確で、客観的だからである。したがって、認識の基準が明確で、あるときにはAであるときにはBというようにならず、一意(ひと通り)に定まるときには、自己認識は誤らないといえる。
第二の条件は、第一の条件のなかでも、特に自己認識を誤りやすいケースとして、自己を評価するときである。これは自己評価ともいえる。自己評価とは、自己をある評価基準に照らし合わせて、良いか悪いかという価値の判断をすることである。第一の条件では、自己がAであるか否かという判断に、価値が入り込まず、それゆえ自己が何であるかという単なる事実の認識であったが、第二の条件では、自己を価値的に評価するという別の判断になった。これは、単に自己がAであるという認識の上に、それが良いか悪いかという判断が加わったのではなく、あらかじめ良い・悪いとされている基準で自己を認識するということである。
このことは、第一の条件のような、まず自己がありそれを認識するという自己認識ではなく、まず評価基準が存在し、それに則って自己を高く評価したいという、自己認識の順序の逆転が生じる。つまり、自己評価においては、評価する主体と、評価される客体が同一、または利害関係を持つときに、それに対する肯定または否定を含意する評価をする動機づけがなされるということになる。簡単に言えば、自分自身の評価あるいは、自分の仲間あるいは対立者に対して、その価値に関する評価をするとき、人は評価を歪めやすいということである。多くの人は、自分や仲間を高く評価したいし、自分に敵対する人や集団を悪く言いたいということだ。そして、それはあらかじめ良いとされている基準に自分たちを当てはめて、自己評価をしようとするということであり、これが順序の逆転なのである。
初めから高く評価したいと動機づけられた認識が、自己評価であるのだが、実はこの自己評価を分析すると、意外と面白い。
そもそも自己評価とは、自分を自分で評価することであり、評価するのもされるのも自分という、一人相撲のようなものだ。ゆえに、もし自分が望むならば、いくらでも自分を高く(低く)評価することができるはずである。そして、それは正しい評価となる。なぜならば、評価とは評価基準に照らし合わせることで行うものであるため、その評価基準を自分で決めている以上、その自己評価は正しいことになるからである。
たとえば、「私は世界で一番優れた人間である。」と自己評価したとしよう。そして、評価基準は自分で作ることができるため、「私であることが、優れた人間である条件だ」とすることができる。となると、自分で作ったこの評価基準に当てはまるのは、自分しかいないため、自分が最も優れた人間であることになる。この評価に論理的な間違いはない。
しかし、人はこのような自己評価は行わないし、納得もしない。自己評価とは自分で自分を評価することである以上、自分をどのように評価しようが自由なのにもかかわらず、人は「あまりにも恣意的な評価」は行わないのだ。では、どのような評価を行うのかというと、無理のない範囲で自分を高く評価するのである。この無理のない範囲というのは、客観性を損なわない範囲ということである。
具体的には、「私は優れた人間だ」と自己評価するとき、いくつかの客観的と思われる評価基準を参考にし、自己評価する。誰かに「あなたは優秀な人だ」と言われたとか、何らかの試験でいい成績を取ったといったことである。こうした客観的な評価基準を根拠として採用し、自己評価を行うため、あまりにも恣意的な評価は行われない。けれども、自分を高く評価したいという動機が介在するため、いくつもある客観的な評価基準の中から、自分に有利な基準を組み合わせて、それを根拠に自己評価を行うことになる。
したがって、自己評価とは、自分が自分自身に対して下す評価であり、その評価には、ある程度の客観性をもたせつつも、自分の望む評価を下すための客観的な基準を恣意的に集める可能性が高いということである。もっとも、どの程度恣意的に評価するのかは、それぞれ異なるだろう。ただ、おそらく原理的に、人は自らを自らの望むように評価しようとすることからは逃れられないのではないかと私は考えている。そのため、第一の条件のように、評価基準自体の客観性が完全であるとき以外は、自己評価というものはその人の欲望が投影されているものだと考える必要があるだろう。このことに関する厳密な論証は、別の記事で扱うことになるだろう。
結論としては、自己認識を行う際、その基準が完全に客観的である場合(「私はアメリカの首都を知っているか、とか」)、その認識は正しいといえるが、その基準が曖昧で、かつそれが価値判断であり、複数の評価基準を根拠としている場合は、少なからず自分の欲望が投影されていると考えるべきである、というものである。
ソクラテスの自己認識
本論に戻る。
ソクラテスは神託を反証しようと思うほどに、自己認識に対して自信をもっていたのだった。では、そんなソクラテスの自己認識は正当だろうか。
上記で検討した結果は、自己認識の基準が明確であるか、明確でない場合、価値判断が含まれていないときに、正確な認識ができる可能性が高いというものだった。ここでの認識基準は、「ソクラテスは知者であるかどうか」である。この基準は客観的なものだろうか。それを解明するには、ソクラテスにとって、知者という概念が定義可能であったのか、またそうだとすればその定義とはなんであったのかを明らかにする必要がある。
まとめ
今回は、デルフォイの神託によって浮き彫りとなった自己認識の問題を主に扱った。ソクラテスの自分が無知であるという自己認識が、正しいものなのかどうかについては、そもそも「知者であるとは?」が明らかにならなければならない。
次回は、ソクラテスの挙げる知者の条件を検討し、ソクラテスが無知であることがどういうことなのか、逆に知者であるとはどういうことなのかを論じ、神託を検証するために知者と呼ばれる人々との対話とその結果をみていく。
この過程で、何かを知っているとはどういうことなのか、知者と呼ばれるに相応しい知とは何なのか、またソクラテスにとって恨みを買って死刑に処されるよりも重要なことはなんなのかといったことが明らかになる。
注釈
(1) 『哲学の饗宴』p.31
(2)『弁明』p.23, 同上
参考文献
プラトン (1927)『ソクラテスの弁明・クリトン』 (久保勉訳) 岩波文庫
こちらは新訳で読みやすく、KindleUnlimitedにて無料で読めます。
荻野弘之 『哲学の饗宴』 NHK出版 2003年
内山勝利(他)編 『哲学の歴史』 中央公論新社 2008年