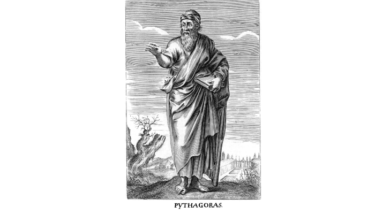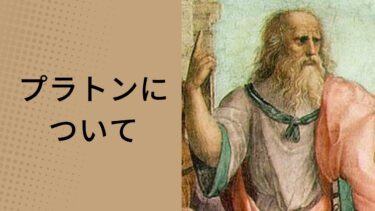この記事では、イオニア地方のミレトスで発展した思想とその思想家(タレス、アナクシマンドロス、アナクシメネス)を総称して、イオニア学派とします。これはミレトス派と同じ意味で、Ionian schoolの訳です。
前回の【古代ギリシア哲学1】で述べたように、哲学とは何かについては、議論が尽きない。しかし、哲学はいつ、誰によって始められたのかという問いについては、答えの一応の一致をみている。
それは、紀元前6世紀前半(紀元前600年〜550年前後)の人物、タレスによってであるとされている。そう考えたのは、アリストテレスであり、自著の『形而上学』においてその記述がある。では、アリストテレスは、なぜタレスを哲学の始まりと考えたのか、また、タレスは、そしてその弟子たちのミレトス派あるいはイオニア自然学派はどのような思想をもっていたのかを紐解いていきたい。
イオニア自然学派
まず、イオニア地方のミレトスという町について簡単に触れておこう。


出典:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%8B%E3%82%A2#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Turkey_ancient_region_map_ionia.JPG
下の図は、小アジア、現在のトルコの地中海に突き出した半島と、トルコのイスタンブールのあるバルカン半島の先端である。
黄色く塗られているところがイオニア地方で、その中にミレトスがあった。しかし現在は、遺跡しか残っていない。
上の図は、古代ギリシア語の方言の分布図であるが、この古代ギリシア語の分布からも分かるように、エーゲ海を中心にその周辺にいくつもの都市国家があった。ミレトスは、対岸のギリシア諸都市との貿易で栄え、東方の文化との接触もある自由で先進的な町だったといわれている。
タレス(BC625年頃生まれたとされている)
イオニア自然学派の創始者のタレスについて見ていこう。
タレスには、さまざまな逸話が残されており、ギリシア七賢人の筆頭とされている。半ば伝説化された人物ではあるが、複数の古代ギリシアの文献に名を残しており、実在したことは間違いないようだ。さまざまな愉快な逸話は、別の回で紹介するとして、ここではタレスが哲学者の始まりだと言われるその理由を、その思想を通して見ていく。
タレスは、「万物の原理(アルケー)は水である」と考えた。
万物の原理が水であるということ、その何が哲学の始まりなのだろうか。
確かに水は重要である。生きていく上で欠かせないし、水や海は生命の母ともされる。世界各地の宗教が、水の神様を祀っている。ギリシア神話にも海の神ポセイドンが存在した。
このように、水について考えてみると、一口に水と言っても、そこにはさまざまな側面があるように思われる。
- 水をH2Oで表すと、水を化学的な組成として扱うことになる。
- 人間の体の60%は水でできているというと、生物、人体との関係においての水になる。
- 神社のお清めの水は、神聖なものになる。
- 暑い夏に飲む水は、爽快な気分にさせてくれる。
では、タレスは水をどのようなものと考えたのか。
それは、万物の原理、すなわち全てのものがそこから生まれ、そこに帰っていくような、素材でもあり、神秘的でもあるようなそんな水である。
世界には多種多様な生物、無生物、人工物がある。そして、それらはいつか形を失い、滅びていく。全てのものは、過去のある時点で生まれ、そして未来のある時点で消滅する、そのような有限な存在者(存在するものという哲学用語)である。それらの存在者は、かつて生まれる前は自分自身とは異なる形を持っていたし、また滅びた後も自分とは異なる形を持つ。土の栄養や水は、植物の一部になり、その植物がまた動物の一部になる。そして動物が死ぬと、土に帰り、また植物の栄養となる。
このように、自然は常に生まれ滅び生まれを繰り返している。これを生成流転、生成変化として古代ギリシア人は捉えた。形あるものは必ず壊れるという言葉があるように、形は常に変わり続ける。では、その形をとっているそのもの、さまざまな形へと姿を変えるそのものはどうか。
土は捏ねられ、壺になるかもしれない。そして壊され、茶碗になるかもしれない。形は変わるが、壺や茶碗が土からできていることに変わりはない。そのように、形を受け入れ、変化し続ける存在は、生まれては滅びる有限な存在である形をとった存在者とは異なり、常に変わらずあり続けるのではないか。つまり、それは無限な存在、この世の生成変化を司る原理なのではないか。
タレスは、その意味での原理を水だと言った。水は自在に姿形を変え、あらゆる生命に必要不可欠である。まさに、形を受け入れるにはふさわしい存在だろう。
しかし、原理としての水は、ただ単に存在者の素材であるだけではない。
万有は神々に満ちている
タレスはこのように考えていた。つまり、万物の原理である水は、単なる物質ではなく、神秘的で生命的な存在でもあったのである。考えてみれば、単にそこにあるだけで、自らは何もしないような素材、材料のような物質を、万物の原理というには物足りない。あらゆるものに形を変え、究極的には全てのものがそれからできているような存在は、神秘的な力を持っていて、自らが自らの生成変化の原因なのである。このように、物質に生命があると考える考え方を、物活論という。日本の八百万の神などもこれに近いと思われる。
まとめると、タレスは、素材+生命としての水を、万物の根源と考えたといえる。
アナクシマンドロス(BC610〜540とされている)
次に、タレスの弟子とされ、イオニア自然学派に数えられるアナクシマンドロスについて見ていこう。(1)
イオニア自然学派の基本的な考え方は、タレスと同じで、何らかの物質が、自らは不変のまま生成変化する。この物質が万物の根源であるというものである。
では、アナクシマンドロスの固有な点は何かというと、
万物の原理は、無限なるもの(ト・アペイロン)である
としたことである。
無限なるものとは、水よりも、より単純で、形を持たないものである。素材としての原理を突き詰めた結果、全ての変化を受け入れる存在は、それ自体にあらゆる形、限定性を持たないものに行き着く。なぜかというと、素材はそれが表す形を表現しようとすればするほど、自らの個性を消していく必要があるからである。
どういうことか。何らかの素材で作品を製作しようとする。その時、その素材が自由自在に形を変えられる物であるほど、作品の製作は楽になるし、より多くの可能性を表現できる。例えば、芸術作品の製作を考えてみる。何かを製作する時、誰もダイアモンドで作ろうとは思わないだろう。ダイアモンドは、まず非常に硬く、変化を受け入れにくい。さらには、ダイアモンドという素材そのものが、もうすでに強い意味(貴重な宝石であるとか、値段が高いとか)を持っていて、それを表現のための手段、媒体にはしにくいだろう。仮に、ダイアモンドでオブジェを作った時、それはオブジェというよりもダイアモンドの塊を意味してしまうだろう。少なくとも、それがダイアモンドであるということを考えないで、単に表現されたオブジェであるとして見ることはできない。つまり、素材が素材であることを受け入れず、形・意味を表現してくれない。要は存在感が強すぎるのである。これが、木でできたオブジェだったら、オブジェの形、それが何を意味しているのかについて、それが何でできているかを忘れて、考えることができるだろう。
製作や芸術について考えるならば、ダイアモンドでゴミ箱を作れば、それはそれで風刺的な意味を持つだろうが、それはすでにダイアモンドもつ意味を前提とした作品である。ここで問題となっているのは、そもそもの存在者の生成の条件としての素材であり、意味の変化以前に意味の誕生の場なのである。
話が複雑になってしまっただろうか。万物の原理を問うという問題は、生成変化の現場に立ち会うことになり、そこでは何らかの素材によって何らかの形ある存在者が生まれる。つまり、無形のものから有形のものが生じる。ということは、その場で初めて意味が生じると言えるのである。その時、形・意味は、それを表現するための素材を消し去ることで初めてその成立が可能になる。つまり、形・意味の出現と素材・媒体の消滅は同時に生じるなければならない。素材の方が形を受け入れることを抵抗しては、形や意味が生じないのである。よってより存在感の薄い、主張をしない存在が、そのような素材=万物の原理に相応しいということになる。アナクシマンドロスは、こういった理由で、水よりももっと非限定的な存在である、抽象的な「無限なものを」を万物の原理にしたと思われる。
以上の議論は、筆者(sou)による解釈が多分に含まれており、アナクシマンドロスの意図を汲み取っているかどうかはわからない。だが、この議論は大きな発展性をもっており、現代の哲学や芸術論や言語論(文字はまさに自ら素材性を抹消し、純粋な意味を伝達する媒体となる。このことは、読みにくい文字や書道の文字などが、その読み方がわからない=意味がわからないということ、あるいは文字の忘れられていた芸術性を通して、文字の素材性を復元することを考えてみるといいかもしれない)につながる重要な哲学的問題なのである。
アナクシメネス(BC586年頃生まれたとされる)
アナクシメネスはアナクシマンドロスの弟子であり、タレスの孫弟子にあたるとされている。
アナクシメネスも、タレスやアナクシマンドロスに従って、
万物の原理は、空気である
と考えた。
これは、アナクシマンドロスと同じ思考の延長線で、水よりもより単純で無限定な物質であり、かつアナクシマンドロスの無限定なものという抽象的な存在よりもより具体的で実在する存在であるという点で、アナクシマンドロスの考えを進化させたものになる。
アナクシメネスにとって、空気とは質料的(素材的)な原理であると同時に、生成変化の原理でもあった。アナクシメネスは、この空気が、収縮し濃くなったり、膨張し薄くなったりすることで、単純な物質が生まれると考えた。具体的には、空気が濃く、重くなると、風になり、雲になり、水になり、最終的に石になる。薄く、軽くなると、火になるとした。確かに、いつもは存在を感じない空気が、風になると空気の圧力を感じ、重さを感じるようになる。また、雲は目に見えるため、空気がさらに濃くなったと考えても不思議ではない。
また、現代の科学の目線から考えても、空気を熱すると膨張するし、逆に冷やすと収縮するため、部分的には現代とも適合する考えだろう。
アナクシメネスは、空気をその物理的性質によって万物の原理とした一面もあるだろうが、より本質的には、タレスのような物活論的な考えが根底にあったと思われる。それは、空気=息であり、この息が魂と同一視されていて、空気によって宇宙が満たされているということが、息=魂によって宇宙が満たされているということにつながるということである。いわば、空気という生命を持った根源的な原理によって、万物は作られており、運動をしているという考えである。そして、このもっとも根源的な原理により、通常は相反するように見える、火と水といった単純な物質が、同じ原理から生まれているという説明ができるのである。
さらに、このようにして生まれた単純な物質が結合して、さまざまな存在者が生まれるとアナクシメネスは考えた。
まとめ〜アリストテレスの考える哲学の始まりとは〜
以上のように、イオニア自然学派は、それ自体が生命を持ち運動するような単純で無限定な物質が、それ自身は変わることなく、生成変化によって生じる形を受け入れる、そのような物活論的な素材を、万物の原理(アルケー)とする。
重要なのは、以上に辿ってきたような、自然に対する考え方である。多様な存在者に満ちた自然、常に生成変化し続ける自然の中に、それ自体は変わることなく存在し、全ての生成変化がそれに基づくような原理を想像すること。それは、目に見える世界を観察し、経験することから始まり、その世界を成立させる目には見えない原理へと向かうのである。
このような、多様で一見すると無秩序な自然が、ある原理によって導かれているという発想は、原理という秩序的で理性的な存在を必要とする。つまり、自然に原理を求める発想は、あらかじめ秩序的で理性的な説明を求めており、あらかじめ自然は秩序に従属するものであるという前提をもっている。すると、人間は初めからそこに秩序を見出そうとしているからこそ、自然の中に秩序を見ているともいえることになる。仮にそうだとすると、人間は自然の中に、自らの認識の方法である秩序性を投影していることになり、自然の中に理性的な法則が見出されるのは、自分自身に原因があり、自然が秩序的であるということの根拠が自然ではなく自分=人間=主観の側にある、ということになる。
このような、自然と人間の関係の問題は、後世の哲学に引き継がれ、現在も完全に解決されたとは言えない。
しかし、今はもう一度古代ギリシアに戻ろう。アリストテレスは、イオニア自然学派の、自然の中に普遍の原理を探求するというこの態度を、哲学の態度であると考え、そこに哲学の始まりを見たといえる。
古代ギリシアには、ロゴスという言葉がある。ロゴスは多義的で、秩序や数比などといった自然界の原理を意味すると同時に、言葉という意味もあった。そして、総じて理性という意味もある。この言葉は、自然と人間の間には、共通の理性が存在し、理性によって人間は自然を理解できるという価値観を表すものである。
自然と人間の共通の次元である理性によって世界を見ること。ここに、ギリシア哲学の神話からの離陸があるように思われる。
この回はここで一旦終わりにして、次回は、誰もが名前を聞いたことのある古代ギリシアの有名人、ピタゴラスを見ながら、古代ギリシア哲学の知の脈絡とアリストテレスの思惑を再び探ってみたいと思う。
注釈
(1)タレスの弟子がアナクシマンドロスで、その弟子がアナクシメネスであったというのは、半ば伝説であり、真偽は不明である。確かなのは、年代順であることと、同じ地域で活動したことである。
哲学教授であるピーター・アダムソンのHISTORY OF PHILOSOPHY WITHOUT ANY GAPSというポッドキャストでは、このような師匠と弟子の関係付けが、古代ギリシアではよく行われていたことが指摘されている。
参考文献
荻野弘之 『哲学の原風景』 NHK出版 1999年
内山勝利(他)編 『哲学の歴史』 中央公論新社 2008年